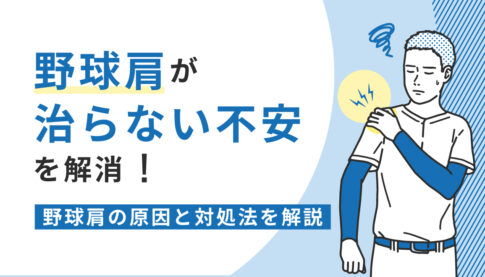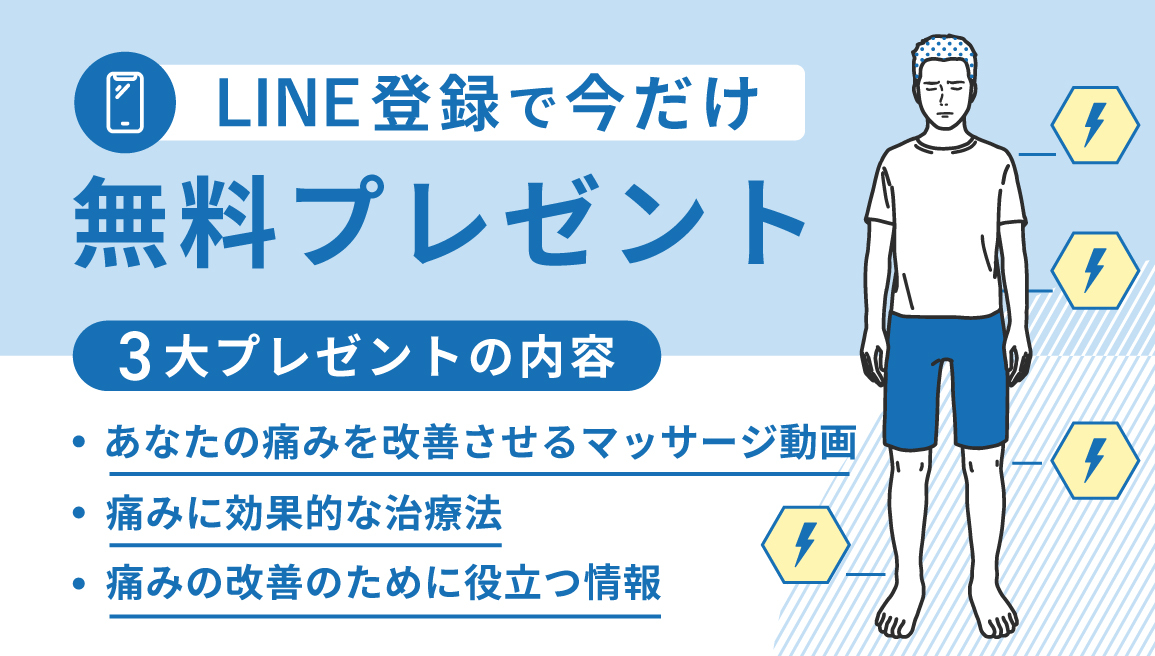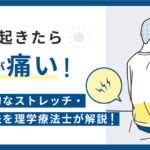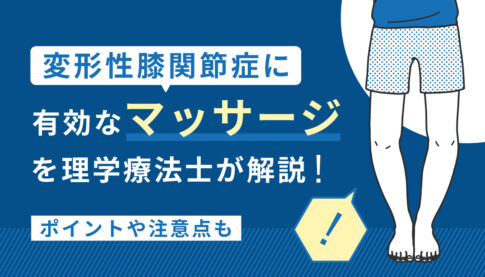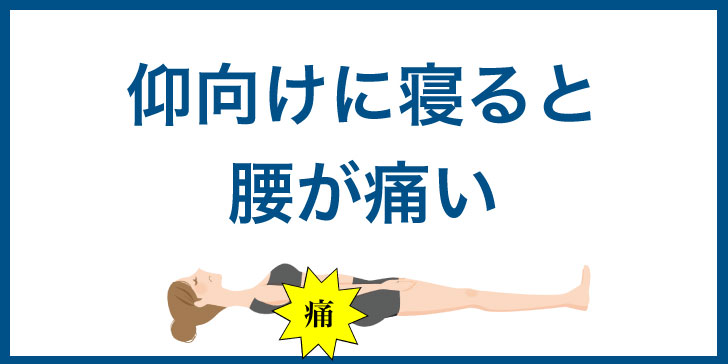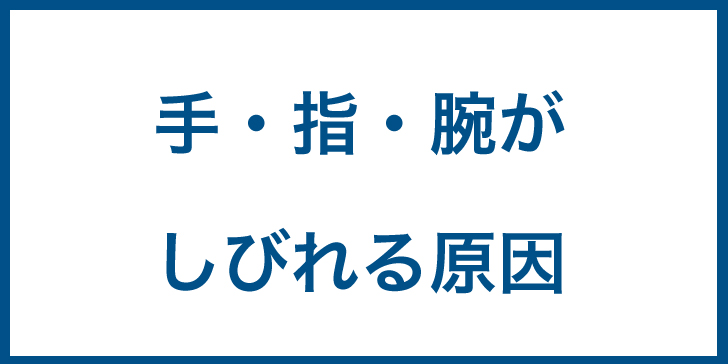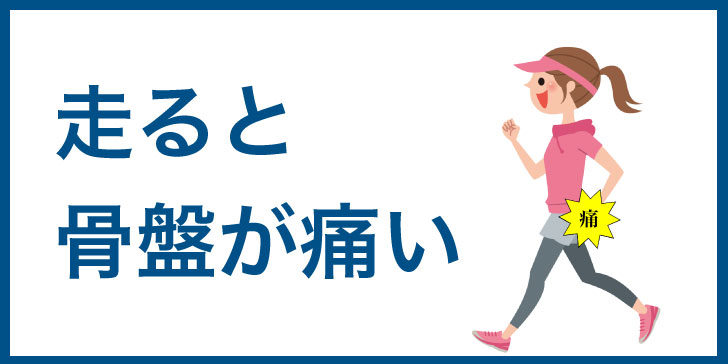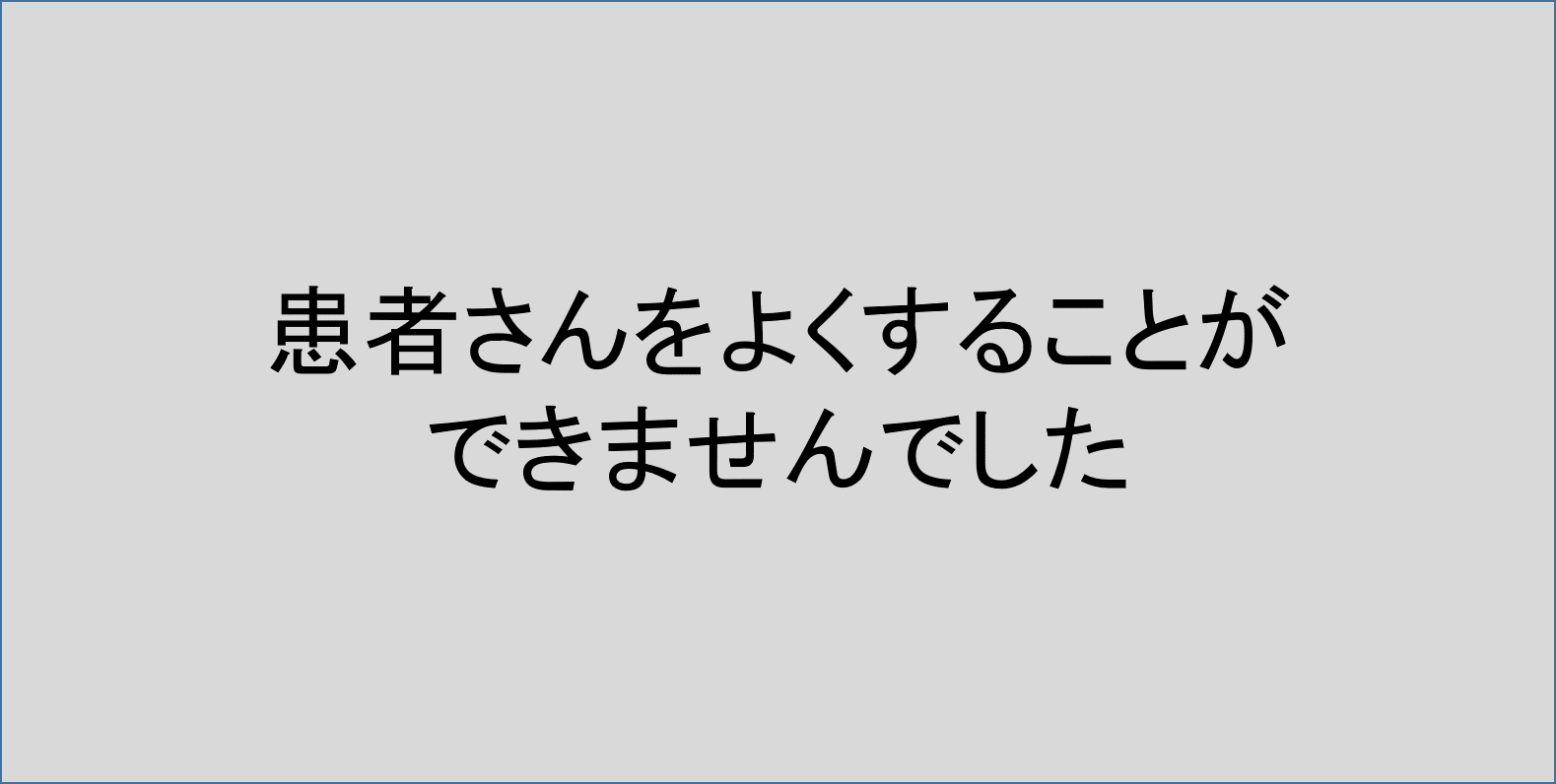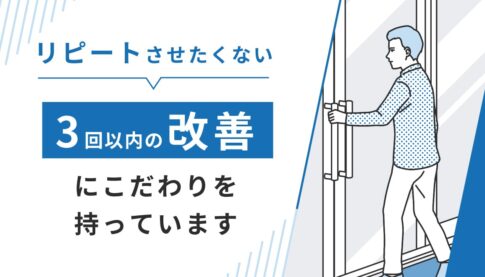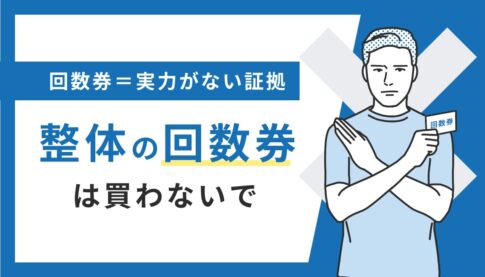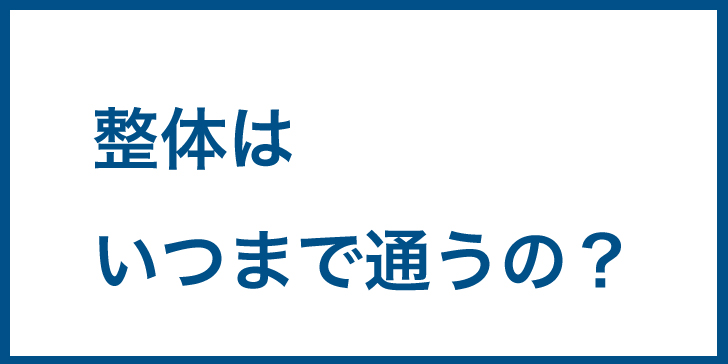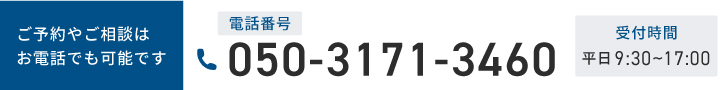野球でボールを投げると肩が痛くなって困っている方へ。
野球肩の痛みを軽減する効果的なストレッチがあることをご存知ですか?
肩の痛みは野球選手に多く、特に投球時の肩の怪我が多いです。
そんな投球時の痛みや違和感を和らげるための誰でも簡単に行える効果的なストレッチがあるんです。
本記事では、ボールを投げる前後に行うべきストレッチから、具体的な方法、注意すべきポイントまで、記事を通して詳しく解説しています。
また、どの動作で痛みが発生し、制限されているのかをチェックするコツもご紹介していきます。
詳しく知りたい方はこのまま読み進めてください。
目次
野球肩の痛みを取るストレッチ|3つのコツ
野球肩の痛みは、プロのスポーツ選手にもアマチュア、部活動の選手にも共通する問題です。
深刻な怪我のリスクを減らしながら、肩の痛みの再発を防ぐために、エクササイズ、ストレッチ、適切なウォームアップ技術を行うことが重要です。
原因としては様々ですが、その内の1つに腱板損傷が挙げられます。
腱板損傷とは、4つの筋肉を総称して腱板筋群と呼び、これらの内のどれか、あるいは複数の筋肉が損傷することを腱板損傷と呼びます。
肩の運動障害・運動痛・夜間痛を訴えますが、夜間痛で睡眠がとれないことが受診する一番の理由です。
運動痛はありますが、多くの患者さんは肩の挙上は可能です。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
肩の痛みを緩和させるためには、まず、どの動作が痛みを引き起こすのか、どの動作が制限されているのかを確認することが大切です。
そのためには、肩の不快な部分を探し、どの動作が痛みと関連しているのかを探すことから始めます。
ここでは、肩の痛みを管理しながら活動を続けるための3つのコツを紹介します。
腱板損傷についてや野球肩について詳しくは下記の記事にまとめてあります。
どの動きで痛みが出るかをチェック
どの動作が痛みを引き起こすのかを知ることは重要です。
投球動作は、大きく分けると5つに分けて考えることができます。
- 片足が地面から離れるワインドアップ期
- 挙げた片足が地面に着き、腕が後ろへ回るコックアップ期
- 後ろに回った腕が前方に振り出され、ボールが指から離れる加速期
- 指からボールが離れた後の減速期
- 腕が完全に振り下ろされるまでのフォロースロー期
肩の痛みが上記の5つのどこで発生するのか、どの時期の動きに問題があるのかなど、5つの時期に分けて考えることで、痛みの原因をある程度絞ることができます。
例えば、コックアップ期では、肩を外にひねる外旋の可動域が必要ですが、外旋させようとすると肩の後ろに鋭い痛みが走ることに気づくかもしれません。
この動きと痛みの情報は、肩のストレッチをするときに役立ちます。
どの動きが制限されているかをチェック
どの動きで痛みが出るのかをチェックしたら、どの動きで可動域に制限があるのかをチェックしましょう。
肩関節の可動域の制限を見るには、腕を身体の横に垂らした下垂位、腕を身体の横から肩の高さまで挙げた90度外転位、腕を身体の正面から真っ直ぐ肩の高さまで挙げた90度屈曲位、それぞれで外旋と内にひねる内旋の動きをチェックしましょう。
これら3つの位置それぞれで伸ばされる筋肉が違うので、どの位置で可動域が制限されているかでストレッチの方法も異なります。
肩だけではなく関連する部位も
肩だけでなく、関連する部位のストレッチも重要です。
首や背中、体幹には、肩の動きに寄与する筋肉がいくつかありますので、これらの他の筋肉をストレッチすることで、痛みを和らげることができます。
野球肩の痛みを取るために|動きのチェック法
肩を動かす際には、動作が肩に与える影響を確認することが大切です。
肩を動かしながら、違和感のある部分、鋭い痛みや鈍い痛み、しびれや痛みなどの感覚に注意しましょう。
肩の広い範囲の動きに関与する肩の筋肉は、過度に使用されて痛み、痛みを引き起こす可能性があります。
野球の肩の痛みを取り除こうとするとき、どのような動きが不快感を引き起こすかを理解することが重要です。
そのために、以下の質問に答えてみてください。
- 特定の動作中に痛みを感じたか?
- 上腕と前腕のどちらが痛いか?
- 刺すような感覚があるか?
これらの質問に答えると、どのタイプのストレッチを実行する必要があるかがわかります。
また、怪我の程度によっては、腕のストレッチだけでなく首や背中のストレッチも必要になる場合があることに注意しましょう。
さらなる損傷を避けるためには、ストレッチ中に正しい姿勢を維持し、以前の怪我のためにすでにきつく感じている筋肉を伸ばそうとしないことが重要です。
過度のストレッチは、組織を悪化させ、さらなる問題を引き起こす可能性があります。
野球肩の痛みを取る5つのストレッチ
どの動作が痛みの原因になっているのかを特定したら、次はストレッチを始めましょう。
野球肩に対するストレッチ運動は、痛みの軽減と管理に役立ちます。
一般的に、肩の状態、可動域、痛みのレベルに応じて、適切なストレッチ運動を選択することをお勧めします。
肩の痛みを軽減するために使用できる5つのストレッチを以下に解説します。
ここで解説する5つのストレッチは、野球を含むスポーツに関連する痛みなどの症状を軽減するのに役立ちます。
ただし、ストレッチを実施しても症状が続く場合は、病院やクリニックで整形外科の医師に相談することをお勧めします。
肩の外旋ストレッチ
野球など投球動作においては、90度屈曲位と90度外転位の外旋が制限されやすいので、それぞれストレッチ方法を解説します。
90度屈曲位の外旋ストレッチ
- 横向きに寝る
- 下側の腕を肩の高さまで動かす
- 肘を90度に曲げる
- 反対側の手で下側の手首をつかみ、手の甲を床方向へ近づける
- そのまま15〜20秒ストレッチする
- 2〜3セット繰り返す
ポイントは、体が完全に横を向いておらず、後ろを向いていると上手くストレッチされないので注意しましょう。
90度外転位の外旋ストレッチ
- バットや棒を用意する
- バットを端をつかみ、肘の後ろ側を通って腕に沿わせる
- もう一方の手でバットの反対側の端をつかむ
- 3でつかんだ手でバットを上へ持ち上げる
- バットと一緒に肩を後ろへひねり、15〜20秒ストレッチする
- 2〜3セット繰り返す
ポイントは、腕は肩の高さをキープし下へ下がったり、肩がすくまないように注意しましょう。
肩の内旋ストレッチ
内にひねる内旋に関しては、90度外転位はセルフでストレッチするのは難しいので、ここでは90度屈曲位のストレッチ方法を解説します。
- 横向きに寝る
- 下側の腕を肩の高さまで動かす
- 肘を90度に曲げる
- 反対側の手で下側の手首をつかみ、手のひらを床方向へ近づける
- そのまま15〜20秒ストレッチする
- 2〜3セット繰り返す
こちらも外旋ストレッチと同様に、体が完全に横を向いておらず、後ろを向いていると上手くストレッチされないので注意しましょう。
肩の外転ストレッチ
外転は腕を横に開く動きのことで、脇の下にある筋肉が硬くなるとかなり高確率で外転は制限されます。
なので、外転方向へのストレッチも念入りにしておくべきです。
- 壁に対して横向きに立つ
- 腕を肩の高さまで動かし、肘から手首までを壁につける
- 身体を壁方向へ倒し、脇をストレッチする
- そのまま15〜20秒ストレッチする
- 2〜3セット繰り返す
身体を壁方向へ倒す際、股関節や膝は曲がっても良いので、脇がしっかり伸びることを意識して行いましょう。
肩の伸展ストレッチ
伸展は身体に対して腕を後ろへ動かすことで、肩の前側が硬くなると伸展が制限されます。
伸展も制限されやすい動きの1つなので、しっかりとストレッチすることをお勧めします。
- 体育座りになる
- 両手をおしりの後ろへ、できるだけ遠くに着く
- 両手は動かさず、肩を下へ下げるように動かす
- 痛みが出ない範囲で肩を下げ、15~20秒キープする
- 2~3セット繰り返す
ポイントとしては、指はおしりの方へ向けて行いましょう。
指をおしりの方へ向けないと、肩は外旋し、その状態で伸展させると脱臼しやすい方向へ動くので、肩にとっては負担の大きい動きになります。
体幹のストレッチ
肩の運動は肩だけで動くわけではなく、体幹の動きも大きく関わっています。
また、野球の投球動作は体幹もダイナミックに動くため、より体幹の柔軟性は必要になります。
- 横向きに寝る
- 上側の股・膝関節を90度に曲げる
- 下側の足は伸ばしままやや後方へ伸ばす
- 両手を伸ばし、手のひらをあわせる
- 体幹を後方へひねり、上側の手の甲が床へ近づくように動かす
- 痛みが出ない範囲でひねった位置で15~20秒キープする
- 2~3セット繰り返す
ポイントは、上側の足を曲げ、骨盤が後ろ側へ倒れないようにすることです。
骨盤が倒れるとストレッチしたい場所が上手く伸びませんし、腰に過剰にひねりの動きが加わるため、腰痛を引き起こす原因になります。
野球肩の痛みを取るストレッチ|5つのポイント
ストレッチは筋肉を伸ばすことですが、闇雲にストレッチすれば良いわけではありません。
ストレッチする秒数や頻度など、適切に行うことで効果を最大限発揮することができます。
以下にストレッチの適切なタイミング、頻度、秒数、強さを解説します。
ストレッチのタイミング
ストレッチの効果としては、筋肉の柔軟性改善による関節の可動域の改善です。
ストレッチをするタイミングとして、運動後のストレッチは筋肉痛の軽減に一定の効果があるとされています。
ただ、スポーツにおいて運動前のストレッチをする場合は注意が必要です。
45秒以上のストレッチでは筋力低下を引き起こすとされ、90秒以上のストレッチではパフォーマンスの低下を引き起こすとされています。
なので、運動前のストレッチは45秒未満にとどめる方が良いでしょう。
ストレッチの頻度
ストレッチの頻度としては、1回2〜3セット行うのが推奨されています。
また、1日2日で効果が出るわけではないため、継続して行う必要があります。
個人差や筋肉の硬さによって差はでますが、おおよそ2〜3ヵ月程度は続けることで効果が出ます。
ストレッチの効果的な秒数
上述したように、45秒以上のストレッチで筋力低下を引き起こし、90秒以上ではパフォーマンスの低下を引き起こします。
一方で筋肉の柔軟性の改善を狙う場合、2〜3分持続的にストレッチをする必要があります。
なので、運動前はパフォーマンスの低下を起こさないようにストレッチは45秒未満にとどめ、運動後やそれ以外でストレッチする際は2〜3分するのが効果的です。
ストレッチの強さ
ストレッチの強さとしては、痛みが出ない程度にとどめましょう。
痛みが出るくらい強くストレッチすると、無意識に力が入ってしまい、上手く筋肉が伸ばされないので、ストレッチの効果が出にくくなります。
強くストレッチすればするほど良いわけではないので、痛みがあるのに無理に伸ばさないようにしましょう。
野球肩の痛みを取るには筋膜リリースもおすすめ
ストレッチを実践していてもあまり効果を感じられない、あるいは効果を感じられてもその場だけの効果に終わってしまう場合は、筋膜リリースもおすすめです。
筋膜とは、筋肉やその他の体の器官を覆う膜です。
繰り返しの動作により緊張することが多いため、緊張が高まり、可動域が狭くなり、それが肩周りで起こると肩の痛みが増します。
筋膜リリースを使用すると、運動能力の回復や炎症を軽減し、将来の怪我を防ぐことにもつながります。
具体的な方法としては、肩の緊張している部分を見つけることから始まり、圧力を加えてゆっくりとリラックスさせます。
圧力は、その部分の痛みや感度の低下を感じ始めるまで、指先で一定の軽い圧力を加えながら、ゆっくりと手を回転させて行います。
また、ストレッチは筋膜リリースと併用することで効果を高めることもできます。
筋膜リリースが終了した後にストレッチをフォローアップエクササイズとして使用できます。
筋膜リリースで狭い範囲、ストレッチでより広い範囲を伸ばすことで、痛みの軽減やより大きな可動域の獲得につながります。
これらのフォローアップエクササイズを定期的に行うことは、肩の痛みに苦しむ野球選手に推奨され怪我の治りが確実に早くなります。
野球肩の痛みを今すぐ取るなら理学ボディ
野球肩の痛みを今すぐ何とかしたいという方は、理学ボディにご相談ください。
筋膜の施術に精通している理学ボディのセラピストなら、筋膜に存在するピンポイントの硬さでも見つけることができます。
理学ボディでは、筋膜に対して施術を行い、最短で痛みを和らげることにこだわっています。
もし、肩の痛みが良くならなくて困っているという方は、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。
以下のLINEをお友達登録していただき、簡単な質問にいくつかお答えいただくだけで、あなたの痛みがどういったものか、その痛みを改善するためのマッサージ動画をお送りします。
すぐにできますので、まずは自宅であなたの痛みがどれだけ改善するのか試してみてください。
まとめ
- 肩の痛みが投球動作のうちのどこで起こるのかを調べることが重要
- 肩の動きのうち、どの方向への動きが制限されているのか調べることが重要
- 肩以外の部位も肩の動きに大きく関わる
- 肩の外旋、内旋、外転、伸展、体幹のストレッチが野球肩に効果的
- 運動前にストレッチする場合、パフォーマンスの低下を引き起こすことがあるため注意が必要
- ストレッチの頻度は1回2〜3セットで2〜3ヵ月程度は継続する必要がある
- 筋肉の柔軟性を引き出すには、2〜3分は持続的に伸張する必要がある
- ストレッチは痛みが過度に出ない強さで行う
今回は野球肩の痛みを取るストレッチについて、痛みの出る動作やタイミングについて解説しました。
闇雲にストレッチするのではなく、肩の痛みでもどの動きで痛いのか、どの動きが制限されているのかを知った上でストレッチすることが大切です。
そして、ストレッチのタイミングや秒数、頻度も適切に行うことで、ストレッチの効果をより高めることができます。
野球肩の痛みで悩んでいる方は、ストレッチの方法についても一度見直してみると良いかもしれません。