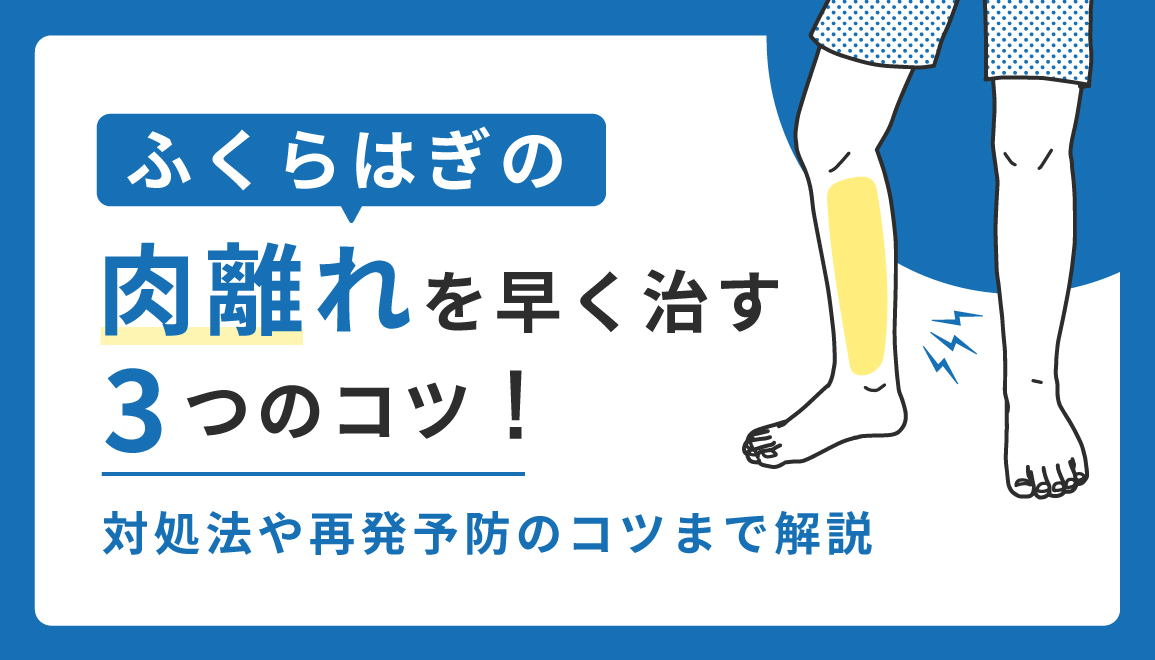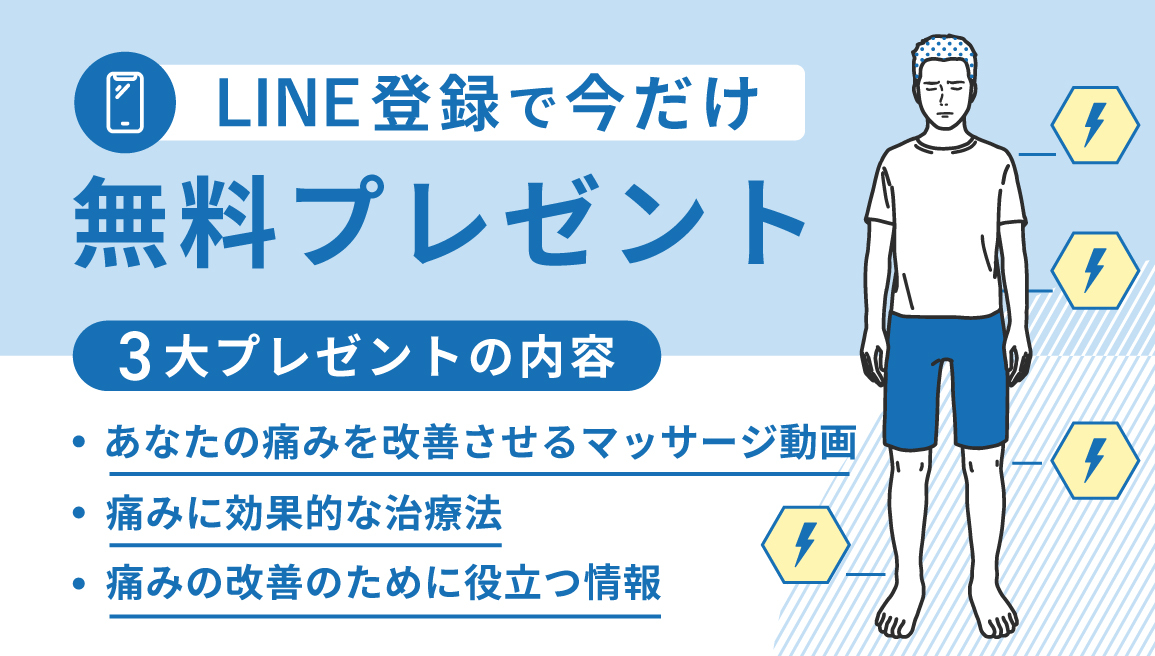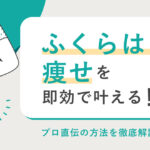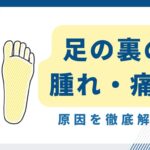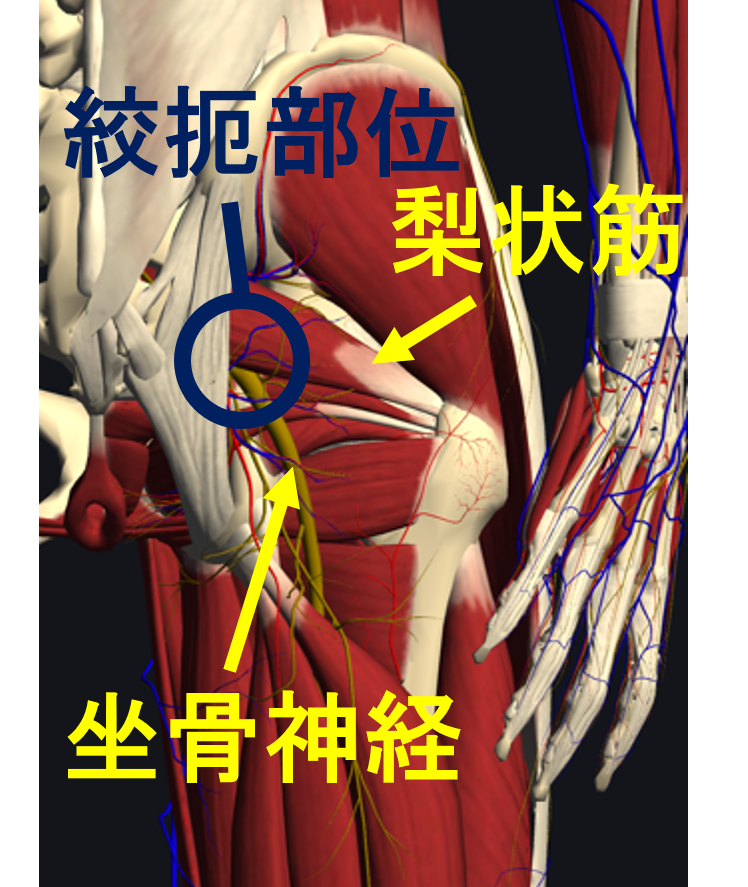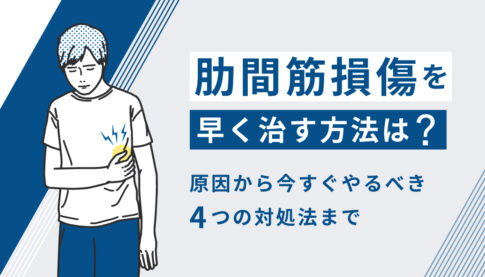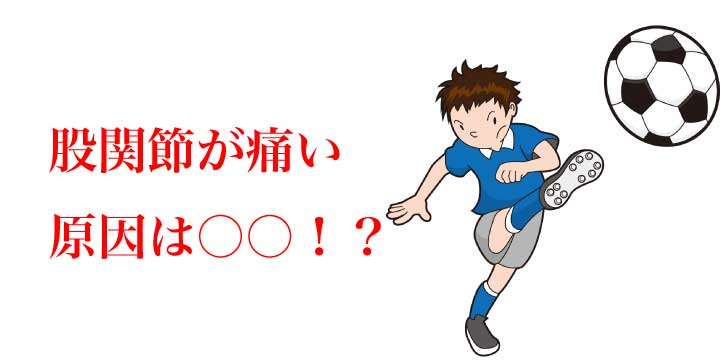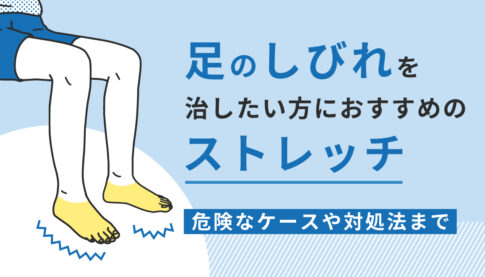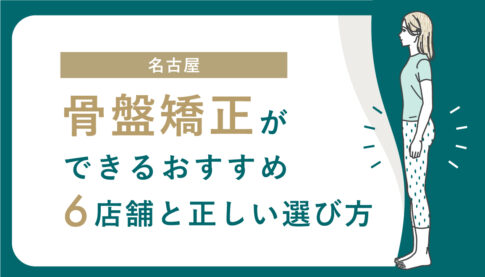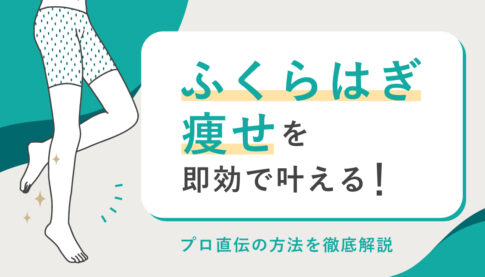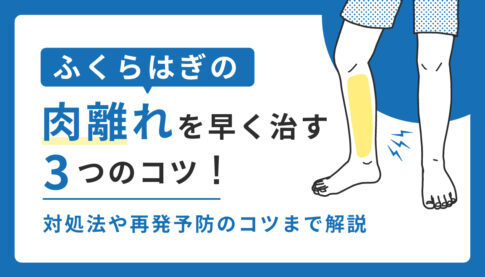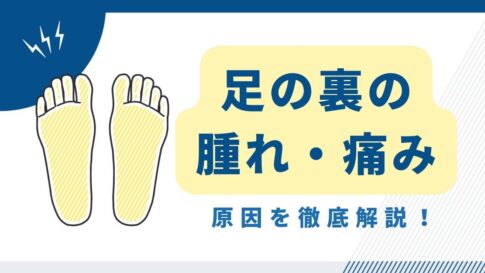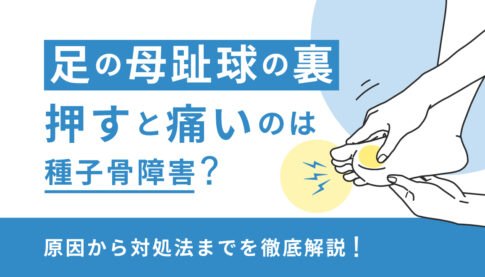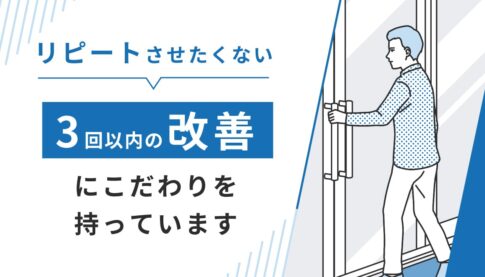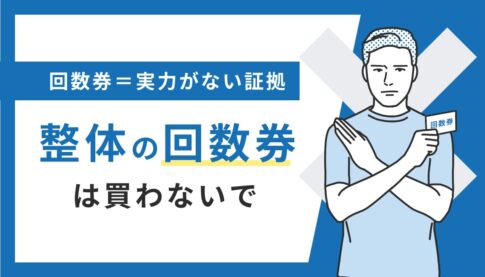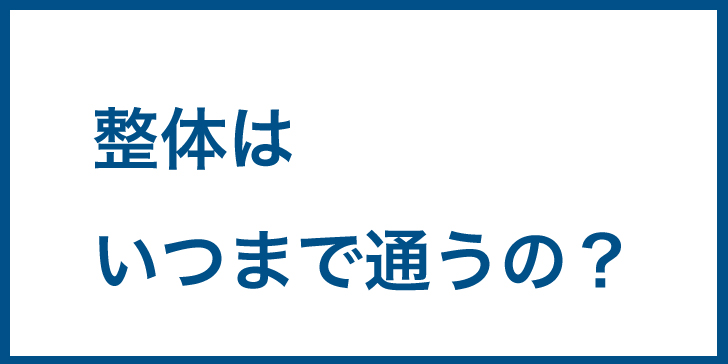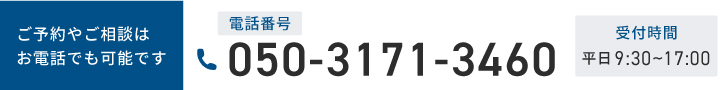スポーツや趣味のランニングなどで、急に「肉離れ」の激しい痛みに襲われた経験はありませんか?
実は「肉離れ」には早く治すコツがあるんです。
特にスポーツを頑張る中高生にとって、大会前や練習中に痛みでトレーニングができなくなってしまうのは大きな悩みです。
本記事では、体のプロである理学療法士が肉離れの正しい知識と、効果的なストレッチ法を徹底解説します。
肉離れとは
肉離れとは、筋繊維が部分的、または全体に断裂する現象を言います。
別名では筋挫傷とも言われます。筋挫傷の治し方について気になる方はわかりやすく説明した記事をご覧ください。
スポーツ時の激しい動き、例えばダッシュやジャンプなどにより頻繁に起こります。
バスケやサッカーなどのスポーツを頑張る中高生に起こりやすく、ふくらはぎや太ももに多く発症します。
肉離れの3つの原因
肉離れの原因は「筋肉の柔軟性不足」「ウォーミングアップ不足」「オーバーユース」の3つが多くみられます。
どれも筋肉に過度なストレスを与えてしまう原因ですが、それぞれのメカニズムについて、詳しく解説します。
筋肉の柔軟性不足
筋肉が柔軟性不足の状態では、突然の動きや負荷に適応できず、肉離れのリスクが高くなります。
特に激しいスポーツでは瞬発的な力が求められるため、筋肉の柔軟性は非常に重要です。
筋肉の柔軟性は、日頃の生活習慣や運動習慣だけでなく、ストレッチなどのケア不足や姿勢の悪さなども影響します。
ウォーミングアップ不足
ウォーミングアップも肉離れの大きな要因の一つです。
ウォーミングアップが不十分では、どんな競技においても筋肉への衝撃は避けられません。
この衝撃が肉離れを引き起こす可能性があるため、指導者や選手自身がそれぞれのリスクを認識し、必要なウォーミングアップをすることが重要です。
具体的にはランニングを行うことで全身の体温を十分に高めることや、ストレッチを取り入れることで関節周りの筋肉をほぐし血行を良くすることです。
これにより筋肉の柔軟性が高まり、急な負荷が加わった場合でも筋肉が対応しやすくなります。
こうした計画的なウォーミングアップは、怪我の予防だけでなくパフォーマンスの向上も期待できます。
オーバーユース
「オーバーユース」はスポーツを頑張る中高生にとっては、切り離せない問題かもしれません。
しかし、このオーバーユースが無視できない肉離れの大きな原因です。
高強度の運動や長時間続けることで筋肉は過労状態となります。
筋肉の回復が追いつけなくなると、筋肉自体の強度が低下し、肉離れを引き起こすリスクが高まるのです。
スポーツを続ける上で一番重要なのは「適度な休息」をはさむことです。
適切な休息を取り入れることで筋肉の回復を促し、肉離れの予防につなげることができます。
肉離れの症状
肉離れの典型的な症状は、筋肉の断裂直後に感じる激しい痛みや急激な違和感が挙げられます。
この痛みは、筋肉の繊維が断裂し、いわゆる内出血が引き起こすものであり、その箇所が膨らんで腫れることがケースも見受けられます。
また、痛みは動かすと強まり、場合によっては動いたり歩いたりすること自体が困難となるケースもあります。
軽度のケースでは違和感程度の症状でも、悪化したケースでは皮膚の色が内出血により紫色に変化することもあります。
肉離れの兆候を感じたら無理に動かすのを避け、すぐに整形外科を受診しましょう。
肉離れを早く治す【応急処置】
肉離れを早く治す応急処置として効果的なのは、RICE(Rest:安静、Ice:アイシング、Compression:圧迫、Elevation:心臓より高い位置へ)処置です。
まず、肉離れが起きた直後は、無理に力を加えず、早急に安静にすることが必要です。
次に、患部をアイシングすることで、血の流出や腫れを防ぎ、血流を冷却して痛みを和らげます。
その後、圧迫バンドやテーピングを使用して、患部を適度に固定しながら圧迫することで、血流や腫れをさらに抑えます。
更に、患部を心臓よりも高い位置に固定(Elevation)することで、腫れや内出血を抑制し、悪化する可能性を最小限に抑えることができます。
肉離れを早く治す3つのコツ
肉離れを早く治すための基本的な3つのコツは、
- 適切なストレッチ・マッサージをする
- 必要な栄養を摂る
- 専門家に見てもらう
の3つです。以下で詳細を解説します。
適切なストレッチ・マッサージをする
柔軟性を維持・向上させるために重要なのが、適切なストレッチとマッサージです。
ストレッチやマッサージは血流を促進し、結果として痛みの軽減や炎症の早期回復につながります。
しかし、注意すべき点もあります。
ストレッチやマッサージは、時期や方法が不適切であると、逆に筋肉への負担を増し、症状を悪化させるおそれがあります。
ふくらはぎの肉離れに効果的な2つのストレッチ方法を動画でご紹介しますで、ぜひ実践してみてください。
- 両手を壁につけ足を前後に広げる
- 前の膝は曲げ、後ろは伸ばし踵をつける
- 後ろ足のふくらはぎが伸びている状態でキープ
- 左右20〜30秒じっくりとストレッチ
- 椅子に浅く座り、片足を前に伸ばす
- 膝をまっすぐに伸ばした状態で徐々に体を前に倒す
- 膝裏が伸びている状態で20〜30秒キープ
- ※痛みのない範囲で行いましょう
※当院では、あなたの痛みにあった個別の対処法を以下のLINEから無料でお伝えしています。いつでもご相談ください。
必要な栄養を摂る
肉離れが発生した場合、損傷部位の回復を早めるために、食事で栄養を摂取することは最も大切です。
筋肉の構成成分であるタンパク質は筋繊維の修復に必須であり、常日頃からの確実な摂取が推奨されます。
さらに、ビタミンCも筋肉の修復に重要な役割を果たします。
食事での栄養管理が難しい場合でも、方法の一つとして、タンパク質が豊富なプロテイン含有のサプリメントなどの併用も効果的です。
また、筋肉の50%以上を占める水分補給が不足すると、筋肉の修復が遅くなる可能性があるため、水分摂取も忘れてはなりません。
以上のように、肉離れの予防と損傷部位の適切な回復には、タンパク質をはじめとする栄養素の摂取と、水分補給が重要です。
専門家に見てもらう
応急処置までは自分でもできますが、その後の治療では専門家の指導が早期回復のカギとなります。
なぜかというと、傷は深さや回復の度合いが異なるため、それらを個人で判断するのは困難だからです。
自己判断で治療を行うと再発のリスクが高まる可能性もあります。
肉離れの早期回復と再発防止を図るには、定期的に医師や理学療法士に診てもらうことを強くおすすめします。
肉離れを早く治すNG行動4つ
肉離れの治療を進める上で注意すべきNG行動は
- 無理なストレッチ
- 温湿布で温める
- 入浴
- 飲酒
の4つです。それぞれについて詳しく解説していきます。
無理なストレッチ
無理なストレッチは絶対NGです。断裂した筋肉組織がさらに傷つく可能性があります。
肉離れの疑いがある場合は、自己判断をするよりも整形外科で詳しい診断を受け、肉離れの度合いを正確に把握しましょう。
適切な治療を行わなければ、いつまでたっても完治せず、常に痛みとともに生活することになりかねません。
回復状況に合わせて、筋肉の痛みが和らいだら、ゆっくりとリハビリを開始するのがおすすめです。
温湿布で温める
肉離れを起こした際には一般的に冷却することが推奨されます。
温湿布などで温めてしまうと、患部の炎症や内出血を悪化させる可能性があります。
さらに炎症部分を温めることで、治癒までに時間がかかってしまうため、温湿布の使用は避けましょう。
入浴
入浴により肉離れの箇所を温めると、血行が促進され肉離れの炎症を悪化させてしまう可能性があります。
炎症が治るまでは、入浴は湯船に浸からず、シャワーのみの利用をおすすめします。
患部を温めないように注意しましょう。
飲酒
アルコールは血管を拡張させる働きがあるため、炎症の強い時期に飲酒してしまうと、血流が増え炎症や内出血を悪化させる可能性があります。
また、アルコールは脱水症状を引き起こす傾向にあるため、水分が不足し、血行が悪化する恐れもあります。
肉離れの早期回復・重症化を予防するためには、飲酒は控えましょう。
十分な水分補給と睡眠を心がけることで、筋繊維の修復を促進し、肉離れの早期回復を目指しましょう。
よくある質問
ここでは肉離れに関するよくある質問を取り上げていきます。
ぜひ、参考にしてみてください。
肉離れに湿布は有効ですか?
肉離れの直後は湿布は有効ではありません。
そもそも肉離れの発生直後は、患部の炎症をいち早く静めることが重要です。
そこで重要となるのがアイシングです。
アイシングは患部を冷却し炎症を抑える働きがありますが、湿布には冷却の効果はほとんどありません。
湿布はメントールが含まれるため冷感を感じますが、冷却の効果はほとんどないんです。
消炎鎮痛成分を含むため、炎症がある程度治まり医師の許可が出てから使用することをお勧めします。
肉離れを早く治すのにテーピングは必要ですか?
肉離れを患った際にはテーピングが有効な治療法の一つです。
テーピングによる適度な圧迫は、無駄な筋肉の動きを抑制し、二次的な損傷を防ぐだけでなく、患部の痛みやむくみをやわらげる効果も期待できます。
さらに筋肉への適切な負荷を保つことで筋力の低下を予防し、肉離れの早期回復に有効な手段となります。
ただし、テーピングには注意点があります。
不適切な方法でテーピングを行うと、逆に症状を悪化させてしまう可能性があるのです。
必ず専門家に正しい方法を教えてもらいながら、使用するようにしましょう。