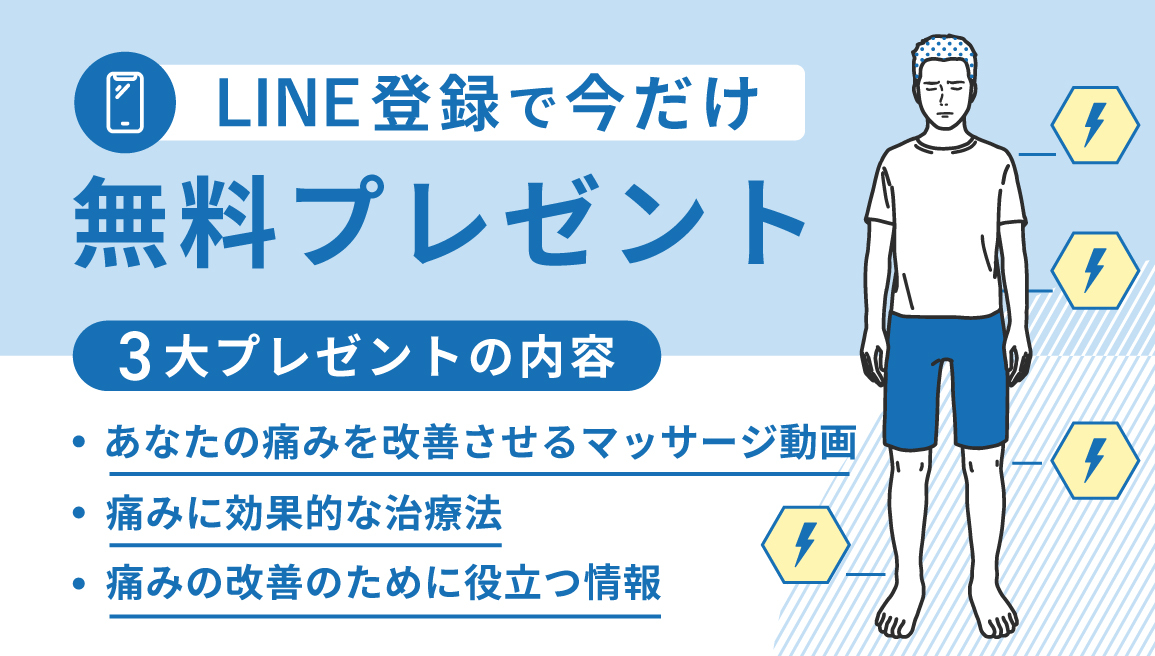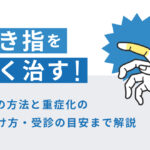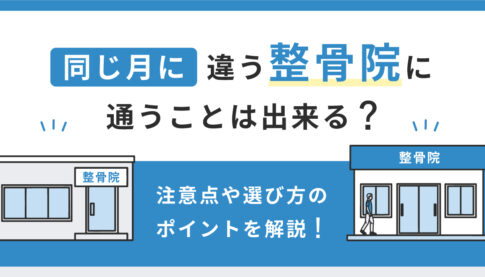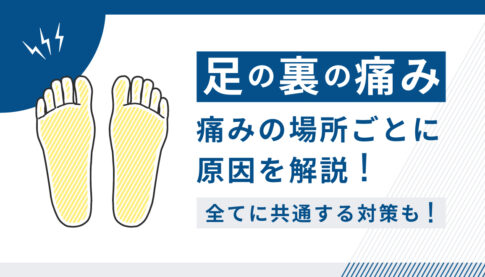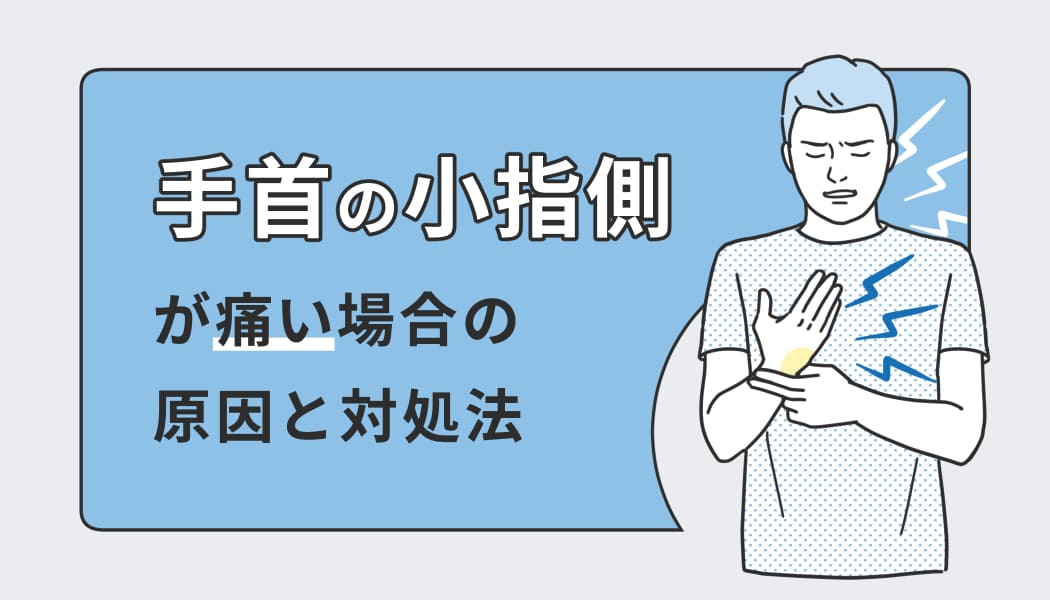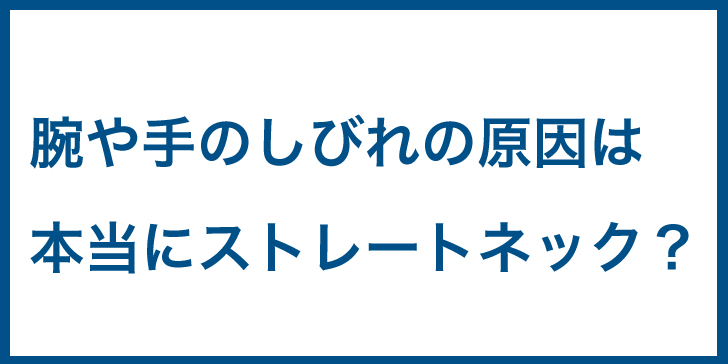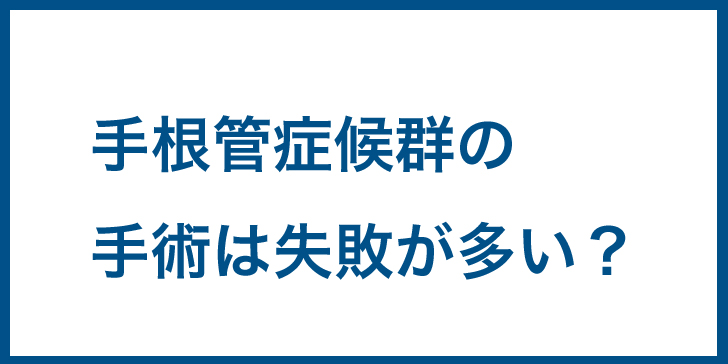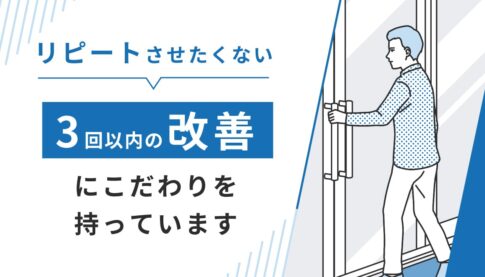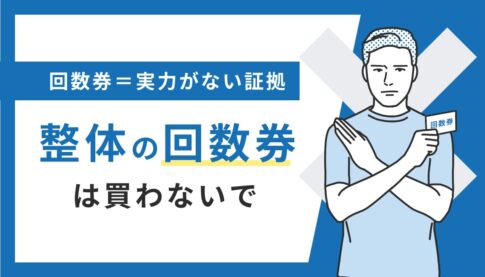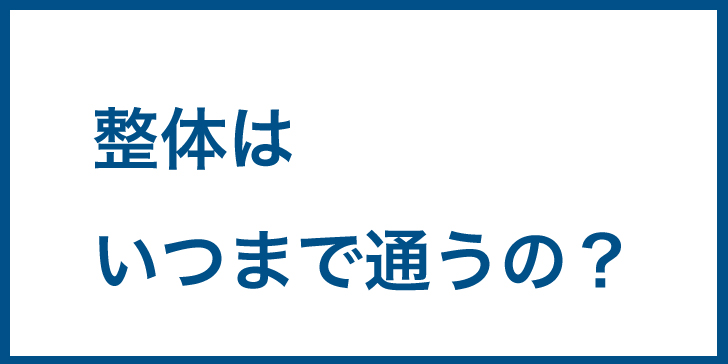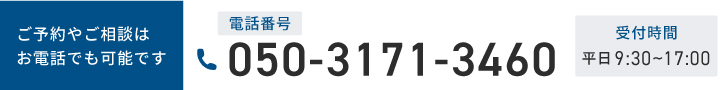自転車は近年人気のあるスポーツの1つです。
スポーツ漫画やオリンピックの影響もあり、最近始めた方も多いのではないでしょうか?
少しずつ走行距離が増えてきて楽しい半面
「自転車に乗った後、太ももが痛い」
なんてお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
せっかくの楽しみも、痛みがあると続かなくなってしまいます。
早く治したいし、痛みを予防したいですよね。
なぜ、サイクリングで太ももが痛むのでしょうか?
今回は、おもにスポーツ自転車初心者の方に向けて、自転車で太ももに痛みを感じる原因や対処法を解説します。
(※この記事ではクロスバイク・ロードバイクを使って舗装路を走ることを想定しています)
目次
自転車で太ももが痛い時に考えられる5つのこと
自転車に乗ったあとに太ももが痛むのは、おもに5つの原因が考えられます。
- 筋肉・筋膜が硬い
- 運動不足
- 負荷量が合っていない
- 漕ぎ方に問題がある
- サドルの高さが合っていない
これらは簡単にまとめると”使いすぎ”もしくは”間違った使い方”に当てはまります。
自転車を漕ぐ動作(ペダリング)は、日常生活とは違った動きです。
そのため、日常生活とは違った体の動かし方をします。
具体的には、日常生活より大きく体を使ったり、筋肉を使うタイミングが違ったりします。
また、自転車は基本的に同じ動きを繰り返すスポーツです。
つまり、間違った使い方が体にダメージを与えやすいスポーツとも言えます。
1分間のペダルの回転数(ケイデンス)が60だとすると、1時間で3,600回。
ケイデンスが80だとすると、1時間で4,800回ペダルを回します。
人によっては、1回のライドで10,000〜20,000回同じ動きをすることになります。
負担のかかる動きを20,000回繰り返したら、すぐに痛みが出てきてもおかしくはありません。
自転車のこれらの特徴が”使いすぎ”や”間違った使い方”を生み、痛みの原因になります。
では、5つの原因を1つずつ詳しく見てみましょう。
筋肉・筋膜が硬い
これはいわゆる”体が硬い”ことが原因です。
もともとの体が硬い方、特に太ももの前(大腿四頭筋)や太ももの後ろ側(ハムストリングス)が硬い場合に多く起こります。
以下の特徴がある方は、筋肉・筋膜が硬い可能性があります。
- 正座をすると太ももの前が張って痛い(大腿四頭筋が硬い)
- 前屈で手が床につかない(ハムストリングスが硬い)
硬い筋肉・筋膜が繰り返し引っ張られると、ダメージを受けて痛みに繋がることがあります。
普段体の硬さが気にならない方でも、自転車は体の動き方が違うため、このような症状が出る可能性があります。
運動不足
これはサイクリング初心者に起こりがちな原因です。
運動不足が原因の場合は、太ももに限らず、腰や首、手など複数の場所に痛みが出ていることが多いです。
また、痛みまでは行かずとも、全身の疲労感(倦怠感)が数日続く、ということもあるでしょう。
サイクリング初心者の中には、運動不足解消のため、久しぶりに運動を始めた方もいると思います。
新たな趣味を始めるのはとても良いことです。
ただし、いきなり運動をしすぎると、体がついていかずオーバーワークになってしまうことも。
体の疲れ具合や痛みと相談しながら、少しずつ走行時間や距離を伸ばしてみましょう。
負荷量が合っていない
自転車に限らず、つい頑張りすぎてしまうことがありますよね。
グループライドで普段より走行距離や時間が長くなったり、ヒルクライムにチャレンジしたり。
大会の直前になっていきなり練習量を増やしてみたり。
時に必要なことですが、急な負荷量の変化は体にダメージになることも覚えておいてください。
走行距離100kmを目指すなら、30km→50km→75kmと徐々に距離を増やして、体の様子を見ることが良いでしょう。
大会に向けての練習も、コースや天気、目標タイムに応じて数ヵ月かけて準備することが大切です。
漕ぎ方に問題がある
自分に合っていない漕ぎ方が体に負担をかけてしまう場合があります。
これはスポーツ用自転車に少し慣れてきた頃に起こることが多い原因です。
たとえば、踏み込みで膝が内側にぶれると、膝に捻れストレスがかかります。
膝は本来、捻れる動きには強くありません。
そのため、数千回同じストレスを受けると、膝の周りの半月板や靭帯・腱が損傷することがあります。
このような痛みはサイクリング中から発生し、自転車を降りた後も数日続くことがあります。
サドルの高さが合っていない
スポーツタイプの自転車(特にロードバイクやクロスバイク)は近所を走る自転車(いわゆるママチャリ)と形が違います。
簡単に言えば、スポーツタイプの自転車はスピードが出やすいように作られており、ママチャリは安定さや小回りを重視して作られています。
スポーツタイプの自転車は低速だと不安定なため、初心者はサドルを低く設定することが多いです。
自転車は安全走行が第一なので、安全の視点ではサドルを低く設定するのは大事なことです。
ただし、自分の自転車に慣れてきて「もっと強度を上げたい」のであれば、一度サドルの設定を見直してみましょう。
サドルを低く設定すると、ペダルを踏む時に膝を必要以上に大きく曲げなければなりません。
このままペダルを強く踏むことを繰り返すと、膝に負担をかけることになります。
これは、膝や太ももを痛める原因になってしまいます。
反対に、サドルを高くしすぎてもバランスが不安定になります。
これは漕ぎにくさや腰痛の原因になることがあります。
【要注意】太ももが痛い人に特徴的な漕ぎ方
ここでは、太ももの痛みの中でも特に多い、太ももの前に負担のかかる漕ぎ方を解説します。
太ももの前が痛む方の漕ぎ方には、以下のような特徴があります。
- 踏みすぎ
- ママチャリの感覚で漕いでいる
- 重いギアを選びがち
- ケイデンスが低い
- 短距離ダッシュは得意だが、一定ペースのキープは苦手
まとめると、重いギアをしっかり踏み込むタイプの方は、太ももの前に負担がかかりやすいです。
自転車で太ももに負担を掛けない漕ぎ方
では、太ももの前への負担を減らすには、どのようにしたら良いでしょうか。
太ももの前への負担を減らすには、おもに3つの改善策があります。
1つめは、ペダリングの方法を変えることです。
ママチャリのペダリングは、ペダルを上から下へ踏み込むイメージです。
スポーツタイプの自転車では、ペダルの動きに沿って円を描くように回してみましょう。
ペダルとシューズを固定できるビンディングやトゥクリップがあるとやりやすいです。
また走行中は一定ペースをキープして、体にかかる負荷の変化を最小限にしましょう。
何度もダッシュを繰り返したり、信号の度に急停止・急発進を繰り返したりすると、体に負荷がかかります。
2つめは、ギアを軽くすることです。
太ももの前を痛める方は、重いギアを選びがちです。
特に上り坂を重いギアで登るのは、階段を何百段も登っているのと同じような負荷がかかります。
これでは、太ももも疲れてしまいます。
ギアを軽くすることで、一漕ぎごとに太ももにかかる負荷を軽くすることができます。
3つめは、自転車のセッティングを変えることです。
サドルの高さの設定方法はさまざまですが、下記の方法をおすすめします。
- 足をペダルに乗せる
- ペダルを真下まで踏んで止める
- このときの膝の角度が25°くらいになるよう調整する
- ペダルを真上まで引き上げる
- お腹と太ももとの間のスペースや膝の曲がり具合に違和感がないか確認する
- 実際に漕いでみて全体的な漕ぎやすさを確認する
サドルの高さだけで解決が難しい場合は、ステムやクランクの長さを変える方法もあります。
特に、膝の曲がりすぎが気になる場合は、クランクを短くすると膝への負担減に繋がります。
自転車で太ももが痛い時の4つの対処法
ここまで、自転車で太ももが痛む原因を解説しました。
ここからは、自転車で太ももが痛くなった時のセルフケアの方法を解説します。
自転車で太ももが痛くなった時は、4つの対処法があります。
- 安静
- アイシング
- ストレッチ
- 筋トレ
では、1つずつ見ていきましょう。
安静
動くのが苦痛になるくらい痛みが強い時は、無理をせず安静にしましょう。
痛みが強いのに無理をして動くと、かえって逆効果になりかねません。
まずは安静にして様子を見ましょう。
併せて痛み止めの薬や湿布(消炎鎮痛剤)を使ってみても良いでしょう。
生活の中では、階段の使用を控えたり車を利用するなどをして、足への負担を減らして生活してみましょう。
筋肉痛の場合、1〜2日が痛みのピークで、その後は徐々に緩和されていきます。
症状が緩和してきたら、痛みの程度に合わせて徐々に活動範囲を広げましょう。
活動の目安は、動いてみて痛みが悪化しないこと、痛む場所が腫れたり熱を持ったりしないことです。
動いてみて再び痛みが悪化したり、腫れたりする場合は、急に動きすぎた可能性があります。
まずは痛みが治まるのを最優先にしましょう。
アイシング
アイシングとは、痛みのある部位を冷やすことです。
アイシングには、過剰な炎症を抑え、痛みのセンサーの感度を鈍らせるはたらきがあります。
特に、じっとしていても痛むときには、アイシングが有効です。
アイシングは、以下の手順で行いましょう。
- 痛みのある部位の周りに氷(アイスバッグ)を当てます。
- 氷を当てたら、弾性包帯を使いアイスバッグを固定します。
- 固定ができたら、太ももを心臓より高い位置に挙げて、安静にします。
※アイシングを行う前に、痛みのある部位に出血や傷がないことを確認してください。
出血や傷がある場合は、止血や傷の処置が優先です。
アイシングを実施する際は、アイスバッグの使用をおすすめします。

持ってない場合はビニール袋に氷を入れても良いです。
ただしビニール袋は薄いため、直接皮膚に当てると凍傷になる恐れがあるので注意しましょう。
氷を薄手のタオルで覆ってから患部に当てるようにしましょう。
冷却時間は15~20分程度が望ましいとされています。
始めは冷えた感じがしますが、15~20分ほどで徐々に感覚が消失していきます。
凍傷を防ぐためにも、感覚がなくなったらアイシングを終了するようにしましょう。
炎症がピークを迎える受傷後24~72時間は継続することが望ましいと言われています。
ストレッチ
痛みがピークを超えて緩和してきたら、安静より適度に動いたほうが症状が軽くなります。
自分で簡単にできる方法としては、ストレッチがおすすめです。
ここでは、2つのストレッチを紹介します。
仕事や家事の合間や、1日の終わりに体をリフレッシュさせるつもりでやってみてください。
大腿四頭筋のストレッチ
太ももの前側・大腿四頭筋のストレッチです。
太ももの前側の痛みが気になるときや、膝のお皿周りが痛むときにおすすめです。
では、次の順番でやってみましょう。
- うつ伏せになる(顔は楽な方を向ける)
- 片足の膝を曲げ、足首を手で持つ
- 踵とおしりを近づけるよう手で引っ張る
- そのまま20秒ほどキープする
- もう一方の足も行う
- 3セットほど繰り返す
このストレッチのときは、腰が捻れたり、骨盤が浮かないように気をつけましょう。
太ももの前が気持ちよく伸びていれば正しく出来ている証拠です。
ハムストリングスのストレッチ
自転車で裏もも(ハムストリングス)が痛むことは、他のスポーツに比べると少ないです。
ですが、裏ももを使おうと意識したり、ダンシング(サドルからおしりを浮かせたペダリング)の後で痛むことがあります。
大腿四頭筋と合わせて、ケアしてみましょう。
では、次の順番でやってみましょう。
- 椅子に浅く座り、ストレッチする側の足を前に出す
- 前に出した足は膝を伸ばし、かかとをつける
- 両手を前に出した足のももに置く
- 胸を張ったままお辞儀をする
- 痛気持ち良いと感じるところで止める
- そのまま30秒キープする
- 反対側も同じように行う
裏ももの筋肉が伸びていれば、正しくストレッチできている証拠です。
もし、ストレッチで痛みが強くなるようであればすぐに中断してください。
やり方や部位が間違っているかもしれません。
時間をおいて再度やってみたり、他の対処法を試してみましょう。
筋トレ
足りない筋力を鍛えることは、痛みの予防だけでなく、パフォーマンスアップにも繋がります。
そのため、痛みが気になる時だけでなく、日常で取り入れてみることをおすすめします。
太ももの前側が痛む方におすすめの筋トレは、おしり(大臀筋)、腸腰筋、体幹の3つです。
トレーニングの時は、鍛えている場所に力が入っているか感じたり、手で触ったりながら行いましょう。
おしり(大臀筋)の筋トレ
おしり(大殿筋)を鍛えると、太ももにかかる負担を分散することができます。
次の順番でやってみましょう。
- 仰向けに寝て、両膝を立てる
- 片足を上げ、両手を太ももの裏で組み足を支える
- もう一方の足で地面を支え、おしりを上げる
- おしりを上げ切ったら、ゆっくり下ろす
- 10回程度繰り返す(慣れてきたら回数を増やしてもOK)
- 左右を入れ替えて同じ動きを繰り返す
腸腰筋の筋トレ
腸腰筋は、太ももを持ち上げる役割のある筋肉です。
自転車では、引き足(ペダルを引き上げる動き)で使います。
ペダルを踏む動きと引き上げる動きを切れ目なく行うと、ペダルを効率良く回すことができます。
さまざまな筋肉に負担を分散することができ、より長い時間自転車を楽しむこともできます。
腸腰筋のトレーニングは、次の順番でやってみましょう。
- 仰向けに寝て、肩甲骨が浮くくらいまで頭を持ち上げる(両手は腰に置く)
- 片足を上げる
- もう一方の足を入れ替える
- 10回程度繰り返す(慣れてきたら回数を増やしてもOK)
体幹の筋トレ
体幹は体の”幹(みき)”という字の通り、体の軸になる部分のことです。
不安定な自転車の上で足をスムーズに動かすためには、体の軸である体幹の安定が大切です。
スポーツ自転車のように体を前傾して支える動きは、椅子に座ったり歩くのとは体の使い方が違います。
自転車に乗る時と似たような姿勢でトレーニングをすることで、自転車で使える筋肉を鍛えることができます。
地味なトレーニングですが、1ヵ月続けると足が動かしやすくなると思います。
体幹のトレーニングは、次の順番でやってみましょう。
- うつ伏せで寝て、肘を肩の真下につく
- 両肘・両膝で体を支えるようにして、お腹を持ち上げる
- そのまま15秒キープする(慣れてきたら秒数を増やしてもOK)
- 2〜3セット繰り返す
これを応用して、片膝や片肘を持ち上げてみたり、保持時間を伸ばしてみると難易度がアップします。
膝を持ち上げても、肩から膝が一直線になるようキープすることがポイントです。
腰が捻れたり反ったりしないよう注意しましょう。
ぜひ、さまざまなバリエーションでチャレンジしてみてください。
今すぐどうにかしたい痛みは理学ボディへ
自転車で太ももが痛むときは、このような方法で対処をしてみてください。
ですが、これらの方法でも痛みが治らないことがあります。
それは、痛みの原因が太ももではなく、別の場所にあるからかもしれません。
痛みが長引いたり、痛みを根本からをしっかり治したい方は、専門家による施術をおすすめします。
「専門店はどこに行ったらよいか分からない」
「いち早く不調を解消したい」
このようなお悩みは、是非私たち理学ボディにご相談ください。
理学ボディは全員が理学療法士という国家資格を取得しており、医学的知識をもとに施術します。
その中でも、私たちは筋膜に特化した施術(筋膜リリース)を行います。
私たちが行う施術は国際的にも認められ、効果が期待できる方法です。
これは、当院で実際に来院された足底腱膜炎の方の施術例です。
(※足底筋膜炎と足底腱膜炎は同じ意味で用いられています)
このように、足裏の痛みの原因が、ふくらはぎや太ももにあることもあるんです。
これは、自分で解決するには難しいです。
特に、過去に怪我をしたことがある方には、このような全身の筋膜調整が症状改善に有効な場合が多いです。
また、施術と合わせて全身の姿勢をチェックしたり、一人ひとりに合ったセルフケアの方法をお伝えすることもできます。
現在、理学ボディではLINEで痛み診断や改善動画のプレゼントを行っています。
ご自身の痛みが気になっている方は、気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、自転車で太ももに痛みを感じる原因や対処法などを解説しました。
太ももの痛みは、太ももの”使いすぎ”や”間違った使い方”が原因です。
まずは数日安静にして、回復に努めましょう。
そして、痛みの再発予防のためにストレッチや筋トレをしてみてください。
繰り返す痛みでお困りのときは、是非お近くの理学ボディにお問い合わせください。