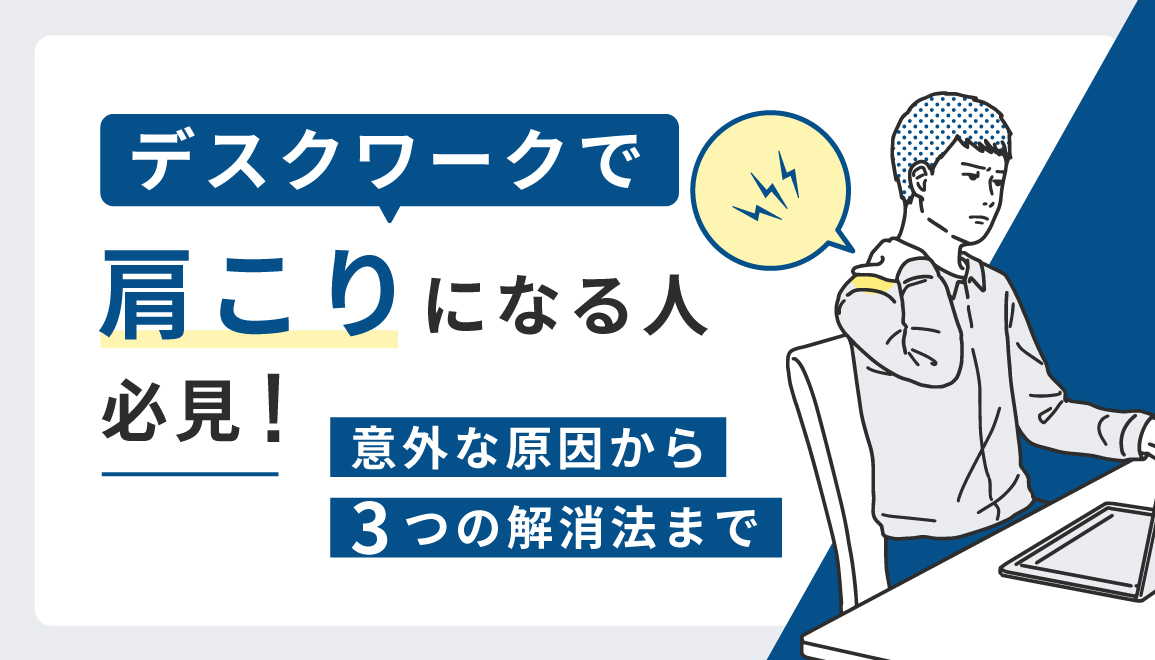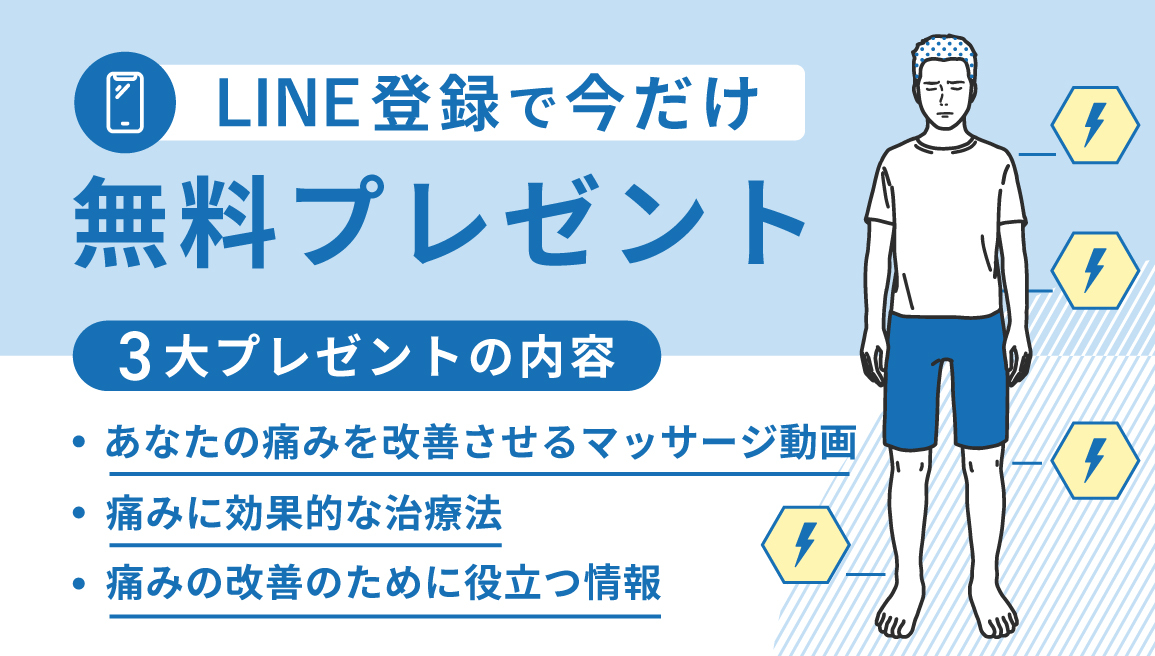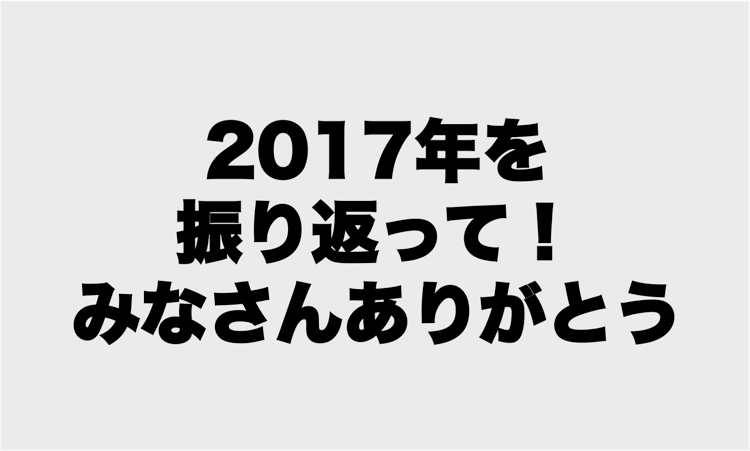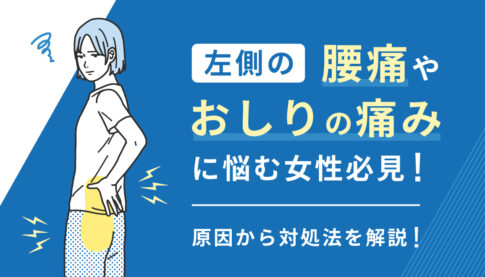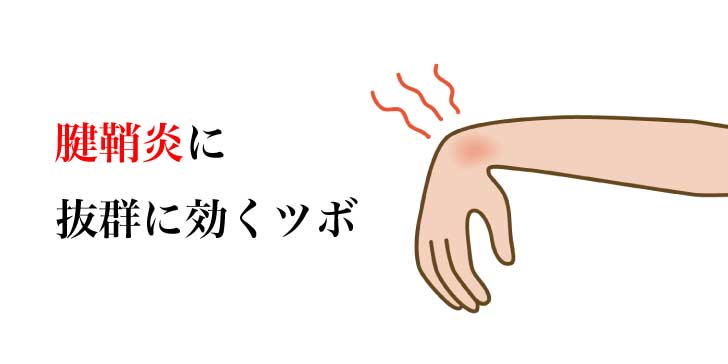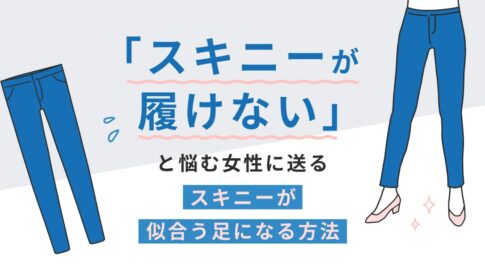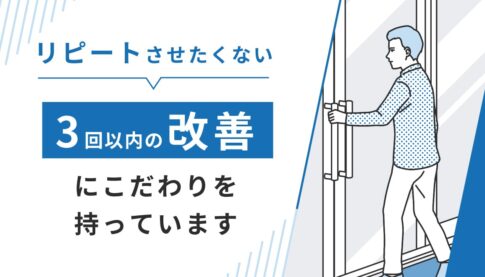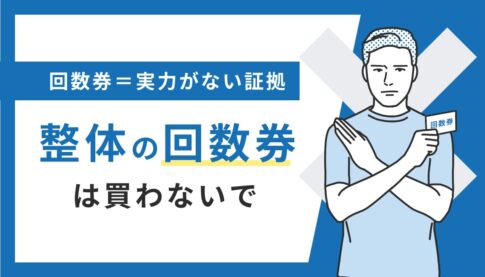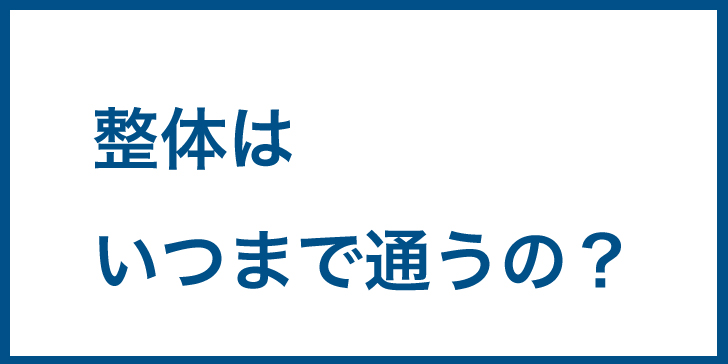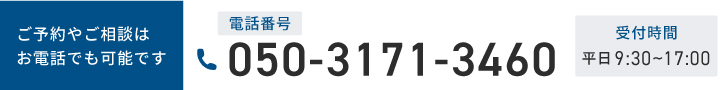「パソコン作業の後は肩や首がこってつらい」
「デスクワークになってから肩こりがとれない」
この記事をお読みのあなたは、このような体の不調に悩んでいませんか?
一度気になりだすと長びきがちな肩こり。
自己流で肩を揉んでみても、なかなか症状は改善しないもの。
一刻も早く、悩みから解放されたいですよね。
あなたの肩こりの原因、もしかするとパソコンに向かう姿勢が原因かもしれません。
そうであれば、原因の特定と正しい対策で、軽減させたり予防することができます。
この記事では、デスクワークでの肩こりに悩む方に向けて、その意外な原因をお伝えします。
正しい姿勢や座り方、机・椅子の最適な高さ、簡単ストレッチも併せて紹介しますので、仕事の合間に是非試してみてください。
※肩こりを今すぐに解消したい方は、正確な原因究明と施術ができる専門家への相談をすすめます。
目次
デスクワークで肩こりになる意外な5つの原因
まずは、どんな姿勢が肩こりを引き起こすのか、悪い姿勢が続くと身体にどんな影響があるのか、といったメカニズムを解説します。
デスクワークで肩こりになる原因は、次の5つです。
- 姿勢に問題がある
- 長時間の同じ姿勢による負担
- 筋肉の硬さ
- 筋力不足
- デスク周りの環境に問題がある
悪い姿勢が肩こりに繋がるのは、イメージしやすいでしょう。
でも、デスク周りの悪い環境が肩こりの原因になるのは、意外に思う方もいるかもしれません。
5つの原因を、1つずつ見ていきましょう。
姿勢に問題がある
デスクワークで作業に集中すると、座りっぱなしになりがちです。
長時間同じ姿勢をとると筋肉の血流が悪くなり、筋肉がさらに硬くなり…という負のスパイラルが起こります。
これが、よく言われる肩こりや首こり・腰痛の原因です。
さらに、姿勢が悪いと負のスパイラルをさらに悪化させてしまいます。
- 顎や顔を突き出している
- 背中が丸まっている
- 作業中、肩が上がっている
- キーボードが肘よりも高い位置にある
肩こりは、おもに僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋などの肩甲骨周りの筋肉が硬くなって起こります。
これらの筋肉は、重さが4~6kgある頭や、体重の約16%の重さを占める両腕を支えています。
顎や顔を突き出したり、背中が丸まっていたりすると、頭が肩よりも前に出ます。
そうなると、頭を支えるために、肩甲骨周りの筋肉はもっと収縮しなければなりません。
頭部が肩の真上にある時よりもかなりの負担がかかってしまい、肩こりになりやすいです。
これも肩こりを引き起こしやすくする一因です。
長時間の同じ姿勢による負担
体の硬さがなく、椅子に座る姿勢に気をつけていたとしても、肩こりになることがあります。
その原因は、同じ姿勢を取り続けることによる”筋肉の疲労”です。
いわゆる”良い姿勢”とは、骨盤が立っていて背筋を伸ばした姿勢です。
これをキープするためには、体幹(腹筋や背筋)に力を入れ続ける必要があります。
姿勢のキープには、腕相撲のような爆発力は必要ありませんが、同じ姿勢が1時間も続くとさすがに疲れてしまいます。
疲労している筋肉は血流不全を起こしており、これが直接肩こりの原因になります。
また、姿勢の崩れに繋がりやすく、間接的にも肩こりの原因になります。
適度に姿勢を変えることは、筋肉を休ませることにも効果があるのです。
筋肉の硬さ
もともと体が硬い方は、座りっぱなしによる肩こりになりやすいです。
特に大胸筋や腹筋が硬い方が、このタイプに該当します。
体の前側にあるこれらの筋肉が硬いと、猫背姿勢を引き起こし、頭が前に突き出しやすくなります。
すると、肩こりの原因になる僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋などの筋肉への負荷が高まります。
さらに、座り姿勢を支える骨盤周りの筋肉の硬さも、姿勢崩れからの肩こりに繋がってしまいます。
特に背中や腰、裏ももが硬い方は、座った姿勢が崩れやすく、肩への負担が高まります。
長時間座っているときに、人は無意識に座り直しをして、体重のかかる場所を変えています。
ですが、体が硬いと姿勢変化のバリエーションが少なくなり、負荷が一点集中になりがちです。
このため、肩周りへの負荷もかかりやすくなります。
筋力不足
デスクワーク中心の生活だと、体を動かさない方も少なくはないと思います。
運動習慣がなく、座りっぱなしの生活では、腰や肩周りを支える筋力が不足してしまうことが多いです。
徐々に疲労が蓄積し、フォームが崩れてしまいがちです。
これらの筋力不足により姿勢が崩れると、肩こりの引き金になってしまいます。
デスク周りの環境に問題がある
意外かもしれませんが、デスク周りの環境の問題で肩こりが起きてしまう方、少なくありません。
あなたの作業環境は、こんな状態にはなっていませんか?
- 柔らかい椅子に座っている
- どちらかの肘掛けにもたれている
- 背もたれにもたれすぎている
- ノートパソコンを使っていて、画面の位置が低い
これらの環境で作業をすると、自然と猫背などの偏った姿勢になりがちです。
長時間作業をする方は、快適な環境を整えることが、肩こりの解消に繋がります。
デスクワークで肩こりにならない正しい座り方
ここからはデスクワークで肩こりにならない正しい座り方をお伝えします。
ひと目見て分かる”正しい座り方”は横から見た時に頭が骨盤の真上に乗っている状態です。
逆に、頭が骨盤より前に出てしまうと、頭の重みを首や肩で受けてしまうためNGです。
椅子に座るときは、次のポイントを意識してみましょう。
- 骨盤を立てて、背筋を伸ばした座り方をする
- 椅子に深く座る
- 背もたれと背中の隙間をなくす
- 足の裏を床につける
- 足は組まない
- 膝の角度が90度になるようにする
- みぞおちの位置を引き上げる
- あごを軽く引く
座り姿勢の土台となる骨盤の位置を整えてから、頭や肩の位置を調整すると、姿勢が崩れにくいのでオススメです。
背もたれはもたれすぎず、触れる程度に使いましょう。
テーブルに置く肘の角度が90度を保つようにすると背筋が伸び、肩の負担が軽くなります。
良い姿勢は肩の負担が軽くなるだけでなく、見た目も美しい座り方なのでおすすめです。
デスクワークの肩こりを解消する3つの方法
デスクワークの肩こりを解消するためには、3つの方法があります。
- ストレッチ
- セルフ筋膜リリース法
- 肩こり解消エクササイズ
どれも自分で実践できるものなので、1つずつ一緒に試してみましょう。
ストレッチ
肩周りや体幹の柔軟性をしっかりと保つことは、肩こりの大切な対策法です。
作業の合間に、次のストレッチを試してみましょう。
胸のストレッチ
- 伸ばしたい方の腕を壁につける(※肘は曲げ、肩より高くなるように)
- 胸を開きゆっくりと深呼吸をしながら伸ばす
- ゆっくり20秒数えたら、逆の手も同様に行う
- 左右2セットずつ行う
腕を壁につけるときに、肘が下がるとストレッチの効果が下がるため気をつけましょう。
胸から肩にかけて気持ちよく伸びていれば正しく出来ている証拠です。
肩のストレッチ
- 伸ばしたい方の肘を曲げ頭の上にあげる
- 反対の手で肘を真後ろに押す(※腕の後ろの筋肉が伸びていれば◎)
- ゆっくり20秒数えたら、逆の手も同様に行う
- 左右2セットずつ行う
脇から肘にかけて気持ちよく伸びていれば正しく出来ている証拠です。
体幹のストレッチ
- 伸ばしたい方の肘を曲げ頭の上にあげる
- そのまま体を反対の手の方に傾け体側を伸ばす
- ゆっくり20秒キープする
- 2の状態からおへそを覗き込むようにし、背面を伸ばす
- ゆっくり20秒キープする
- 2の状態から天井を見上げるようにし、体側の少し前側を伸ばす
- ゆっくり20秒キープする
- 反対側も同様に行う
頭の位置を変えることで、体側のお腹側・背中側をまんべんなく伸ばします。
特に硬いと感じる部位は、重点的に伸ばしてみましょう。
セルフ筋膜リリース法
ご自身で行うセルフ筋膜リリースも、対策の1つです。
セルフ筋膜リリースは、次の手順で行いましょう。
- 筋膜の硬い部分(コリ)を見つける
- コリの場所を3〜10分間前後刺激する
- コリが複数箇所ある場合は、他の部分で①②を繰り返す
注意点したいポイントは刺激の強さです。
セルフ筋膜リリースにはゴリゴリとした強さは必要ありません。
なぜなら、強すぎる刺激は正常な筋膜まで壊してしまうからです。
また、コリの部分は痛みセンサーが過敏になっているため、軽い圧でもかなり痛みを伴います。
刺激の強さは、気持ち良いと感じる圧で行うようにしましょう。
肩こりには、肩の筋肉だけでなく、首や胸の筋肉も関係しています。
これらの筋膜リリースを行うと、より高い効果が期待できます。
※肩や背中の筋肉は自分では直接ほぐすことは難しいため、ストレッチをおすすめします。
※当店では効果的に痛みを改善出来るよう、あなたの痛みに効くおすすめの筋膜リリース動画をLINEから無料でお伝えしています。
筋膜の専門家直伝の方法を、ぜひお試しください。
首の筋膜リリース
- 顔を右へ向ける
- 首の左前に浮き出てくる筋肉をさわる
- その筋肉の前側、のど仏の高さの筋膜へ指を当てる
- 筋膜の動きにくい場所やコリを見つけたら、気持ち良いと感じる圧で刺激する
- 反対側も同様に行う
首を回旋させたり、横や前後に倒す動きが良くなります。
首の動きが良くなると、結果的に肩への負担も減るので、肩こりの解消につながります。
胸の筋膜リリース
- 胸の真ん中の骨をさわる
- のどからみぞおちまでの範囲で動きの悪い場所を探す
- 筋膜の動きにくい場所やコリを見つけたら、気持ち良いと感じる圧で刺激する
肩こりがある方は、頭が前に出て背中が丸くなっている場合が多く、胸の筋膜が縮こまって硬くなっている場合が多いです。
胸の筋膜がほぐれると、胸を開いて背中を伸ばしやすくなるため、肩こりの解消につながります。
肩こり解消エクササイズ
ストレッチや筋膜リリースと併せて、肩周りの筋肉を動かすエクササイズもおすすめです。
筋肉を動かすと血流が改善され、硬くなった筋肉をほぐすことに繋がります。
肩甲骨を動かすエクササイズ
猫背や反り腰で硬くなった胸の筋肉、肩甲骨周辺の筋肉をほぐします。
動作のポイントは、肘で大きな円を描くように動くことです。
- 座り姿勢になり指先を肩につける
- 両肘を胸の前で合わせ背中を開く
- 息を吸いながら、ゆっくりと両肘を頭の横まで引き上げる
- ゆっくりと息を吐きながら、胸を大きく開き肘を下ろす
- 10回目安に繰り返す
- 反対回しも同様に行う
両肘を背中で合わせるようなイメージで行いましょう。
四つん這いエクササイズ
背中の動きをよくするエクササイズです。
- 四つんばいになります
- おしりから背中・首の順に体を丸めて5秒キープします
- おしりから背中・首の順に体を反らせて、5秒キープします
- ②③を5回ほど繰り返します
③のとき、腰を反ると腰を痛める危険があるので気をつけましょう。
デスクワークを肩こりなく快適にする秘訣
これら3つの対策法の他に、デスクワークを快適にすごす秘訣があります。
それは、適度に休憩を挟むことと、デスク周りを整えることの2つです。
適度に休憩を挟む
座りっぱなしが肩こりの原因になることは先にお伝えしましたが、座りっぱなしを防ぐ一番簡単な対策法は休憩です。
ここで言う休憩は、横になることだけではありません。
椅子から立ち上がったり歩いたりしても、首や肩にかかるストレスを分散できます。
30分に一度が理想ですが、少なくとも1時間に1回は椅子から立ち上がれると良いでしょう。
会議中などで立ち上がるのが難しい場合は、上記の座り姿勢を整えたり、小まめに座り直してみてください。
デスク周りを整える
仕事時間の多くを過ごすデスク周りを整えることも、快適な生活に繋がります。
先ほどの座り姿勢のポイントと併せて、見直してみましょう。
- 背もたれ付きの椅子にする
- 座面の土台が硬い椅子を選ぶ
- ディスプレイの上端が、目線の高さにくるようにする
- 目からディスプレイまでの距離は40㎝以上確保する
- キーボードは、自然と手が届く距離に置く
- 肘の屈曲角度は90°以上とする
- 手首や前腕を載せられる机のスペースやひじ掛けを確保する
- キーボードやマウス(トラックパッド)はディスプレイと別に設置する
ノートパソコンは、キーボードとディスプレイが一体型となっているので、上記のポイントをすべて押さえるのはなかなか難しいでしょう。
特にディスプレイはどうしても低い位置にあるので、姿勢が前かがみになりやすいです。
ノートパソコンによっては画面も小さく、さらに前傾姿勢になってしまいます。
そこでノートパソコンの場合は、台に載せてディスプレイの高さを上げることをおすすめします。
工夫して少しでも正しい姿勢へ近づけるようにしましょう。
デスクワークの肩こりには筋膜リリースが有効?
今回紹介した対処法で、肩こりが改善する人もいればしない人もいると思います。
改善する場合は継続していただけたら良いですが、改善しない場合はセルフケアには限界があるかもしれません。
筋膜はいくつもの層になって全身を覆っており、時に互いに影響を及ぼします。
そのため、肩こりの原因がふくらはぎの筋膜にある、ということもあります。
自己判断で正確に原因を特定することは難しいです。
専門家であれば、全身の筋膜の状態をみながら、時には症状がある部位から離れた筋膜にアプローチすることができます。
「専門店はどこに行ったらよいか分からない」
「少しでも早く痛みを解消したい」
ご自身でのケアに限界を感じたら、私たちプロを頼ってください。
私たち理学ボディは全員が理学療法士という国家資格を取得しており、医学的知識をもとに施術します。
私たちは筋膜に特化した施術(筋膜リリース)を行います。
そして3回以内に卒業できることにこだわっています。
もちろん、全員が1〜3回の施術で改善するわけではありませんが、他の整体や病院に行くよりは少ない回数で改善できる自信があります。
また、施術と合わせて全身の姿勢をチェックしたり、一人ひとりに合ったセルフケアの方法をお伝えすることもできます。
ですので、なかなか肩こりが改善しない人は、一度ご相談いただければと思います。
理学ボディは北海道から九州まで店舗を展開しています。
症状にお困りの方は、一度お近くの店舗にご相談ください。
まとめ
この記事では、デスクワークでの肩こりに悩む方に向けて、3つの原因とおすすめの対策法を紹介しました。
デスクワークでの肩こりに悩む方は、まず3つの対策法を試してみてください。
それでも「痛みが解消しない」「自分がどの姿勢なのかわからない」
と痛みに悩まされるようなら、私たち理学ボディを頼ってください。
現在、理学ボディではLINEで痛み診断や改善動画のプレゼントを行っています。
ご自身の痛みが気になっている方は、気軽にお問い合わせください。