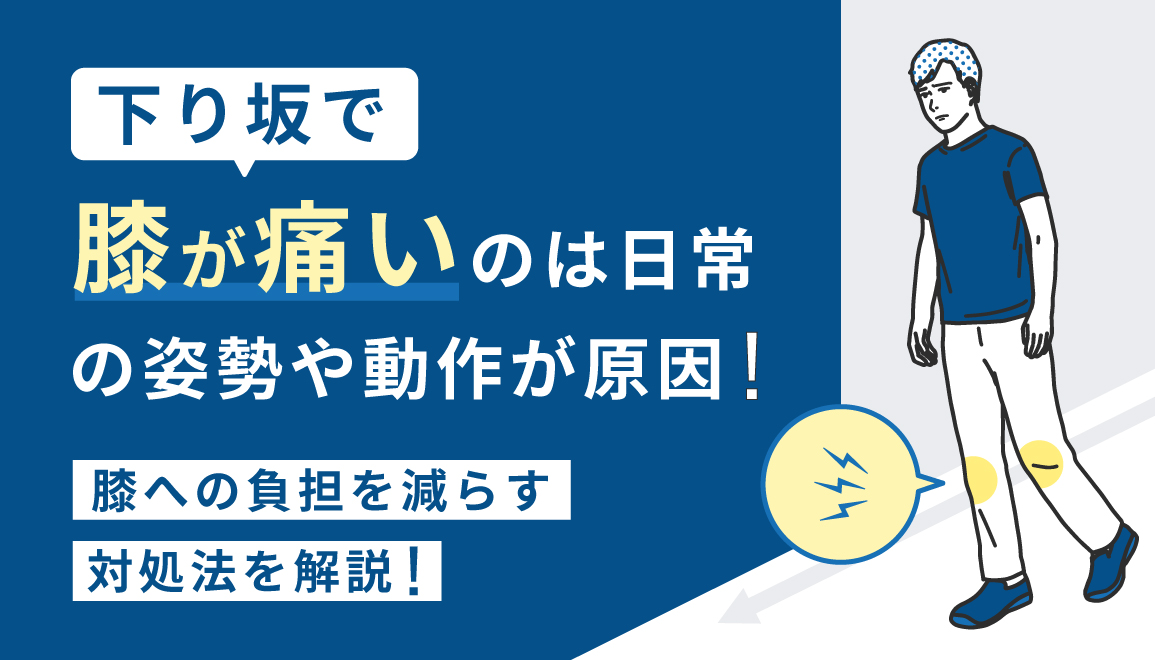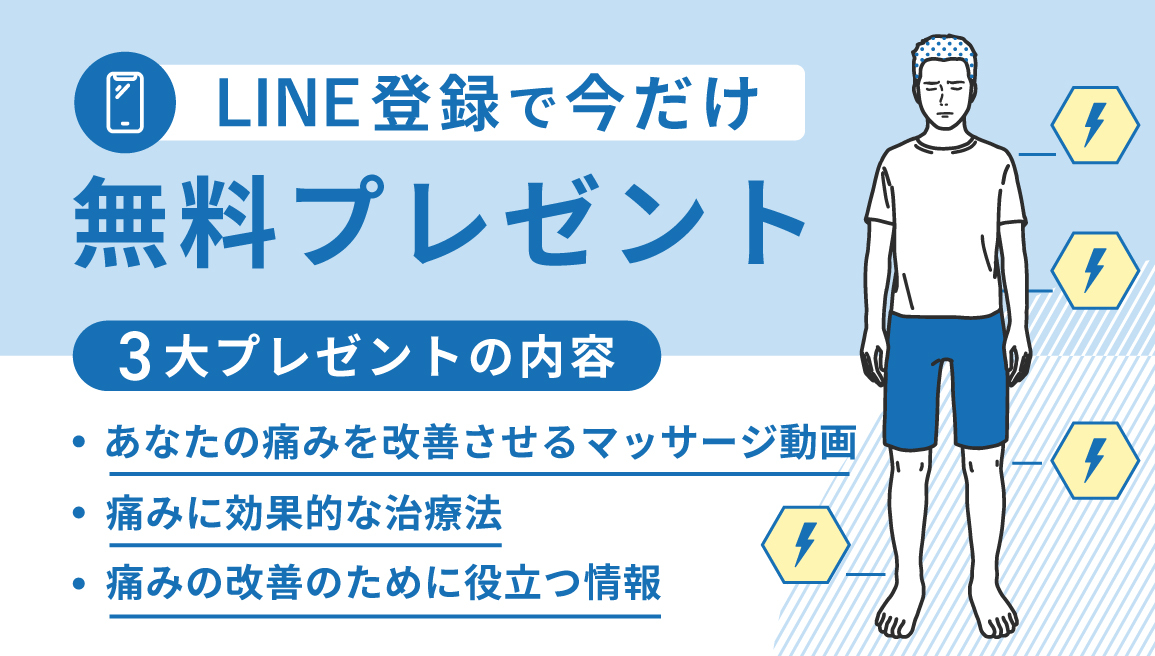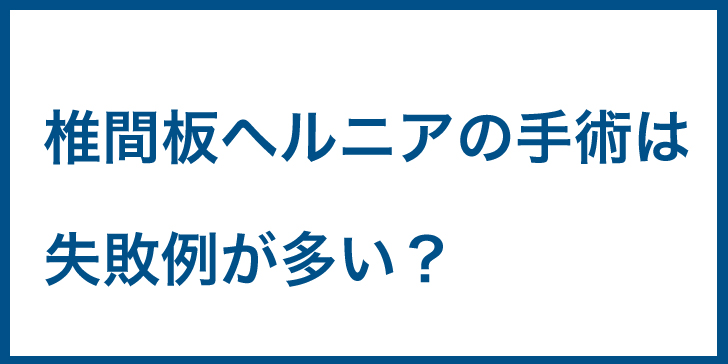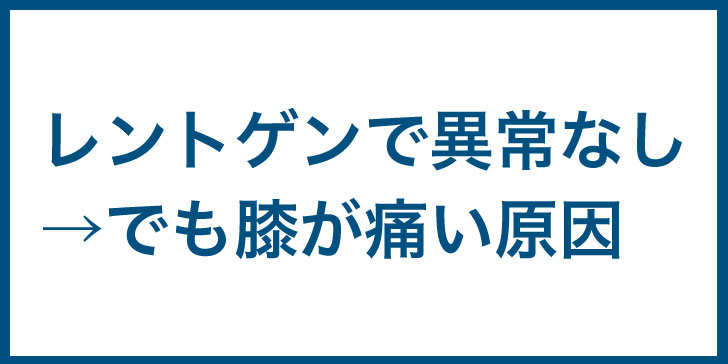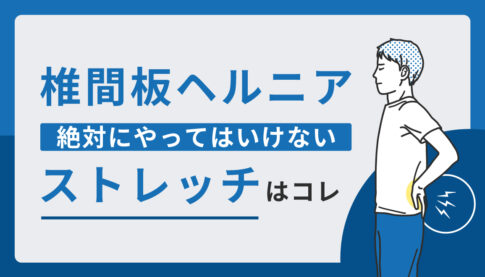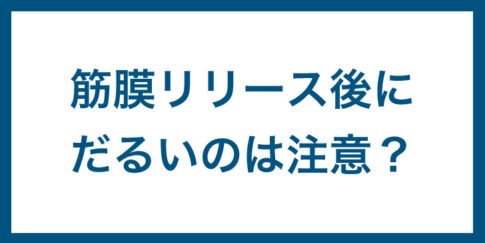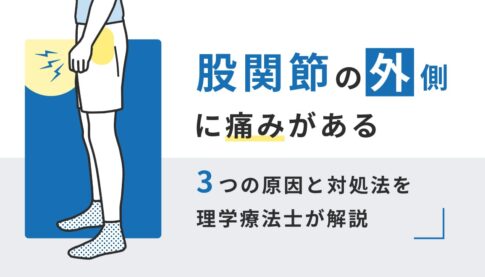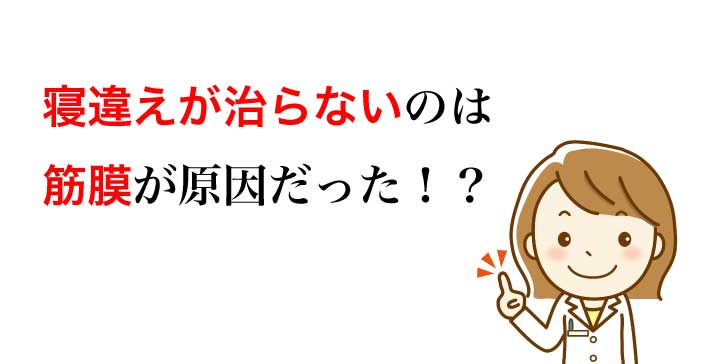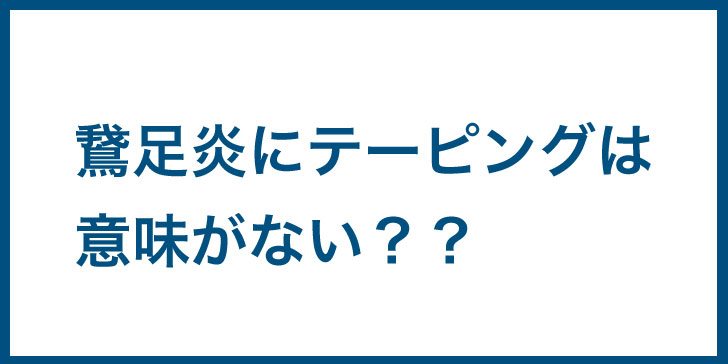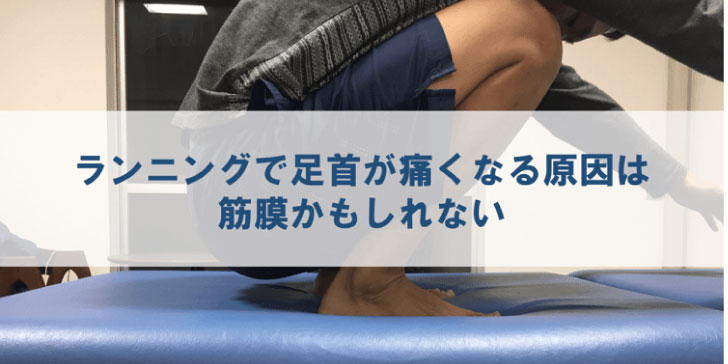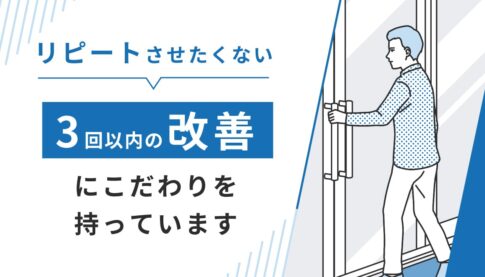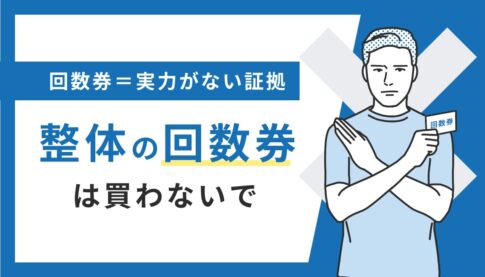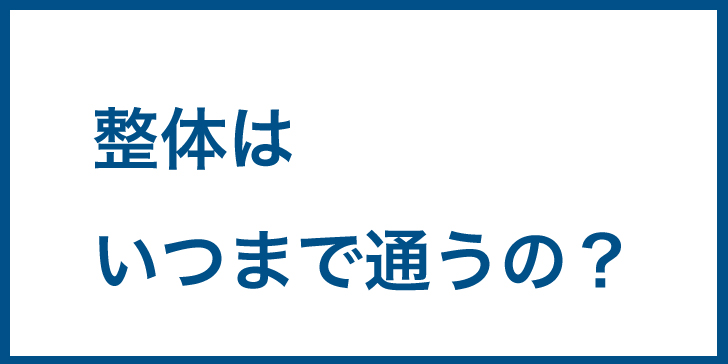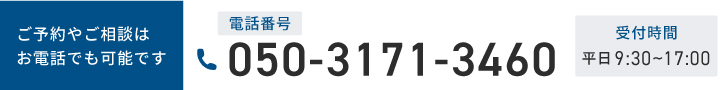下り坂を歩くたびに膝が痛くなる。
下り坂を歩くと、足がパンパンに張って膝も痛くなる。
このような悩みありませんか?
下り坂は平地や階段を降りるよりも膝への負担は大きくなりやすいです。
なので、下り坂で膝が痛くなってしまう方も多いですが、対策をすることで痛みを和らげることも可能です。
そこで、今回は下り坂で膝が痛くなる原因や膝が痛い時に考えられる事、対処法を解説していきます。
下り坂で膝が痛くなる原因
下り坂で膝が痛くなる原因としては、おもに以下の2つあります。
- 後ろ側の膝のコントロールが難しい
- 前側の膝への衝撃が大きい
それぞれ解説していきます。
後ろ側の膝のコントロールが難しい
下り坂だけではなく、階段を降りる際にも共通する部分があるのですが、前側の足を着地する際、後ろ側の膝を曲げながらゆっくりと足を着地します。
この時、後ろ側の膝は大きく曲がっており、それをコントロールするには前ももの大腿四頭筋という筋肉が強く働いています。
もし、大腿四頭筋が働かないと、急激に膝がガクッと曲がってしまい、転んでしまいます。
ただ、階段を降りる時と違い、下り坂では体の重心が後ろ寄りになっています。
重心が後ろ寄りになると、大腿四頭筋は体が垂直の状態よりも引き伸ばされるため、さらに大きな力が大腿四頭筋にかかります。
ただでさえ、膝が大きく曲がって、それ以上曲がっていかないようにコントロールしているのに、後ろ重心で大腿四頭筋が伸ばされるので、かなり大きな力が加わっています。
なので、下り坂では後ろ側の膝に大きな負担がかかっており、膝の痛みを引き起こしやすいと言えるでしょう。
前側の膝への衝撃が大きい
下り坂は前方に向かって地面が斜めになっているので、膝が伸びたまま着地しやすく、着地時の衝撃も平地や階段と比べて大きくなりやすいです。
平地では地面の高さが一定なので、膝への衝撃は少ないですが、下り坂の場合は斜め前に低くなっているので、その分膝へ加わる衝撃が大きくなりやすいです。
着地時の膝の衝撃を和らげるのが、上述した後ろ側の膝のコントロールです。
後ろ側の膝をゆっくりコントロールして曲げることができないと、前側の膝をゆっくり着地することもできません。
なので、前側の膝が痛かったとしても、原因は後ろ側の膝にあるという場合も考えられます。
また、膝が伸びきったまま着地しやすく、これも膝を痛める原因の1つになります。
膝関節は構造的に伸びると安定しますが、逆に関節が動くゆとりがない状態です。
そのため、本来歩く時には膝は軽く曲がっており、衝撃を和らげていますが、膝が伸びきったまま着地すると関節のゆとりがないので、衝撃を和らげることができずにダイレクトに膝に加わってしまいます。
たとえば、ジャンプして着地する時は膝を曲げて着地しますよね。
あれと同じように考えると、膝を伸ばしたまま着地するのがどれほど衝撃が大きいかイメージしやすいと思います。
まとめると、地面が前側へ斜めに低くなっている、膝を伸ばしたまま着地しやすいという2つの理由から、前側の膝にかかる負担が大きくなりやすいと言えるでしょう。
膝が痛い時に考えられる事
膝が痛い時に考えられる事としては、おもに以下の5つです。
- 変形性膝関節症
- 半月板損傷
- 靭帯損傷
- 腸脛靭帯炎
- 鵞足炎
それぞれ解説していきます。
変形性膝関節症
変形性膝関節症とは、関節軟骨が年齢とともに弾力性を失い、使い過ぎによりすり減り、関節が変形するというものです。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
症状としては、歩き始めや立ち上がった瞬間の痛み、正座、階段の昇り降りの痛み、しにくさが挙げられます。
原因としては、加齢による関節の衰え、肥満、遺伝、骨折や半月板損傷などの外傷によるものが考えられます。
ただ、変形性膝関節症はある日突然なるものではなく、上記の原因の影響で徐々に関節の変形が進行することで発症するものです。
痛みが出る前に、膝の曲げ伸ばしのしにくさや違和感などがあるはずなので、そういったものがなく、痛みだけが急に出た場合は変形性膝関節症である可能性は低いでしょう。
半月板損傷
半月板とは、C型をした軟骨様の板で内側・外側にそれぞれがあり、クッションとスタビライザーの役割をはたしています。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
簡単に言うと、膝にかかる衝撃を吸収し、膝を安定させてくれる役割を持つのが半月板です。
ですが、膝にかかる負担が大きい、偏った負担が繰り返し膝にかかると、半月板はその許容範囲を超えて損傷してしまう場合があります。
その結果、半月板が損傷すると半月板損傷と診断されます。
症状としては、半月板が損傷すると、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。
ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなるロッキングという状態になり、歩けなくなるほど痛くなります。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
バスケットボールやサッカーなどのスポーツ中の受傷が多いとされていますが、加齢による組織の老化で損傷する場合も少なくありません。
程度が軽い場合はリハビリテーションや痛み止めで良くなっていきますが、重症の場合は手術で半月板を縫い合わせたり、取り除くことが必要になることもあります。
靭帯損傷
膝関節には細かい部分まで見るともっとありますが、大きく分けると4つの靭帯が存在しています。
- 膝の前に付着する前十字靭帯
- 膝の後ろに付着する後十字靭帯
- 膝の内側の内側側副靱帯
- 膝の外側の外側側副靭帯
このように、前後、左右から膝を守ってくれているのが上記の4つの靭帯です。
一般に外反強制により内側側副靱帯が、内反強制により外側側副靭帯が損傷し、また脛骨上端の前内方に向かう外力で前十字靭帯が、後方への外力で後十字靭帯が損傷します。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
外反と言うのは膝が内側に飛び出すいわゆるX脚のような形、内反と言うのは膝が外側に飛び出すいわゆるO脚のような形のことを指します。
スポーツ中や交通事故など、その他大きな力が膝に加わって外反や内反へ強制されると、各靭帯が損傷される可能性があります。
症状としては、受傷直後は痛みや関節の動きの悪さ、腫れがメインで、しばらくするとそれらの症状は軽快していきますが、膝の不安定感が目立ち、下り坂やひねる動きの際に顕著に出現します。
そのままにしておくと、さらなる膝の痛みや半月板の損傷につながる可能性もあるため、リハビリで筋力をつけたり、サポーターで膝を安定させる、場合によっては手術が必要なこともあります。
腸脛靭帯炎
腸脛靭帯と言うのは、おしりの外側から膝の外側まで伸びる長い靭帯のことを指します。
そこが炎症を起こす腸脛靭帯炎は別名、ランナー膝とも言われ、マラソンをする方に多く見られ、足を酷使した際に膝の外側にズキズキとした痛みを生じるのが特徴です。
ただ、これはマラソンをする方だけに起こるわけではなく、膝の外側や内側、前側に偏って体重をかけて歩いたり走る、立つ、それこそ下り坂を歩くことで筋肉が過剰に緊張する部位が出てきます。
たとえば、外側に偏ると腸脛靭帯や外側広筋、内側に偏ると内側広筋や縫工筋、薄筋と呼ばれる筋肉が緊張します。
ある方向へ偏って力が加わった時、膝の曲がりすぎや、O脚のように外側へ曲がってしまわないように、筋肉がそれを止めるように収縮します。
そのように、筋肉が伸びたり縮んだり何度も繰り返され、日常的に行われることで、筋肉は常に緊張した状態となり、痛みを伴うようになる可能性があります。
腸脛靭帯のところで、何度もそうしたこすれるような力が加わることで、腸脛靭帯を起こす可能性があります。
鵞足炎
鵞足と言うのは、太ももの内側から膝の内側へかけて伸びている3つの筋肉の総称で、鵞鳥の足のように見えることからそう呼ばれています。
この鵞足がある部分は、膝の曲げ伸ばしで伸びたり縮んだりするため、下り坂をはじめ、階段の上り下りなど、膝の曲げ伸ばしを繰り返すことで、炎症が起こり膝の内側にズキズキとした痛みを生じます。
痛みが起こるメカニズムとしては、腸脛靭帯炎と同じようなものと考えられます。
下り坂で膝が痛い時の対処法
下り坂で膝が痛い時の対処法としては、おもに以下の3つが挙げられます。
- ストレッチ
- 筋トレ
- クッション性の高い靴に変える
それぞれ解説していきます。
ストレッチ
膝周りの筋肉が硬いと、膝関節の動きが悪くなり、着地時の衝撃を和らげることが難しくなるのと腸脛靭帯炎や鵞足炎を引き起こしやすくなります。
なので、膝周りの筋肉の柔軟性を引き出すことは重要です。
今回は特に硬くなりやすい、大腿四頭筋、ハムストリングス、大腿筋膜張筋の3つの筋肉のストレッチを解説します。
大腿四頭筋
- 足を伸ばして座る
- 片側の膝を曲げ、かかとをおしりの辺りにつける
- 両肘を床につける
- 余裕のある人は肘を離して背中を床につける
- そのままの姿勢で15〜20秒キープする
- 2〜3セット行う
ポイントは、腰を軽く丸めながらストレッチすることです。
腰を軽く丸めることで、大腿四頭筋がよりストレッチされるので、効果を高めることができます。
ハムストリングス
- 足を伸ばして座る
- 腰から背中を真っ直ぐ伸ばす
- 両手を前へ突き出しながら体を倒す
- 指先がつま先をさわる、可能ならつま先をこえるように体を倒していく
- 限界のところで10秒キープする
- 2〜3セット行う
ポイントは、できるだけ腰から背中は真っ直ぐ伸ばしたまま、体を前に倒すことです。
ハムストリングスは間接的に腰を丸くする働きがあるので、腰を伸ばすことでよりストレッチ効果を高めることができます。
大腿筋膜張筋
- 横向きになって寝る
- 下側の足の股関節と膝関節を90度に曲げる
- 上側の足の膝関節を90度に曲げ、膝を床へ近づける
- 膝が床につかない場合は、タオルやクッションで高さを補う
- そのまま15〜20秒キープする
- 2〜3セット行う
ポイントは、上側の足の股関節が曲がらないようにすることです。
大腿筋膜張筋は股関節を曲げる働きがあるので、股関節が曲がっていると上手くストレッチできません。
股関節はやや後ろ側へ引き気味の方がストレッチ効果を高めることができます。
筋トレ
膝関節は曲げ伸ばしは大きく動きますが、横やひねりの動きはほとんど動きません。
それだけに、横やひねりの動きに弱いため、筋肉の働きで膝を安定させることが重要です。
そこで重要となるのが、ハムストリングスと膝窩筋です。
多くの人は前ももの大腿四頭筋が普段の生活の中で使われやすく、反対に裏もものハムストリングスは使われにくい傾向にあります。
なので、ハムストリングスが弱くなりやすいため、筋トレすることで大腿四頭筋とのバランスが取れ、膝を安定させやすくなります。
膝窩筋はいわゆる膝のインナーマッスルで、関節のすぐ近くに位置し、膝を安定させてくれます。
ハムストリングス
- うつ伏せになる
- 膝と膝の間は握りこぶし2個分ほどあける
- かかとをおしりの外側へ向かってゆっくりと曲げる
- 曲げられるところまで曲げたら、元の位置までゆっくりと膝を伸ばす
- 20回程度繰り返す
ポイントは、なるべくゆっくりと曲げ伸ばしをすることです。
筋トレというと強い力で瞬間的に力を入れることをイメージするかもしれませんが、普段の生活ではそのような場面はほぼありません。
むしろ、筋肉がゆっくりと伸ばされながらも力を発揮するような力の入れ方が求められるので、なるべくゆっくりと行うようにしましょう。
膝窩筋
- 足を伸ばして座る
- 片側の膝を少し曲げる
- つま先を内側に向ける
- つま先を内側へ向けたまま、かかとを滑らせるように膝を90度以上曲げる
- 元の位置まで膝を伸ばす
- 20回程度繰り返す
ポイントは、つま先を内側へ向けたままの状態を保ちつつ、膝を曲げることです。
膝窩筋は膝を曲げる働きとすねの骨を内側へひねる働きを持ちます。
なので、つま先を内側へ向けることですねも内側にひねり、その状態で膝を曲げることで膝窩筋が働きやすくなります。
クッション性の高い靴に変える
膝への衝撃を和らげるためには、靴底が薄い靴や硬い靴ではなく、クッション性の高いものに変えることも1つの手段です。
ストレッチや筋トレは手間もかかるし、時間もかかりますが、靴を変えるだけであれば買ってしまえばすぐに実践できます。
靴底が厚めで、柔らかいタイプの靴を選びましょう。
理学ボディのおすすめ
今回紹介した対策を実践しても中々膝の痛みがなくならないという方は、理学ボディで施術を受けることがおすすめです。
理学ボディでは、最短で痛みを改善させることにこだわっており、筋膜という組織に対して施術を行います。
筋膜は筋肉を覆っている膜状の組織で、筋膜が硬くなると筋肉の柔軟性が低下、筋力が発揮しにくいなどが起こります。
筋膜の硬さのある場所はピンポイントで存在しているため、ストレッチやマッサージでは中々ほぐすことができません。
もし、筋膜の硬さが腰痛に影響しているのなら、ストレッチやマッサージをしていても中々改善することは難しいでしょう。
ですが、筋膜の施術に精通している理学ボディのセラピストなら、ピンポイントの硬さでも見つけることができます。
もし、膝の痛みがなくならなくて困っているという方は、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。
以下のLINEをお友達登録していただき、簡単な質問にいくつかお答えいただくだけで、あなたの痛みがどういったものか、その痛みを改善するためのマッサージ動画をお送りします。
すぐにできますので、まずは自宅であなたの痛みがどれだけ改善するのか試してみてください。