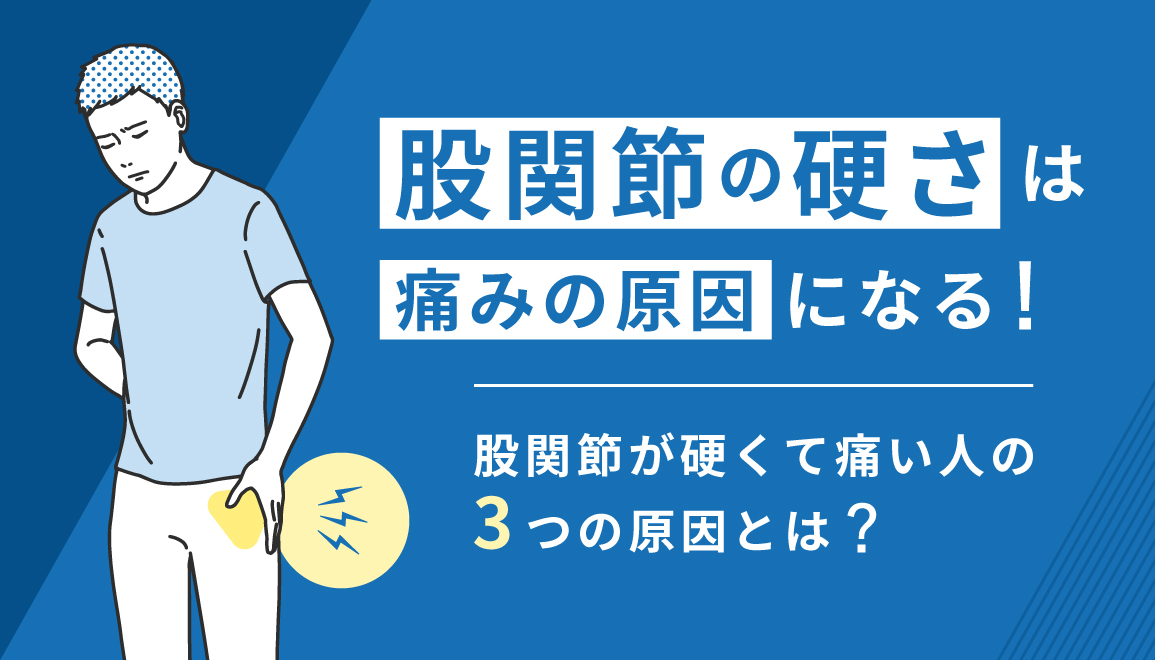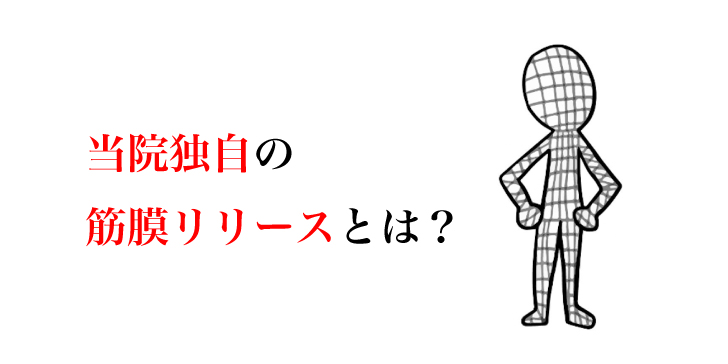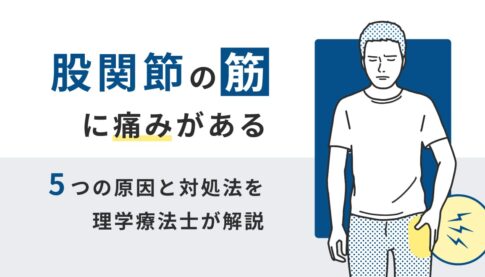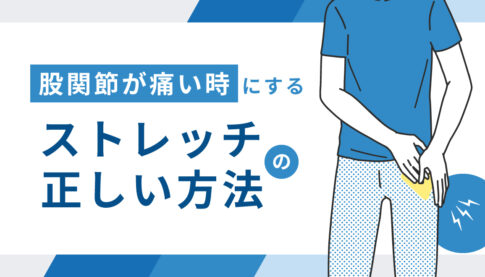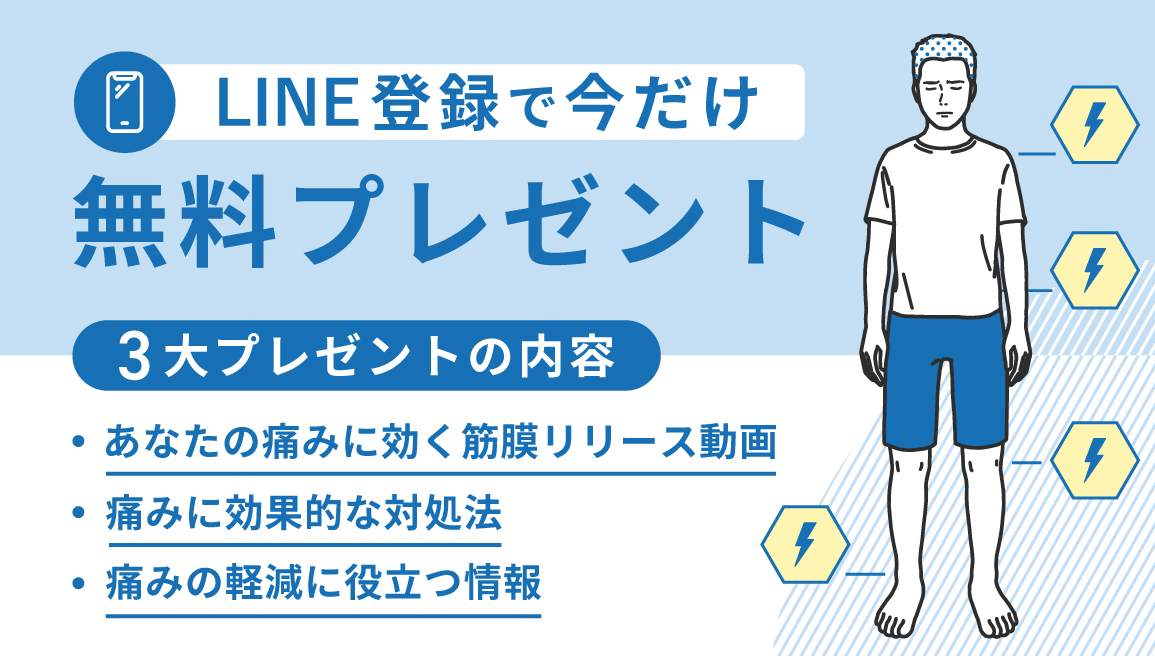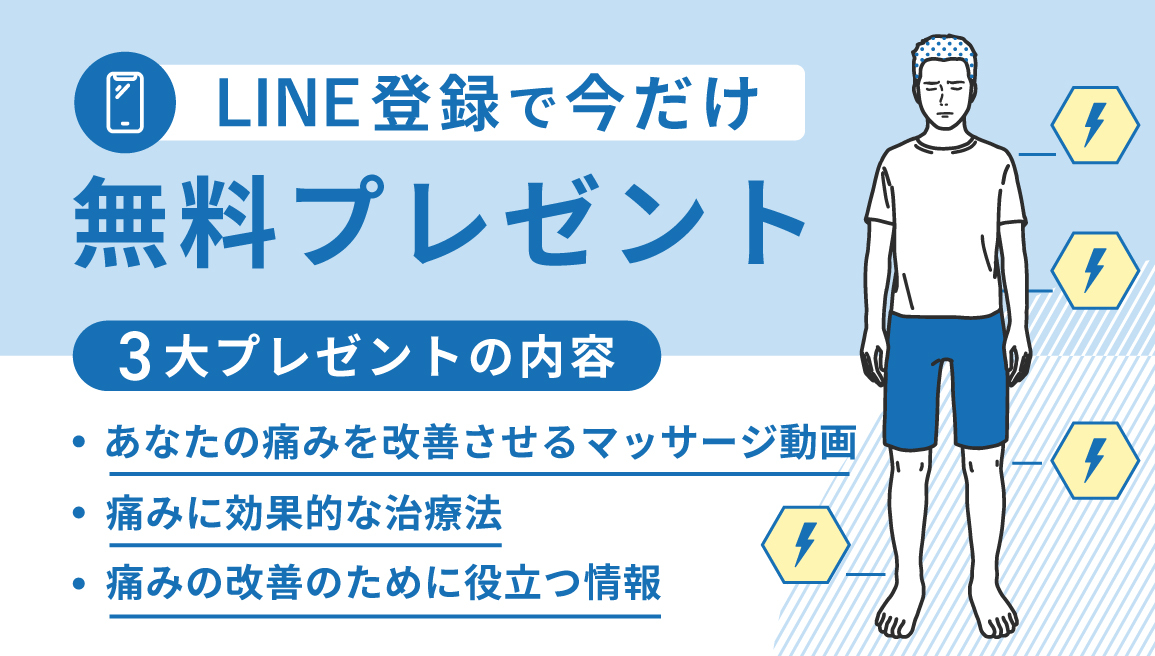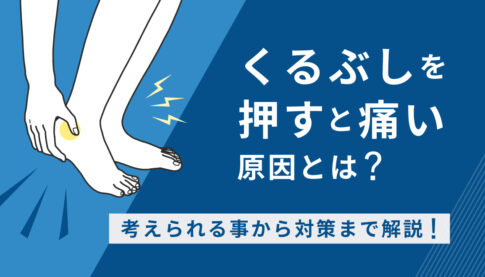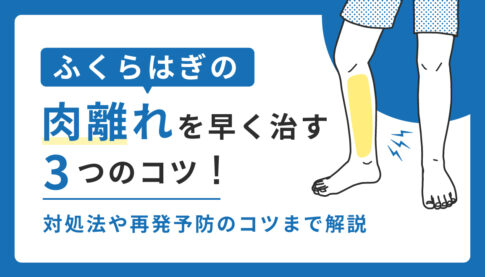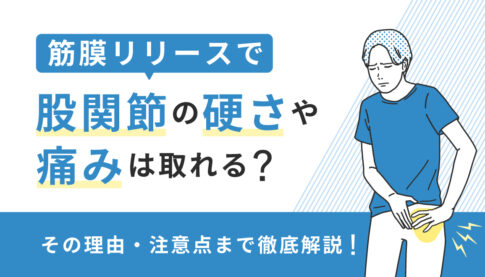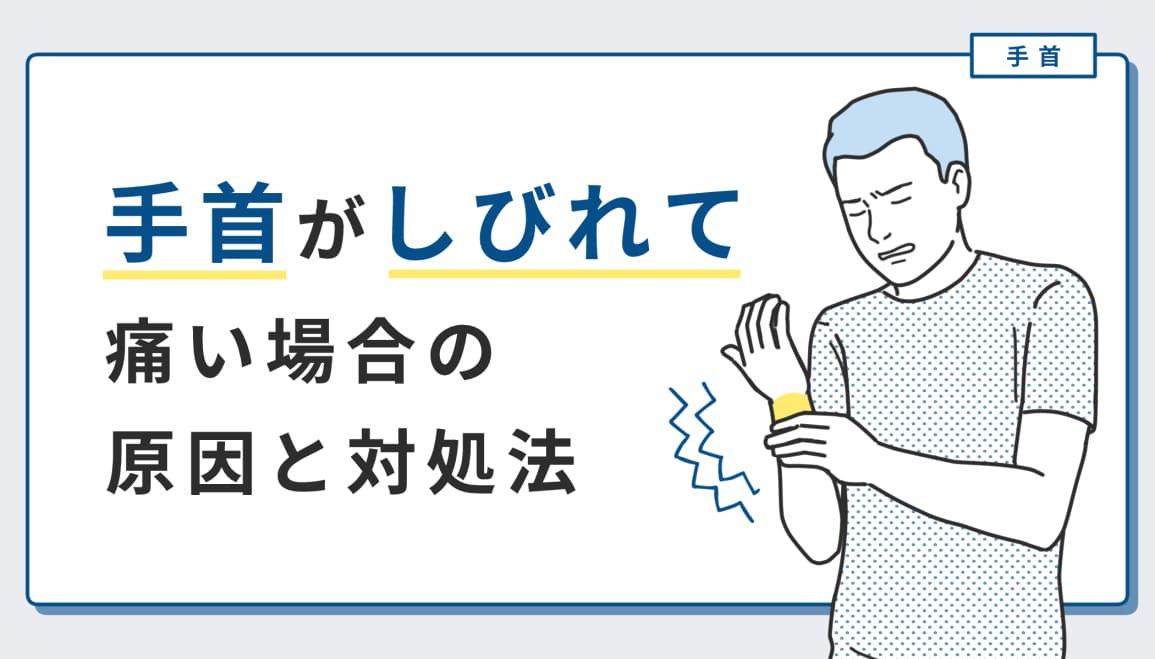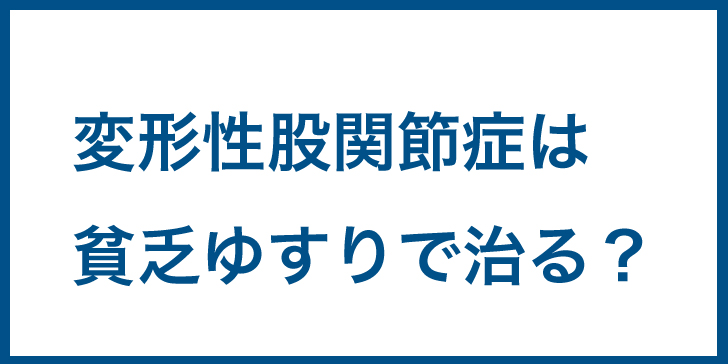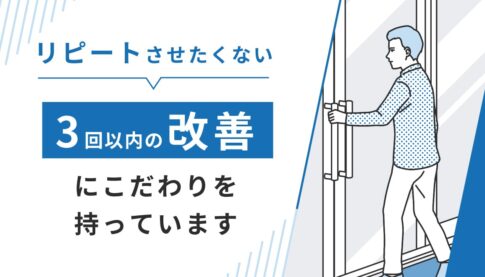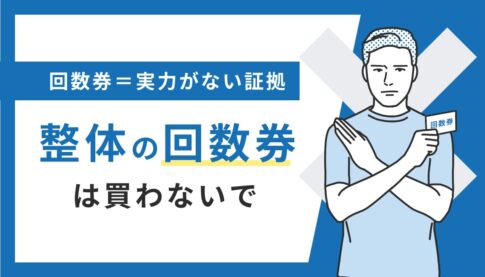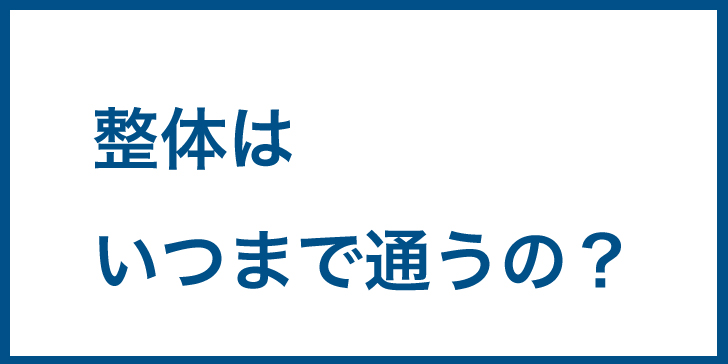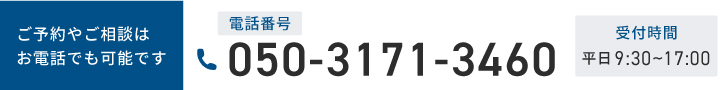歩き始めや立ち上がった時に股関節が痛い。
股関節を外に開いたり閉じたりすると痛くなる。
股関節が硬く、足を組んだりあぐらをかけない。
このように、股関節の痛みや硬さに悩んでいませんか?
実は股関節の硬さと痛みは関係しあっています。
つまり、股関節の痛みは股関節の硬さが原因である可能性があるのです。
ただ、股関節の硬さの背景には様々な要因があるので、闇雲にストレッチをしたら良いというわけでもありません。
そこで、今回は股関節が痛い時に考えられる事や原因、股関節が硬いことによるデメリット、柔らかいことによるメリット、痛みに対する対策を解説していきます。
※当院では、国際的に認知されている筋膜リリースという技法を用いてあなたの痛みを即時的に解消する施術を行っております。
当院だからこそ出来る筋膜リリースの施術やその驚きの効果についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事を覗いてみてください。
さらに、痛みを今すぐどうにかしたい方に向けて、あなたの痛みに効く具体的な筋膜リリースの方法をLINEから無料でお伝えしています。
ぜひご活用ください。
目次
股関節が硬い・痛みがある時に考えられる事
股関節の痛みがある時に転んだり、捻ったりと明確なきっかけがある場合は、骨折や靭帯損傷などの外傷が可能性として考えられます。
しかし、特にきっかけがないのにも関わらず痛いという場合は以下の3つが考えられます。
- 筋肉の痛み
- 臼蓋形成不全
- 変形性股関節症
それぞれ解説していきます。
筋肉の痛み
骨折などの外傷でない場合は、多くの場合で筋肉が原因となって痛みが出ています。
筋肉が痛みを起こすきっかけとなる原因としては、以下の2つが挙げられます。
- 筋肉の使い過ぎ、過剰な筋肉の緊張
- 血流が悪い
普段し慣れない運動をした、長時間同じ姿勢でいた、同じ動きを反復した、反動をつけて強くストレッチしたなどで筋肉が過剰に緊張してしまう可能性があります。
筋肉を過剰に使う、あるいは過剰に緊張するような負担がかかると、筋肉は緊張して硬くなります。
筋肉には、痛みを感じ取るセンサーがあり、筋肉の緊張でセンサーが反応すると、それを痛みとして脳へ伝えることで痛みが起こります。
また、手足に血管があるように、筋肉にも血管が通っています。
筋肉が緊張すると、血管は圧迫されてしまい、血流が悪くなってしまいます。
血流が悪くなると、痛みを発生させる発痛物質が体で作られるので、血流の悪さも痛みを起こす原因の1つになるのです。
※筋肉が原因で痛みが出ているケースについての詳しい対処法は以下の記事にもわかりやすくまとめています。
臼蓋形成不全
股関節は大腿骨頭という球状の骨と臼蓋という受け皿で構成されています。
受け皿である臼蓋が何らかの原因で、十分に発育しないことを臼蓋形成不全と言います。
小児期の臼蓋形成不全は基本的には乳児の時に超音波やX線(レントゲン)で診断される画像上の診断名なので、臨床的に問題となるような症状はありません。
ただ、発育性股関節形成不全のように、大腿の皮膚溝(しわ)が非対称であったり、脚の開きが悪いこと(開排制限)があります。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
子どもの臼蓋形成不全の場合、股関節の動きの悪さはありますが、痛みなどの症状が出ることはあまりありません。
しかし、大人の臼蓋形成不全の場合、後に解説する変形性股関節症の初期と同じであり、立ち上がる時や歩き始めなど、動作の始めに股関節の前側や外側に痛みを生じる場合があります。
股関節は大腿骨頭と臼蓋が上手くはまり込むことで自由に動くことができます。
ですが、臼蓋の形成が不十分であると、大腿骨頭が臼蓋に上手くはまり込まず、骨と骨がぶつかったり、筋肉や腱を関節に挟み込んでしまうことで、痛みが起こります。
※臼蓋形成不全の方が特に気をつけるべき内容や、痛みの対処法は以下の記事にわかりやすくまとめています。
変形性股関節症
変形性股関節症とは、先天的な問題、あるいは慢性的な股関節への負担が原因となり、股関節を構成する大腿骨頭や臼蓋が変形し、関節の隙間が狭くなる、あるいは関節の間にある軟骨がすり減ることを指します。
関節の隙間が狭かったり軟骨がすり減ると、大腿骨頭が臼蓋に上手くはまり込まない、股関節の一部分に負担が集中するなどが起こり、股関節の痛みの原因になります。
股関節症のおもな症状は、関節の痛みと機能障害です。股関節は鼠径部(脚の付け根)にあるので、最初は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。
関節症が進行すると、その痛みが強くなり、場合によっては持続痛(常に痛む)や夜間痛(夜寝ていても痛む)に悩まされることになります。
■参照元:公益社団法人日本整形外科学会
変形性股関節症は進行する病気ですので、痛いのを放っておくと、徐々に関節の変形が強くなり、最終的には手術が必要となる場合もあるので、動き始めの痛みが続くようなら一度整形外科を受診することをお勧めします。
※変形性股関節症かも?と不安な方は下記の記事で症状をチェックして見極めてみましょう!
股関節が硬い・痛くなる原因
股関節が硬い、痛くなる原因としては以下の3つです。
- 筋肉が硬い
- 同じ動きの繰り返し
- 姿勢の悪さ
それぞれ解説していきます。
筋肉が硬い
単純に筋肉が硬くなると、股関節へかかる負担は大きくなります。
股関節は曲げる・伸ばす、開く・閉じる、ひねるといったあらゆる方向へかなり大きく動かすことができる関節です。
それだけ大きく動くのは、日常生活の中でも大きく動く機会が多いということです。
ですが、股関節の筋肉が硬くなると、当然股関節の動きは制限されてしまいます。
股関節の動きが制限された状態で、大きな動きが要求されると、筋肉にも股関節自体にも負担がかかります。
それを繰り返すことで、筋肉がより硬くなったり、筋肉に微細な傷がついて炎症を起こすことで、痛みにつながります。
また、将来的に変形性股関節症になるリスクも高くなってしまうでしょう。
同じ動きの繰り返し
同じ動きを繰り返し行うことで、同じ部分に負担が繰り返しかかることになります。
たとえば、しゃがんだり立ったり、立ち座りを繰り返す、階段の昇り降りをすることが多い、サッカーやマラソンなど股関節をよく使うスポーツなどが該当します。
同じ動きを繰り返すということは、特定の筋肉にばかり負担がかかっているということで、その筋肉は緊張して硬くなりやすく、股関節の動きも制限してしまいます。
その結果、筋肉自体の痛みや血流の悪さによる痛み、筋肉が硬くなることによる関節の動きの悪さで痛みが起こります。
姿勢の悪さ
普段の姿勢の悪さは股関節の筋肉を硬くする原因になります。
たとえば、デスクワークが多く、座っている時間が長い方。
座っていると、股関節の前側にある腸腰筋や大腿筋膜張筋といった股関節を曲げる筋肉が縮みます。
座っている時間が長いと、股関節を曲げる筋肉は縮んだままで伸びる機会がないので、緊張して硬くなってしまいます。
すると、股関節の動きは制限され、股関節に負担がかかりやすい状態となってしまうのです。
どんな姿勢にせよ、同じ姿勢で長時間過ごすことは、股関節はもちろん他の関節にも良い影響は与えません。
股関節が硬くなることで起こるデメリット
股関節が硬いと様々なデメリットがあります。
股関節が硬いことで起こるデメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 怪我をしやすくなる
- 血流が悪くなる
- むくみやすい
- 冷えやすい
- 疲れやすい
- 痩せにくい
関節が硬いので怪我をしやすいですし、血流が悪くなることでむくみや冷えも起こりやすいです。
さらに、股関節が硬いということは、股関節の動きを他の関節で補わないといけず、言い換えると無駄な動きが増えます。
なので、余計にエネルギーを消費するため、疲れやすい体になってしまいます。
また、エネルギー効率が悪いことと血流が悪いことで代謝も悪くなるので、痩せにくい体になってしまうでしょう。
股関節が柔らかいことによるメリット
股関節が硬いと様々なデメリットがあることがわかりましたよね。
ですが、股関節が柔らかければ、股関節が硬いことによるデメリットとは反対のことが起こるというこが言えます。
- 怪我をしにくくなる
- 血流が良くなる
- むくみにくい
- 冷えにくい
- 疲れにくい
- 太りにくい
このように、改めて言葉にして挙げると、多くのメリットがあることがわかります。
股関節が柔らかい状態を保てれば、股関節の痛みは起こりにくいし、上記のような多くのメリットもあるので、股関節が硬い人は意識して柔らかくすると良いでしょう。
股関節の硬さ・痛みに対する対策
股関節の硬さ、痛みに対する対策としては以下の3つが挙げられます。
- ストレッチ
- 筋トレ
- 普段の姿勢の見直し
それぞれ解説します。
ストレッチ
筋肉の硬さに対しては、シンプルにストレッチで伸ばすことが効果的です。
ここでは、股関節の筋肉の中でも特に硬くなりやすい股関節の付け根に付く腸腰筋、おしりの大殿筋、内ももの内転筋のストレッチの方法を解説します。
腸腰筋のストレッチ
- 両膝立ちになる
- 片足を前方に大きく出す
- 前足に体重をかけ、後ろ足の股関節の付け根を伸ばす
- そのまま15~20秒キープする
- 3回程度繰り返す
ポイントは、体幹が前に傾かないように真っすぐに保ち、少し腰を丸めることで、より腸腰筋が伸ばされます。
大殿筋のストレッチ
- 椅子に腰かける
- 片足を反対側の膝の上に乗せる
- 乗せた側の足首と膝を水平になるように上から軽く押さえる
- 水平に保ったまま、体を前に倒す
- 倒した状態で15~20秒キープする
- 3回程度繰り返す
ポイントは、体を前に倒す際、腰が丸くならないように注意しましょう。
腰が丸くなると、大殿筋はあまり伸ばされないので、ストレッチの効果が薄くなってしまいます。
内転筋のストレッチ
- 両膝立ちになる
- 片足を体の真横に出し、つま先を真横に向ける
- 横に出した足へ体重をかける
- 横に出した足と反対側の内ももを伸ばす
- その状態で15〜20秒キープする
- 3回程度繰り返す
ポイントは、真横に出した足に体重をかける際、体が倒れないように注意しましょう。
体が倒れると、内転筋があまり伸びないのでストレッチの効果が薄れてしまいます。
※痛みに効く股関節周りのストレッチは下記の記事にもわかりやすくまとめています。
筋トレ
筋肉は曲げる筋肉があれば、伸ばす筋肉があるように、反対の働きを持つ筋肉が存在しています。
一方の筋肉が働く時、反対の働きを持つ筋肉は邪魔にならないように力が抜けるという特性があります。
たとえば、曲げる筋肉が働く時は伸びる筋肉は緩んで伸びます。
なので、ストレッチで解説した硬くなりやすい筋肉の反対の働きを持つ筋肉を鍛えると、硬くなりやすい筋肉も緩んで伸びやすくなるということです。
ここでは、ハムストリングス、中殿筋の筋トレを紹介します。
ハムストリングスの筋トレ
- うつ伏せになる
- 膝を伸ばしたまま片足を持ち上げる
- 元に戻す
- 反対側の足も同様に持ち上げる
- 元に戻す
- 左右交互に10回ずつ繰り返す
ポイントは、足を持ち上げる際に腰が反らないように軽くへそを引っ込めるように力を入れておくことです。
中殿筋の筋トレ
- 横向きに寝る
- 下側の足は股関節と膝を90度に曲げる
- 上側の足は膝を伸ばしたまま、上に持ち上げる
- 元に戻す
- 10回程度繰り返す
ポイントは、足を持ち上げる際に骨盤が動かないようにすることです。
骨盤が動かないように、足を遠くに伸ばしながら持ち上げると効果的に中殿筋を鍛えることができます。
普段の姿勢の見直し
座っている時間が長い、足を組むことが多い、どちらかの足に体重をかけて立っていることが多いなど、同じ姿勢を長時間とっている方は普段の姿勢を見直すことが大事です。
30分〜1時間に1回は少し体を伸ばしたり、軽く体を動かすなど、同じ姿勢のままにならないようにすることがポイントです。
股関節が硬くなるだけでなく、体の様々な不調の原因にもなるので、適度に体を動かす時間を作るのが良いでしょう。
※上記の他に当店では効果的に痛みを改善出来るよう、あなたの痛みに効くおすすめの筋膜リリース動画をLINEから無料でお伝えしています。
理学ボディのおすすめ
ストレッチや筋トレをしても、股関節の硬さや痛みが変わらないという方は、理学ボディで施術を受けることがおすすめです。
理学ボディでは、最短で痛みを改善させることにこだわっており、筋膜という組織に対して施術を行います。
筋膜は筋肉を包んでいる膜状の組織で、筋膜が硬くなると筋肉も上手く伸びたり縮んだりすることができません。
ストレッチで筋肉を伸ばすことはできますが、筋膜が硬くなっている場合、まずは筋膜をほぐさないと筋肉は上手く伸ばすことができません。
硬くなった筋膜をほぐすことのはストレッチや筋トレでは不十分な場合が多く、直接筋膜をほぐすことが有効なことが多いです。
なので、筋膜に精通しているセラピストに評価してもらい、ほぐしてもらうことで、筋膜も筋肉もほぐすことができ、股関節の動きが良くなった結果、痛みも解消されることが期待できます。
もし、股関節の硬さや痛みを早く治したくてお困りでしたら、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。