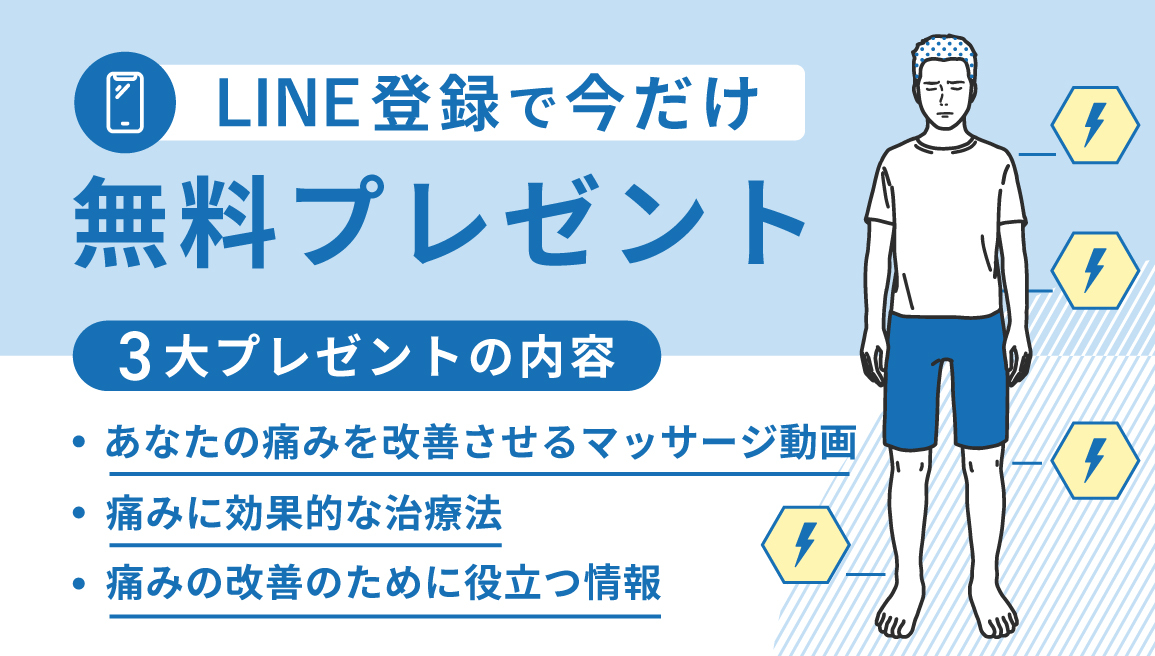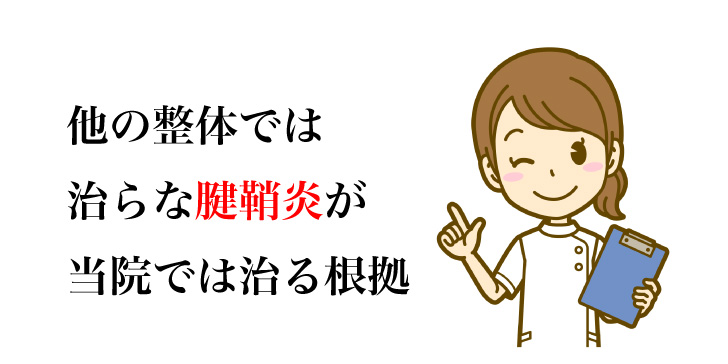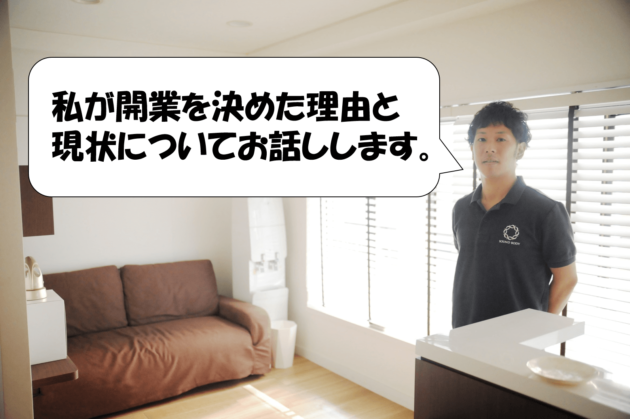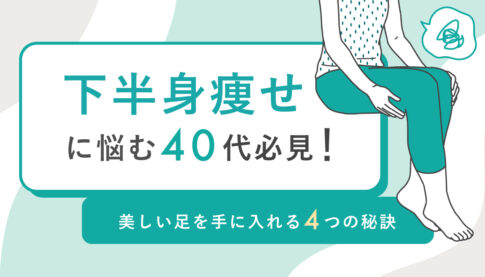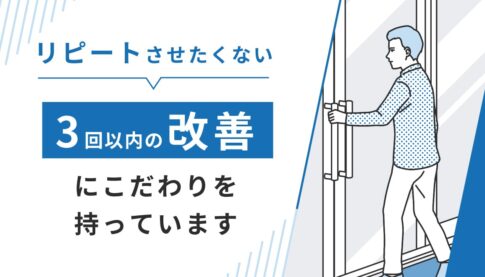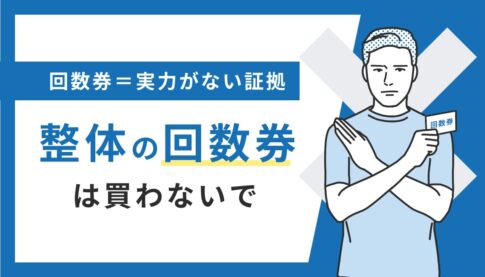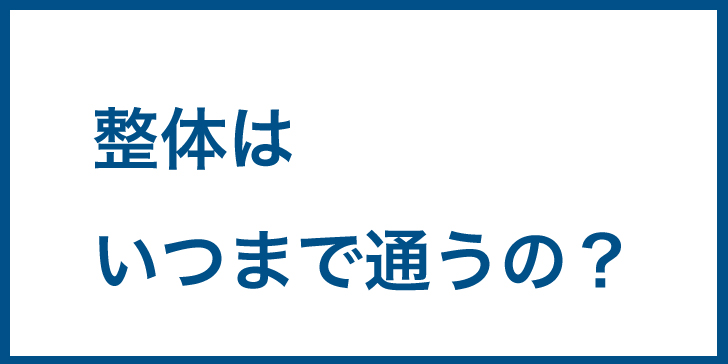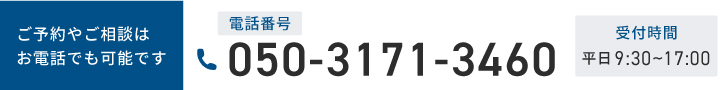「歩き始めや立ち上がった時に股関節が痛む。」
「股関節が痛いからストレッチとかした方が良いのかも。」
歩く、立ち上がるといった日常的な動作で股関節が痛くて悩んでいませんか?
また、股関節が痛いからストレッチなど自分で対策した方が良いのか、しない方が良いのかも自分では中々判断できないかもしれません。
ストレッチするのは良いですが、ストレッチ自体が股関節の痛みの原因になってしまう可能性があることを知っておかなければいけません。
良かれと思ってしていることが、実は股関節にとっては悪い場合もあるからです。
今回は股関節が痛い時に考えられること、股関節が痛くなる原因、対策、効果的なストレッチを解説します。
股関節が痛い時に考えられること
転んでおしりをぶつけた、交通事故にあったなど、明確な痛くなったきっかけがある場合は骨折や筋肉、靭帯損傷などの外傷が考えられます。
ですが、そうでない場合で、股関節が痛い時に考えられることとしては、おもに以下の3つが考えられます。
- 筋肉の痛み
- 変形性股関節症
- 臼蓋形成不全
まず、第一に疑われるのは、股関節の周りにある筋肉の痛みです。
変形性股関節症や臼蓋形成不全は慢性的に股関節に負担がかかっている、あるいは、先天的な問題が影響するので、一日や二日でなるようなものではありません。
股関節の痛みを感じた時、以前から痛みや違和感があったわけではなく、突然痛くなったのであれば、何らかのきっかけで筋肉に一時的に問題が生じている可能性が高いです。
そうではなくて、以前から痛みや違和感を感じていたのであれば、変形性股関節症や臼蓋形成不全の可能性もありますので、一度整形外科で医師による診察を受けることをお勧めします。
それぞれ以下に解説していきます。
筋肉の痛み
上述した通り、股関節の痛みのほとんどは筋肉が原因の痛みです。
- 普段しない運動をした
- 運動前の準備体操をせずに始めた
- 運動習慣がない方が急に運動を始めた
- ストレッチで強く伸ばしてしまった
- 痛いのを我慢してストレッチした
- 長時間同じ姿勢で作業した
- 同じ動きを繰り返し行なった
上記に挙げたようなきっかけで、筋肉がこわばって硬くなると、痛みを感じる可能性があります。
筋肉をはじめ、皮膚や靭帯には痛みを感知するセンサーのような組織が備わっています。
筋肉がこわばると、このセンサーに負荷がかかり、それを感知して痛みとして脳に伝えることで、痛みが起こります。
また、筋肉内には血管が通っていますが、筋肉のこわばりによって血管が圧迫されると、血流が悪くなり、痛みを起こす発痛物質というものが作られます。
それも痛みを起こす原因の1つになるので、筋肉のこわばりが解消されない限りは血流も悪いままなので、発痛物質も作られ続けることとなります。
さらに、それが続くと、筋肉のこわばりは股関節の動きを悪くするので、筋肉だけでなく、股関節自体にも負担がかかります。
短期的には股関節内で炎症を起こすことで痛みが起こったり、長期的には上述した変形性股関節症のような病気にもつながります。
なので、筋肉の痛みを感じたら、早めに筋肉のこわばりをケアしてあげてこわばりを慢性化させないことが大切です。
変形性股関節症
股関節は骨盤という受け皿に先端が丸い大腿骨の頭がはまり込む形をとっており、うまく転がったり滑ったりしながら自由自在に動くことができます。
変形性股関節症とは、先天的な問題や股関節への慢性的な負担が原因で、股関節を構成する骨盤、あるいは大腿骨の頭の一部が変形し、関節の隙間が狭くなったり軟骨がすり減ってしまうことを指します。
変形や軟骨のすり減りによって、骨盤にうまく大腿骨の頭がはまり込まない、うまく体重を支えられないことで、股関節にかかる負担が増してしまい、痛みにつながります。
股関節症のおもな症状は、関節の痛みと機能障害です。股関節は鼠径部(脚の付け根)にあるので、最初は立ち上がりや歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。
関節症が進行すると、その痛みが強くなり、場合によっては持続痛(常に痛む)や夜間痛(夜寝ていても痛む)に悩まされることになります。
■参照元:公益社団法人日本整形外科学会
関節の変形が進行すると、痛みだけでなく、うまく歩くこともできなくなってきて、手術が必要になる場合もあります。
臼蓋形成不全
大腿骨の頭の受け皿は骨盤ですが、これを臼蓋と言い、子供の成長に伴って発育していきます。
これが、何らかの原因で発育不足となったのが臼蓋形成不全です。
小児期の臼蓋形成不全は基本的には乳児の時に超音波やX線(レントゲン)で診断される画像上の診断名なので、臨床的に問題となるような症状はありません。
ただ、発育性股関節形成不全のように、大腿の皮膚溝(しわ)が非対称であったり、脚の開きが悪いこと(開排制限)があります。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
小児の場合、特に痛みなど症状はありませんが、成人の臼蓋形成不全は変形性股関節症の初期に当たり、変形性股関節症に見られるような、動き始めや動いた後に股関節の前や外側に痛みが生じる場合が多くみられます。
ストレッチが股関節の痛みの原因になる
ストレッチは正しく行えば、股関節の痛みに対して効果的ですし、筋肉を柔らかくし股関節の動きを良くすることができます。
ですが、ストレッチは良いものだと思ってやりすぎると逆効果になってしまう場合があります。
ストレッチはこわばり硬くなった筋肉に対して行いますが、こわばっている筋肉を伸ばすので、伸ばされまいと抵抗する力が加わります。
それを無視して、強くストレッチしたり長時間ストレッチすると、筋肉には微細な傷がついてしまい、それが痛みや炎症を引き起こしてしまう可能性があります。
炎症が起こると、治る過程で筋肉はむしろ硬くなってしまうので、痛みも出るし筋肉も硬くなるしでデメリットが大きいです。
なので、股関節の痛みに対してストレッチするのは良いですが、痛みが出ない範囲で正しく行う必要があります。
股関節の痛みに効果的な対策
股関節の痛みに対して効果的な対策は以下の3つです。
- ストレッチ
- 筋トレ
- マッサージ
ストレッチと併せて、筋トレやマッサージも行うとより効果的です。
それぞれ解説します。
ストレッチ
上述した通り、間違った方法で行うと痛みを解消することはできませんが、正しく行えば股関節の痛みに対して効果的な対策の1つです。
正しいストレッチのポイントは強度と時間です。
具体的には以下のポイントを守ってストレッチしましょう。
- 痛みが出る一歩手前、気持ち良く伸ばせるくらいの強度
- 1回20~30秒のストレッチを2~4セットを目安
ここでは、特にこわばりやすい股関節の前側と内側の筋肉のストレッチについて紹介します。
股関節前側のストレッチ
普段の生活の中で、座る、しゃがむ、またぐ、階段を昇るなど、股関節を曲げる動きは多いですが、股関節を伸ばす動きは少ないです。
なので、日ごろからよく使う股関節を曲げる筋肉はこわばりやすいため、ストレッチで伸ばすことが必要です。
それが、股関節の動きを良くして、痛みの解消や怪我の予防につながります。
具体的な方法は以下の通りです。
- 壁に対して横向きに、膝立ちになる
- 壁と反対側の足を前に出す
- 前に出した足に体重をかけ、壁側の股関節の付け根をストレッチする
- 20秒程度キープし、元に戻る
- 繰り返し行う
ポイントは、腰を反らないように下っ腹に軽く力を入れておくこと、へそは真っ直ぐ前に向けておくことです。
腰が反ると上手く股関節の付け根がストレッチされないので、注意が必要です。
股関節内側のストレッチ
股関節内側の筋肉も前側の筋肉と同じく、普段の生活であまり伸ばされることがない部分です。
なので、ここもストレッチで伸ばすことで、股関節の痛みの解消や怪我の予防につながるので、ストレッチしてあげましょう。
具体的な方法は以下の通りです。
- 膝立ちになる
- 片方の足を膝を曲げ外側につき、つま先はなるべく真横を向くようにする
- 外側についた足に体重をかけ、股関節の内側をストレッチする
- 20秒程度キープし元に戻る
- 繰り返す
ポイントは、しっかりとつま先を外側へ向け膝とむきをそろえること、へそを真っ直ぐ前に向けることです。
つま先と膝の向きがそろっていないと、膝がねじれて膝の痛みの原因になりますし、上手く股関節の内側を伸ばすことができないので、注意しましょう。
筋トレ
股関節の周りには多くの筋肉があるので、どこかの筋力が弱ってしまうと、体重をかけた時に上手く体を支えられない、真っすぐ歩けないといったことが起こります。
それがすぐに痛みに直結するわけではありませんが、そうした動きのズレや左右での差が長期間続くと、少しずつ股関節に負担となり、筋肉のこわばりにつながります。
理想は股関節の前後左右の筋力のバランスが取れていることです。
ここでは、特に筋力が低下しやすいおしりと骨盤の外側から外ももにかけての筋トレを紹介します。
おしりの筋トレ
おしりの筋肉は大殿筋という大きな筋肉があります。
大殿筋は大腿骨を後ろへ引く働きがあり、この動きには大殿筋が大きく関与しています。
ですが、生活の中で大腿骨を後ろへ引く動きというのは、歩く、階段を昇る以外にはそんなになく、股関節を曲げている方が生活の中では多いため、大殿筋は弱くなりやすいです。
具体的な筋トレの方法は以下の通りです。
- 仰向けで両膝を立てる
- おしりを持ち上げて、体と一直線になるようにする
- ゆっくりとおしりを降ろす
- 繰り返す
膝はかかとが膝の真下にくるくらいに曲げておくと、大殿筋に力が入りやすくなります。
骨盤外側から外ももの筋トレ
骨盤の外側には中殿筋や大腿筋膜張筋という筋肉があり、外ももにはそれらと連結する腸脛靭帯という靭帯があります。
これらが弱くなると、歩いている時なんかにおしりが横に突き出てしまったり、膝が内側に入りやすくなります。
しっかりと筋力があれば、外側から骨盤や外ももを押さえる役割があり、真っすぐ歩くことができる、股関節にしっかりと体重をかけることができます。
具体的な筋トレの方法は以下の通りです。
- 横向きに寝る
- 下側の足は股関節を45度、膝を90度くらいに曲げておく
- 上側の足は体と一直線上にくるようにする
- 上側の足を真上に持ち上げる
- 元に戻す
- 繰り返す
上側の足を持ち上げる際、骨盤や体が前後に傾いてしまう場合があるので、傾かないように注意して行いましょう。
マッサージ
マッサージはストレッチで中々ほぐせない部分に行うと効果的な方法です。
ここでは、特にこわばりやすく、股関節の痛みにつながりやすい大腿直筋という筋肉をマッサージする方法を紹介します。
大腿直筋は前ももから膝にかけて伸びる長く大きな筋肉です。
これは膝を伸ばす働きがある筋肉ですが、股関節を曲げる働きもある筋肉です。
ですが、この筋肉がこわばっていると、股関節を曲げる際に邪魔になってしまう場合があります。
そのせいで、股関節の他の筋肉の働きも邪魔してしまうので、自分でマッサージでケアすると良いでしょう。
具体的な方法は以下の通りです。
- 骨盤の前側の出っ張りを探す(へそを挟んで左右に1つずつある)
- その出っ張りのすぐ下に親指を横にして当てる
- 親指で少し圧迫しつつ、指を左右に動かしてマッサージする
骨盤の出っ張りのすぐ下には大腿直筋の腱があります。
ここが大腿直筋でも硬くなりやすいポイントなので、マッサージしてみください。
まとめ
股関節が痛い時にまず考えられるのは、筋肉が原因の痛みです。
それらの多くは、筋肉のこわばりによる血流の悪さや股関節の動きの悪さが関係します。
なので、ストレッチすることは効果的ではありますが、無理やり伸ばしたり、長時間伸ばすとかえって逆効果になってしまうこともあります。
ですが、正しくストレッチを行えば、筋肉のこわばりには効果的で痛みの解消も可能ですので、本記事を参考にこわばりやすい筋肉をストレッチしてみてください。
また、筋トレやマッサージも併せて行うことで、筋肉のこわばりを予防することができ、怪我の予防につながるので、是非行ってみてください。