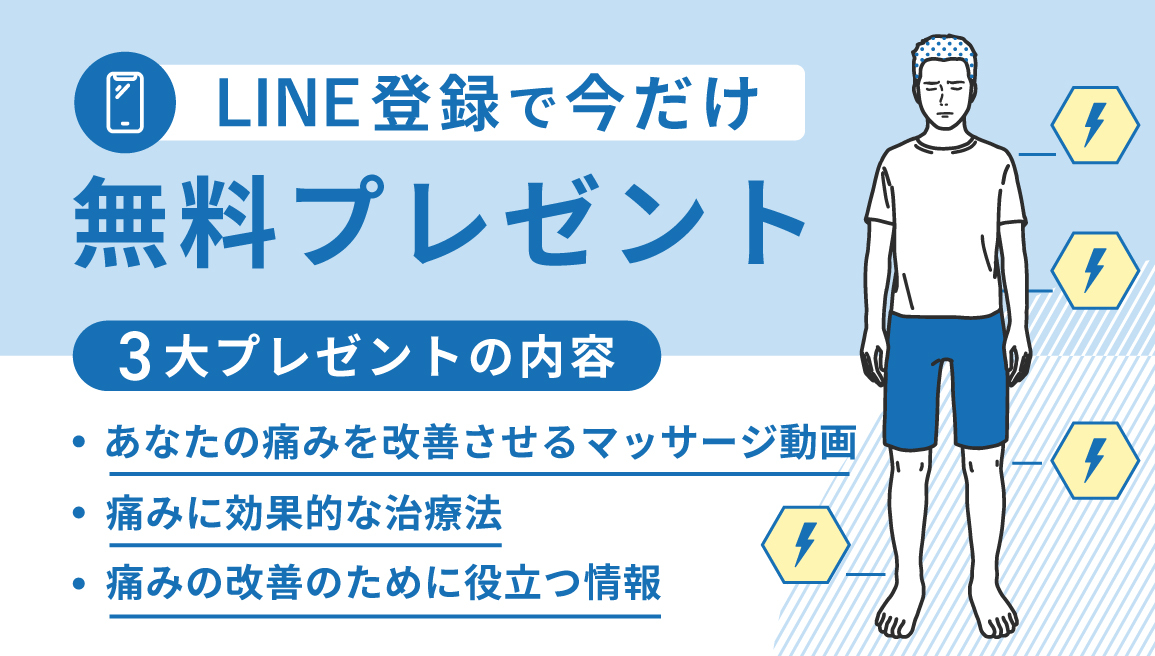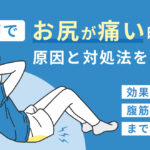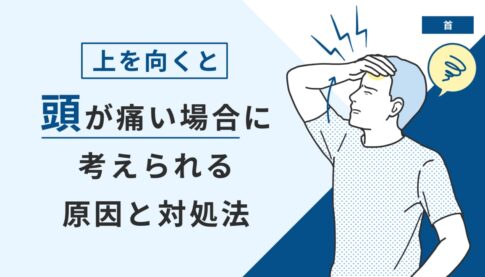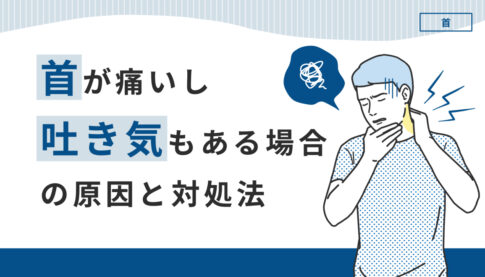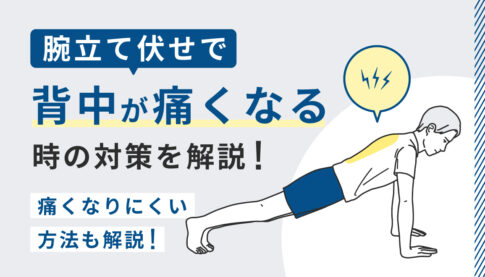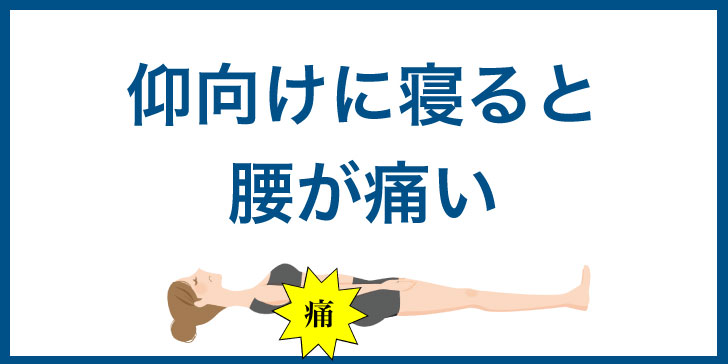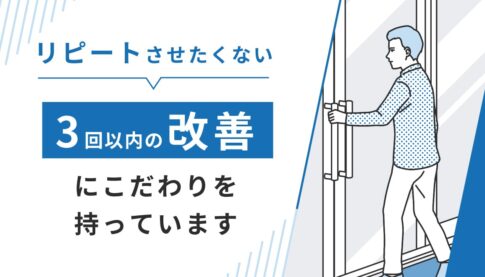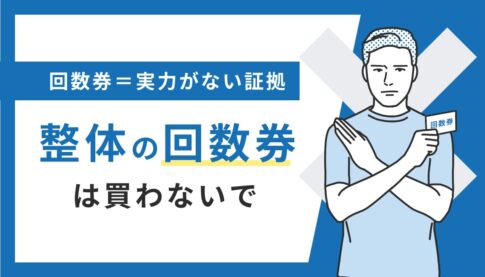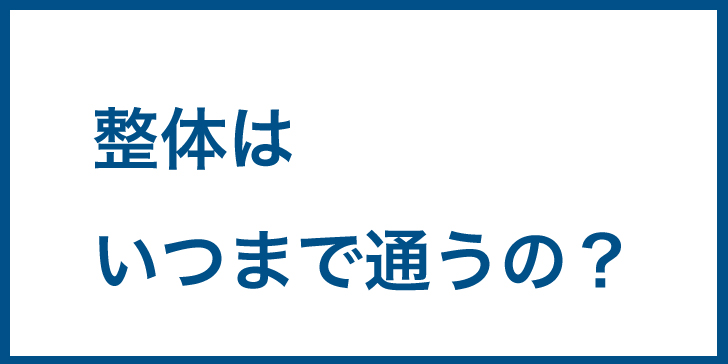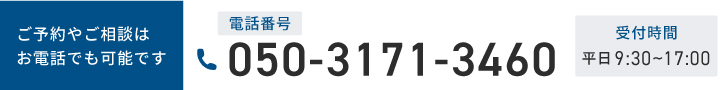産後のママは、出産時の傷の痛みや後陣痛、関節痛など、様々な「痛み」に襲われます。
「交通事故だと全治3ヵ月相当」とも言われる産後の体のダメージ。
赤ちゃんとの暮らしも、痛みがあっては辛いですよね。
その中の1つが足の甲の痛み。
足の甲の痛みは、歩くとき、授乳や抱っこなど、産後の生活のどんな時にも起こります。
産後ママにありがちな悩みですが「産後だから仕方ない」と思われがちです。
でも、そんなことはありません。
足の甲の痛みは原因と対処法が分かれば、予防したり軽減させることができます。
この記事では、産後の足の甲の痛みに悩む方に向けて、痛みの原因や対処法を理学療法士が解説します。
「足の甲が痛む理由が知りたい」
「痛みが続いているけど、病院に行った方が良いの?」
「足の甲をケアしたいけど、赤ちゃんが小さくて外出できない」
という方は、まず足の甲の痛みの原因を知り、セルフケアを試してみてください。
※足の甲ではなく、足首が痛む場合は、以下の記事をお読みください。
「足の甲の痛みを一刻でも早く治したい」という方は、専門店への相談をおすすめします。
目次
産後に足の甲が痛いときに考えらえること
産後に足の甲が痛いときに考えられることは、次の4つです。
- むくみ
- 筋力不足
- 育児姿勢による足への負担
- 足の使い方の問題
これらはいずれも、産後のママに特徴的なものです。
1つずつ見ていきましょう。
むくみ
まず1つ目に考えられることは、足のむくみです。
むくみとは、とくに皮下組織に異常に水がたまった状態のことで、医学用語では「浮腫(ふしゅ)」と呼ばれます。
むくみは全身どこにでも起こりますが、重力の影響により、心臓より下、とくに心臓から遠い足に多くあらわれます。
産後は、特に次のようなむくみ症状が見られます。
- ゾウの足のような見た目になる
- 足首やくるぶしが見えないなくなる
- 皮膚がパンパンになり、テカテカする
- 皮膚が突っ張り、しゃがめない
- 出産前に履いていた靴が入らない
- いつもは寝れば治る足のむくみが治らない
- 顔がむくんで丸い
- 手指がむくんで指輪が入らない
産後は、足だけでなく顔や手など、通常ではむくみにくい場所もむくんでしまいます。
足の甲がむくむと、足首や足の指が動かしづらくなります。
むくんだ足のまま足に体重をかける(立つ・正座・しゃがみ姿勢など)と、皮膚が突っ張り痛みを感じることがあります。
筋力不足
妊娠中はお腹が大きくなるほど動きにくくなるため、運動量は減ってしまいがちです。
また、産褥期は体を休めることが最優先となり、その分体力は落ちがちです。
さらに、出産直後は家の中で過ごすことが多く、体を動かす機会は少なくなりやすいです。
このように、妊娠・産後はどうしても運動不足になりがちです。
そのため、足も含めて全身の筋力の低下が起こります。
特に、足の筋力が不足すると、体重を十分に受け止められず、足のトラブルの要因の一つとなります。
育児姿勢による足への負担
産後の姿勢の歪みが足へストレスをかけることもあります。
抱っこと授乳は、産後の育児で必須です。
抱っこは1日中反復して行うし、授乳も長いと20分以上かかることがあります。
猫背での授乳や長時間の片側抱っこなど、不適切な育児姿勢は足へ負担をかけます。
※授乳姿勢は、直母だけでなく、ミルク授乳でも同様です。
適切な育児姿勢のポイントは下記で解説します。
足の使い方の問題
姿勢の問題に加えて、足の使い方の問題も考えられます。
妊娠前に扁平足や外反母趾があった場合は、妊娠をきっかけに悪化しがちです。
その理由は、妊娠中の女性ホルモンの変化によって関節が緩むこと、妊娠中の急激な体重増加によるものです。
元々足首の関節が緩むと、土踏まずが低下したり、扁平足になりやすくなります。
足にかかる衝撃を吸収しにくくなり、足に痛みがでることがあります。
靴との相性が悪い(すり減った靴や踵のないサンダル)ことも、足の不安定感を増し、痛みの原因になることがあります。
産後に足の甲がむくんで痛むのはなぜ?
これらの3つの原因の中でも、特に足の甲の痛みと関係が深いのは、足のむくみです。
産前産後は、特に体がむくみやすい状況にあります。
むくみによる足の甲の痛みの特徴は、足がパンパンになって弾けそうな痛みです。
小さいサイズの靴を無理矢理履いたときの窮屈感を伴う痛みに似ています。
むくみの原因は、おもにホルモンの変化・体水分量の変化・育児の疲労の3つが考えられます。
どれも産前・産後に特有の原因であり、むくみに悩む方に知っておいていただきたい知識です。
ホルモンの変化
出産直後は、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが急激に減少します。
女性ホルモンの減少によるホルモンバランスの変化が引き起こす症状の1つにむくみがあります。
症状が激しい人は更年期のような状態となる場合もあります。
体水分量の変化
産前・産後のママの体では、体内を巡る血液や水分量も大きく変化します。
妊娠中に増えた血液や水分は、出産で減少します。産後は影響でむくみを感じる場合があります。
妊娠中、ママの血液量は妊娠前の1.5倍程に増えます。産後、急激に血液量が減ることで、体内の水分バランスを保ちにくくなり、むくみが発生しやすくなります。
■参照元:エナレディースクリニック
また、分娩時の会陰裂傷が重度であったり、分娩時間が長かったりすると、会陰や鼠径部のリンパ組織がダメージを受けることがあります。
これにより、余分な水分が排出されにくくなることで、産後のむくみが生じる場合もあります。
育児の疲労
ホルモンや水分量が不安定な状況に加えて、育児による疲労もむくみの要因になります。
出産の疲労に加え、生活リズムが定まっていない産後は、疲労が蓄積されがちです。
赤ちゃんをあやすために立ち姿勢が多くなる、授乳で同じ姿勢が続くといったことが重なり、むくみに影響することもあります。
睡眠不足や栄養不足も疲労を増長させてしまう要因です。
産後に足の甲が痛いのは良くなる?
まとめると、座りっぱなしでの足の甲の痛みは『むくみ』によるものが多いです。
この痛みが治るのかどうかは、気になるところですよね。
まず注意していただきたいのは、妊娠中に妊娠高血圧症候群によるむくみを経験した方です。
一般的に、軽症の場合は出産後速やかに症状が回復します。
しかし、重症の妊娠高血圧症候群では、産後もしばらく症状が続き、治療が必要な場合があります。
産後も頭痛・高血圧・むくみが続く場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
妊娠高血圧症候群では、産後でも産褥子癇という病気を発症する可能性があるため、油断は禁物です。
原因疾患のないむくみの場合は、水分量やホルモンバランスが落ち着くのに合わせて、むくみも徐々に軽減されます。
産後のむくみのピークは2日後とも言われていますが、個人差が大きいため一概には言えません。
私の場合は、産後2週間むくみが続き、退院のときに靴が履けなかったことを覚えています。
多くの場合、むくみが軽減されれば、足の甲の痛みも落ち着くでしょう。
下記の対処法を実践しながら、体の回復を第一に考えていただけたらと思います。
ただ、むくみが長引いたり、むくみ以外の原因で痛みが起きているときは、ケアが必要な場合があります。
むくみや不適切な姿勢により筋膜が硬くなったり、滑りが悪くなっている可能性があるからです。
このような痛みは、筋膜のケアで改善されることが多いです。
長引く痛みをいち早く解消したい方は、筋膜のケアの専門家への相談をおすすめします。
産後に足の甲が痛いときの対処法7つ
ここからは、具体的な対処法として、次の7つのセルフケアを見ていきましょう。
- ストレッチ
- マッサージ
- 姿勢を見直す
- 足の使い方を見直す
- 体を温める
- 食生活を見直す
- 適度に運動する
ストレッチ
ストレッチは、産後でも簡単にできる対策です。
足の甲の硬さが気になる場合には、足の周りを動かしてほぐすストレッチから始めてみましょう。
ストレッチで逆に痛みが増す場合は、無理せず他の対処法を試してみてください。
足指から足首を動かすストレッチ
足指の曲げ伸ばしや足首回しを、より丁寧に行ってみましょう。
むくんで動かしにくい場合は、手でアシストしてあげると、大きく動かすことが可能です。
足指・足首のどちらも、無理のない範囲で動かし始め、30回を目安に徐々に動きを大きくしましょう。
手でアシストする場合、足指は親指から1本ずつ動かすと、ストレッチ効果が高くなります。
股関節前側のストレッチ
産後の生活は、座る、しゃがむ、またぐ、階段を昇るなど、股関節を曲げる動きが多く、股関節を伸ばす動きは少ないです。
これが習慣的になると股関節の前側(付け根)が硬くなりやすいため、ストレッチで伸ばすことが必要です。
- 壁に対して横向きに、膝立ちになる
- 壁と反対側の足を前に出す
- 前に出した足に体重をかけ、壁側の股関節の付け根をストレッチする
- 20秒程度キープし、元に戻る
- 繰り返し行う
腰を反らないように下っ腹に軽く力を入れておくこと、へそは真っ直ぐ前に向けておくことがポイントです。
腰が反ると上手く股関節の付け根がストレッチされないので、注意が必要です。
マッサージ
足の甲が痛むときには、周りの筋膜が硬くなりがちです。
硬い筋膜をマッサージすることで筋膜をリリースすることができます。
育児の合間にケアしてみましょう。
全てのマッサージは、以下の手順で行いましょう。
- 筋膜の硬い部分(コリ)を見つける
- コリの場所を3〜10分間前後刺激する
- コリが複数箇所ある場合は、他の部分で①②を繰り返す
ここで重要なのは、同じ症状でもコリの場所は人によって違うことです。
足の甲が痛い方の中には、すねの外側の筋膜が硬い方もいれば、すねの内側の筋膜が硬い方もいます。
なので、必ずご自身のコリの状態や症状を確認しながら行うようにしましょう。
では、実際の様子を部位別にみていきましょう。
すねの内側の筋膜リリース
- 脛の内側の骨(脛骨)の後ろに指を当てる
- 膝と足首の真ん中から足首に向かって、少しずつずらしながら触る
- 硬い場所(コリ)・押されて痛みがある場所・滑りが悪い場所を見つける
- 上下・左右・斜めなどいろんな方向にマッサージする
踵の内側(外側)の筋膜リリース
- 踵の硬い骨(踵骨)を探す
- 踵と内(外)くるぶしとの間で、踵の骨の際を探す
- 骨の際をたどり、硬い場所(コリ)・押されて痛みがある場所・滑りが悪い場所を見つける
- 上下・左右・斜めなどいろんな方向にマッサージする
マッサージで注意点したいポイントは、刺激の強さです。
マッサージはつい手に力を入れたくなってしまいますが、実はゴリゴリとした強さは必要ありません。
なぜなら、強すぎる刺激は逆に体を壊してしまう可能性があるからです。
刺激の強さは、気持ち良いと感じる圧で行うようにしましょう。
姿勢を見直す
徐々に体を起こす時間が増えてきたら、育児姿勢を見直してみましょう。
足首への負荷を軽減させるためには、歪み姿勢の改善が大切です。
ここでは、抱っこと授乳時のポイントを、それぞれ3つに絞ってお伝えします。
- お腹を前に突き出さない
- 赤ちゃんの抱っこ位置はできるだけ高く
- 左右の時間を均等に
お腹を前に突き出した立ち姿勢は、歪み姿勢の最もメジャーな例です。
足の甲への負荷を軽減させるためには、お腹を前に出さずに立つように心がけましょう。
横抱きの場合は、脇を締めて手首の力は抜き、できるだけ赤ちゃんを胸に近づけましょう。
頭の位置を入れ替え、左右の腕にかかる時間が均等にすることも工夫の1つです。
縦抱きの場合は、赤ちゃんの頭とママのあごがぶつかるくらいの高さが理想です。
この姿勢を長続きできるよう、抱っこひもの調整も大切です。
特に、腰や背中のストラップは苦しくない範囲で出来るだけ締めましょう。
赤ちゃんが高い位置になるよう調節できると、抱っこの感じが軽くなるはずです。
- 骨盤を立てて座る(椅子の場合は深く腰掛ける)
- 背中を壁や背もたれにつける
- 授乳クッションで赤ちゃんやママの肘を支える
※直母でもミルク授乳でも同様です
椅子に座る場合は、椅子に深くかけ、背もたれを使いましょう。
床に座って授乳する場合は、骨盤の後面を壁に当てて座り壁に背中をつけましょう。
このとき、ズッコケ座りにならないよう注意しましょう。
また、赤ちゃんが低い位置にいると背中が丸まってしまいます。
授乳クッションなどを使い、赤ちゃんとママとの距離を近づけると猫背予防に繋がります。
頭を支える側の腕には、反対側の腕より負担がかかります。
タオルなどで高さをつけて上げると左右均等な姿勢がキープできます。
足の使い方を見直す
足首への負荷を軽減させるには、足の使い方を見直してみるのも1つの手です。
妊娠中は大きくなるお腹を支えるため、つま先重心になりがちです。
そして、赤ちゃんを出産した後も、この姿勢の癖が残ってしまうことがあります。
扁平足や外反母趾の進行を予防するためにも、足に適切に体重を乗せることが大切です。
まずは、立ち姿勢でのご自身の重心のかけかたを確認してみましょう。
肩幅に足を広げ立った時、体重がつま先よりにかかっていたり、小指側より親指側に多くかかっていたりしませんか?
偏りがある方は、踵・親指(母趾球)・小指(小趾球)の3点で体重を支えてみましょう。
イメージしにくい方は、足裏全体で地面を踏むように意識してみましょう。
立ち姿勢で体重のかけ方が確認できたら、抱っこや家事の姿勢でも同様にチェックしてみましょう。
抱っこ姿勢は、赤ちゃんが重くなればなるほど、どうしてもつま先に体重がかかりやすくなります。
3点均等に体重を乗せるのが難しくなってきたら、踵が浮かないよう意識して立ってみてください。
体を温める
一般的に、体を温めることはむくみ改善に効果があるとされています。
温浴の際は、水温を38度〜42度に設定しましょう。
この温度は、自律神経の副交感神経が優位になり、血管が拡張されやすくなります。
すると、体を循環する水分量が増えるため、むくみ改善に繋がる、というメカニズムです。
食生活を見直す
食生活もむくみと関係があります。
特に、塩分が多い食事には注意が必要です。
育児で自分の食生活にまで手が回らず、インスタント食品や丼もの、パン食などに偏ってしまう方もいることと思います。
これらの食品は、塩分を多く含みます。
体の中に塩分が増えると、浸透圧を保つために、体内の水分を溜め込もうとします。
これは、自分でむくみやすい体質を作っているとも言えます。
産後はカット野菜やミールキットを活用して、バランスの良い食事を心がけましょう。
最近はレンジを使う時短レシピも数多くあります。
本やインターネットで、『時短レシピ』を調べてみてください。
適度に運動する
産後は、授乳や抱っこで「座りっぱなし」「立ちっぱなし」といった生活となりがちです。
どちらも、足の筋肉を使う機会が少ないため、むくみを悪化させます。
外出ができるようになったら赤ちゃんと一緒に散歩をしてみましょう。
ウォーキングは、産後のママが一番手軽にできる全身運動です。
全身の筋肉を動かすため、むくみを軽減させる効果が期待できます。
また、散歩には産後うつの予防効果もあると言われています。
ママの心身の健康のためにも、散歩は是非実践していただきたい対処法です。
散歩に出るときは、転倒予防や足への負担軽減のため、すり減った靴や踵のないサンダルを避け、足にフィットしたスニーカーを履くようにしましょう。
今すぐ痛みをどうにかしたいなら理学ボディ
産後の足の甲の痛みは、これら7つの対処法を試しながら、様子をみてみてください。
産後2~3ヵ月経っても、痛みが長引く場合は、筋膜に原因があるかもしれません。
長引く痛みをどうにかしたい方は、私たち「理学ボディ」にご相談ください。
理学ボディでは、筋膜リリースの専門家が、全身の筋膜の状態をみながら、時には症状がある部位から離れた筋膜にアプローチすることができます。
ご自身でのケアに限界を感じたら、私たちプロを頼ってください。
理学ボディは全員が理学療法士という国家資格を取得しており、医学的知識をもとに施術します。
また、私たちは筋膜に特化した施術(筋膜リリース)を行います。
そして3回以内に卒業できることにこだわっています。
もちろん、全員が1〜3回の施術で改善するわけではありませんが、他の整体や病院に行くよりは少ない回数で改善できる自信があります。
ですので、短期間で痛みを改善させたい方は、一度ご相談いただければと思います。
理学ボディは北海道から九州まで店舗を展開しています。
症状にお困りの方は、一度お近くの店舗にご相談ください。
まとめ
この記事では、産後の足の甲の痛みの原因や対処法を理学療法士が解説しました。
足の甲の痛みは7つのセルフケアで対処すると共に、長引く場合は私たち理学ボディを頼ってください。
現在、理学ボディではLINEで痛み診断や改善動画のプレゼントを行っています。
ご自身の痛みが気になっている方は、気軽にお問い合わせください。