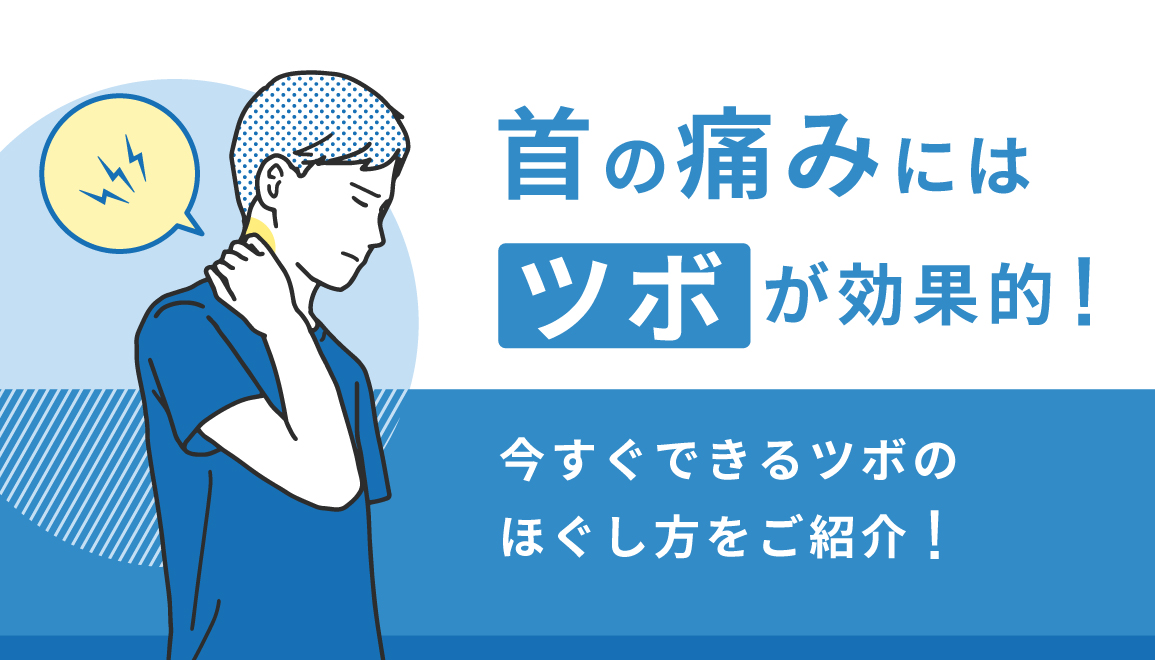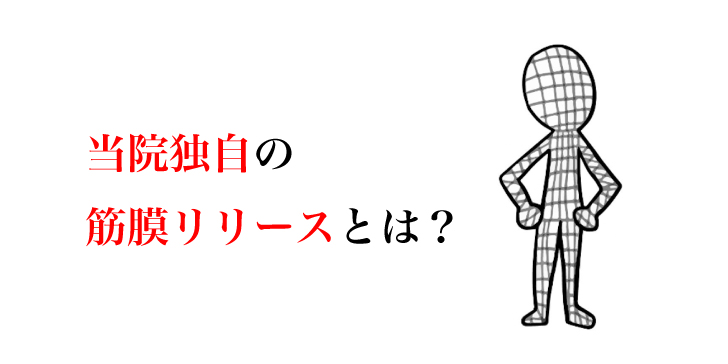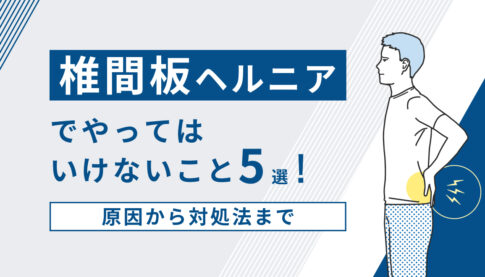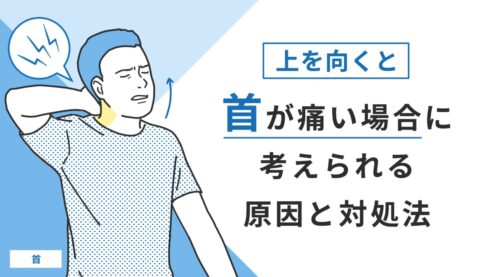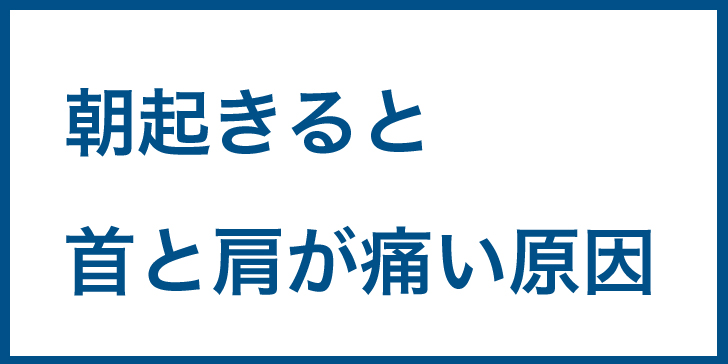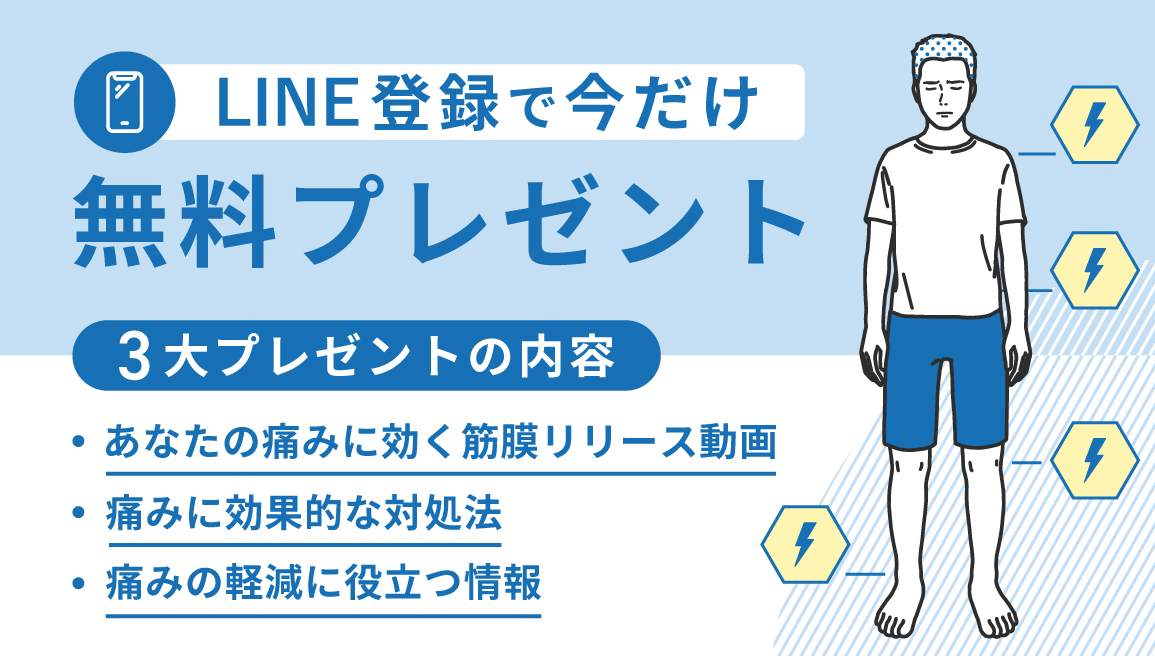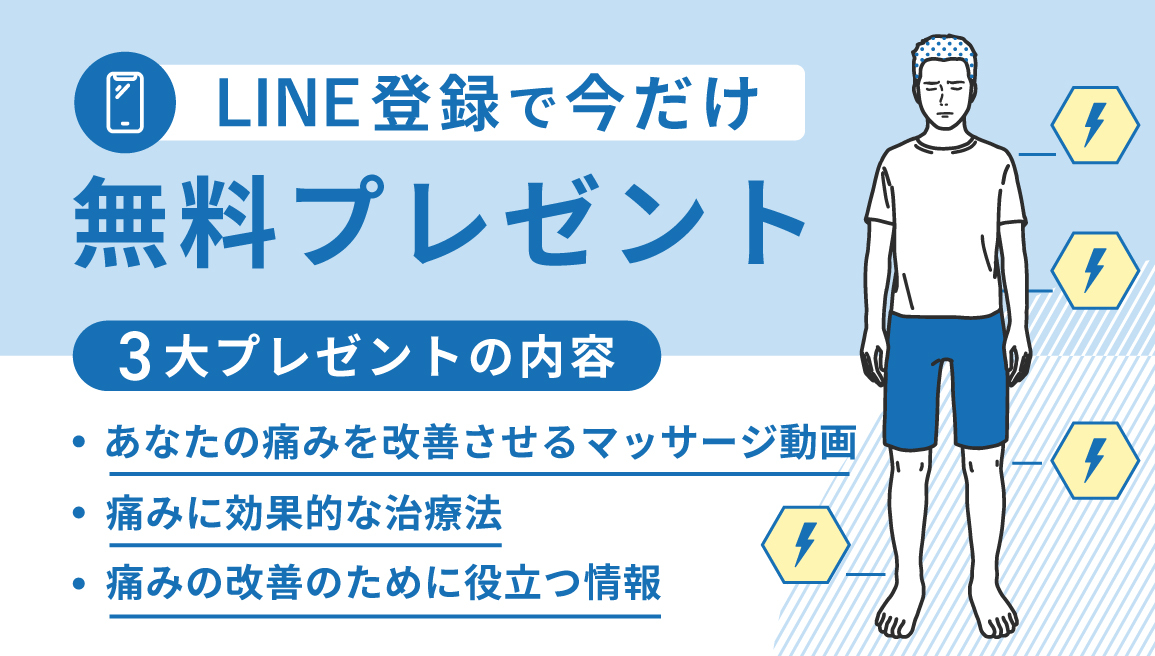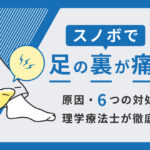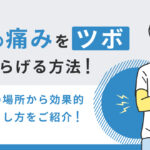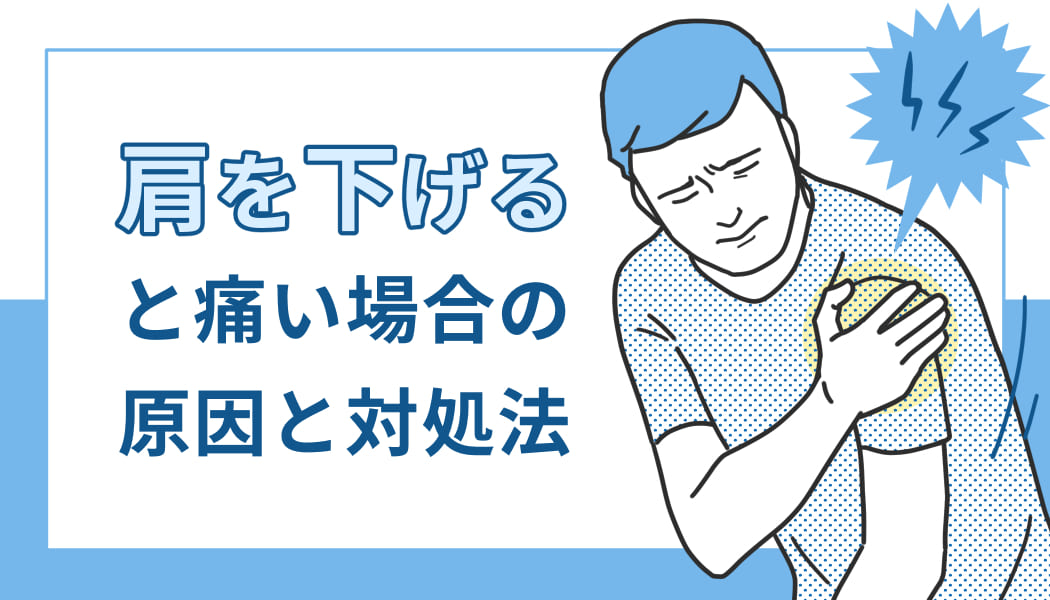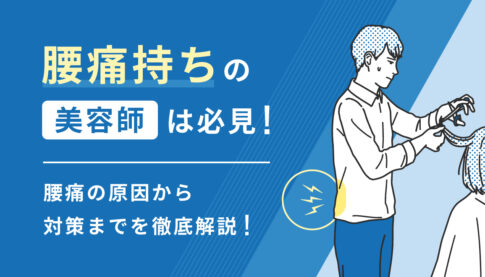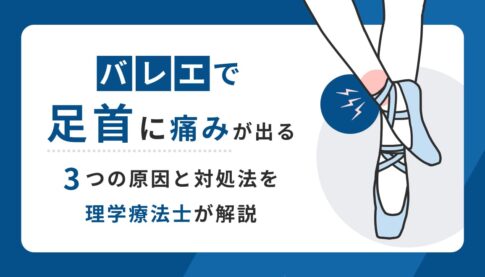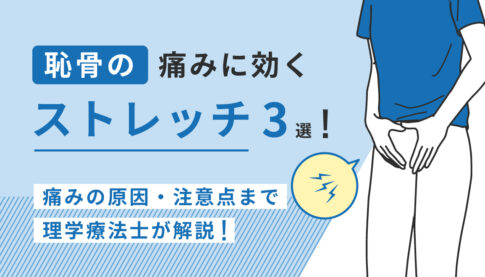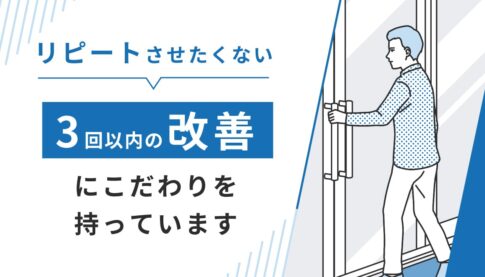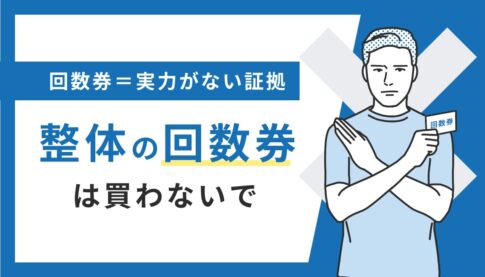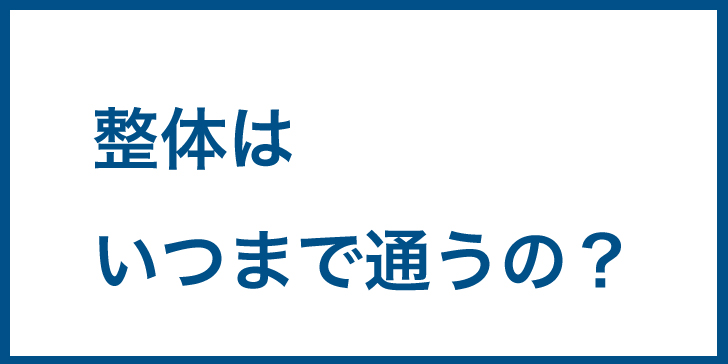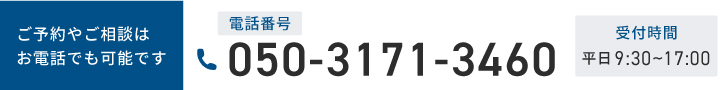上を向くと首が痛くなる。
首から肩がズシーンと重く、動くのもやる気が出ない。
首を動かすと痛いので、あまり首を動かせない。
このような悩みありませんか?
首は痛くなければそれほど気になりませんが、痛みがあるとかなり生活に支障が出て、ストレスを感じてしまいますよね。
自分でストレッチしようとしても、痛みがあるとストレッチするのも難しかったり、上手く伸ばせないこともあるはずです。
そんな方にお勧めなのが、ツボをほぐすことです。
ツボには痛みを和らげる効果のあるものあり、首や肩の痛みに対応したツボも存在します。
そこで、今回は首の痛みを和らげるためのツボの場所やツボの効果的なほぐし方について解説していきます。
※当院では、国際的に認知されている筋膜リリースという技法を用いてあなたの痛みを即時的に解消する施術を行っております。
当院だからこそ出来る筋膜リリースの施術やその驚きの効果についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事を覗いてみてください。
さらに、痛みを今すぐどうにかしたい方に向けて、あなたの痛みに効く具体的な筋膜リリースの方法をLINEから無料でお伝えしています。
ぜひご活用ください。
首の痛みがある時に考えられる事
首の痛みがある時に考えられる事としては、おもに以下の3つです。
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 頚椎症性脊髄症
- 頚椎症性神経根症
それぞれ解説していきます。
頸椎椎間板ヘルニア
ヘルニアと聞くと腰をイメージするかもしれませんが、首でもヘルニアは起こる可能性があります。
原因としては、背骨をつなぐクッションの役割をしている椎間板がおもに加齢変化により後方に飛び出すことによって起こります。
30~50歳代に多く、しばしば誘因なく発症します。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
症状としては、首や肩にしびれや痛みが出たり、指の細かい動きが難しくなり、ボタンをとめにくくなったり、箸が使いにくくなったりします。
ただ、頚椎は第1頚椎から第7頚椎まで7つの頚椎から構成されており、ヘルニアが頚椎のどこで起こるかによって症状が異なります。
よく起こりやすい場所は、第5頚椎から第7頚椎の間で、首の後ろ側で付け根辺りから肩の外側、腕の外側から親指にかけて症状が出やすいです。
※ヘルニアなどの頸椎が原因の首の痛みは危険な動きで症状を悪化させてしまうため要注意です。
具体的な注意点や対処法は以下の記事に詳しく記載してあります。
頚椎症性脊髄症
頚椎が何らかの原因で変形してしまう病気を頚椎症と言います。
頚椎症によって神経が圧迫されることでしびれや痛みが出現するのですが、背骨の後方にある脊髄の通り道の脊柱管で脊髄が圧迫されることで症状が出現する場合を頚椎症性脊髄症と呼びます。
原因としては、加齢変化による頚椎症(椎間板の膨隆・骨のとげの形成)の変化によって、頚椎の脊柱管(骨の孔)の中にある脊髄が圧迫されて症状が出ます。
日本人は脊柱管の大きさが欧米人に比較して小さく、「脊髄症」の症状が生じやすくなっています。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
症状が出る場所は脊髄が頚椎のどこで圧迫されるかによって異なります。
頚椎症性脊髄症がよく起こるのは第4頚椎から第6頚椎の間とされています。
しびれや痛みの出る場所としては、首の後ろ側で真ん中辺りから肩の外側から腕の外側を通って親指までの範囲です。
※すでに痺れや痛みが強い場合は、椎間板の変性が生じているケースが多いです。
下記の記事に詳しい原因や対処法を記載しているので、手遅れになる前にぜひ一読してみてください。
頚椎症性神経根症
脊柱管で脊髄が圧迫される頚椎症性脊髄症に対し、脊髄から枝分かれして背骨と背骨の間から出ている神経が圧迫されるのが頚椎症性神経根症です。
原因としては、加齢変化による頚椎症(椎間板の膨隆・骨のとげの形成)の変化によって、脊髄から分かれて上肢へゆく「神経根症」が圧迫されたり刺激されたりして起こります。
遠近両用眼鏡でパソコンの画面などを首をそらせて見ていることも原因となることがあります。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
症状としては、頚椎症性脊髄症と似ており、よく起こる場所も同じで、首、肩の外側から腕の外側、親指にかけてしびれや痛みが生じる可能性があります。
ツボとは
そもそも、ツボとは東洋医学では五臓六腑の異常が滞る場所とされています。
そこを鍼や灸、マッサージをして整え、滞っている異常を解放することで、体の不調を改善できるというものです。
ツボは全身に数多く点在しており、それぞれに効果が出やすい症状があります。
たとえば、眼精疲労や頭痛、めまい、肩こりなど、様々な症状に対応しているツボが存在します。
首の痛みも例外ではなく、首をはじめ、頭痛や肩の痛みに効果のあるツボもあるので、上手くやれば首の痛みを和らげることも不可能ではありません。
今回は首の痛みに効果のあるツボをいくつかピックアップして紹介します。
即効性もあるので、是非1つ1つ試してみてください。
首の痛みを和らげるために効果的なツボ
首の痛みを和らげるために効果的なツボはおもに以下の7つです。
- 肩井
- 臀臑
- 肩中兪
- 落沈
- 合谷
- 後渓
- 手三里
それぞれ解説していきます。
肩井
肩井の場所は、首の付け根の背骨と肩の外側の先端を結んだ線上の中間辺りに位置しています。
下をうつむくと、首の後ろで背骨が触りやすくなりますが、最も飛び出ている背骨が首の付け根の背骨です。
その背骨と肩の先端とを結んだ中間で肩井を探しましょう。
首こりや頭痛、歯の痛みに効果があります。
特に肩の筋肉と関連が深く、四十肩や五十肩といった肩の痛みや動きの悪さにも効果があるとされています。
肩の動きと首は関連が強いので、肩の症状を和らげることで首の痛みを和らげるという効果も十分に期待できます。
臀臑
臀臑の場所は、肩の外側先端と肘の外側を結んだ線上の中間辺りに位置しています。
首だけでなく、肩や腕の痛みにも効果的なツボです。
また、目の病気にも効果的とされています。
目で辺りを見渡す時は、目だけの動きでは広く見渡せませんが、首が一緒に動くことでより広い範囲を見渡すことができます。
このように、目と首の動きには深い関係があり、そういった意味でも臀臑は首や目の症状に効果があるのだと考えられます。
肩中兪
肩中兪の場所は、首の付け根の背骨から指2本分外側にいった所に位置しています。
肩井と同様に、うつむいた時に最も飛び出ている背骨が首の付け根にあたる背骨です。
それを目安に肩中兪を探しましょう。
首こりや頭痛、肩こりに効果的なツボです。
また、喘息や風邪をひいた時の咳、背中の痛みやむちうちの症状にも効果があります。
落沈
落沈の場所は、手の甲側で、人差し指と中指の骨を根元へたどっていき、2つの骨が交わる部分に位置しています。
ツボを押す時の注意点としては、骨を強く押すと痛みが出たり、最悪の場合骨折する可能性もあるので、骨は押さないように少し位置をずらして押すようにしましょう。
寝違えた時の首の痛みに高い効果を発揮します。
文字通り、首の痛みを楽ちんにしてくれます。
合谷
合谷の場所は、手の甲側で、親指と人差し指の骨を根元へたどっていき、2つの骨が交わる部分に位置しています。
このツボも落沈と同様に、骨に近い所に位置するツボなので、骨を直接強く押さないように注意が必要な場所です。
首から上の症状に効果的で、首こりや肩こりはもちろん、疲れ目や頭痛、歯の痛み、鼻水にも効果的だとされています。
また、自律神経を整える働きもあり、疲れやストレスを緩和する効果も期待できます。
後渓
後渓の場所は、小指の外側を先端から根元へ向かってなぞっていくと、根元で骨が出っ張っている部分に当たります。
その骨のすぐ下に後渓があります。
ここも落沈や合谷と同様に、骨が近くにあるので、骨を強く押さないように注意しましょう。
寝違えによる首の痛みや肩こり、頭痛、目の疲れに効果的なツボです。
手三里
手三里の場所は、肘を曲げたときにできるしわから肩の方向へ指3本分の場所に位置しています。
肩こりや寝違えなどの首周辺の症状をはじめ、腕の痛みに効果的です。
また、手三里は大腸を整えてくれるとされており、便秘や下痢にも効果的なツボです。
ツボをほぐす方法
ツボをほぐすための方法ですが、おもに以下の4つあります。
- 押す
- 鍼
- お灸
- 温める
それぞれにメリットやデメリットがあるので、ご自身に合った方法で試していただければと思います。
それぞれ解説していきます。
押す
これは道具もいらず、ツボの場所が分かればどこでも場所もとらずにすることができるので、個人的には一番自分でもやりやすい方法ではないかと思います。
効果的なツボの押し方としては、以下の点に注意してツボを押してみてください。
- 指の腹で垂直に押す
- 気持ち良い強さで押す
- 力任せに強く押さず、軽く押す
- 5秒くらいかけてゆっくりと押していき、ゆっくりと戻す
- 押せば押すほど良いわけではなく、1日5回程度にしておく
- 押した後にあざになっていたり、痛みがある場合は押し過ぎなので注意
ツボはピンポイントに存在しているため、見つけるのが難しいです。
見当違いの場所を押しても十分な効果は得られません。
ツボを見つけるポイントとしては、押すと体の奥の方にジーンと届く感じがして、痛いけど不快ではないような感覚があります。
感じ方には個人差があるので、一概には言えませんが、これを目安にツボを探して押してみてください。
鍼
ツボに対する鍼治療は、ツボに対して鍼を刺すという方法です。
鍼治療による効果としては、鍼による刺激が自律神経や免疫の働きなどに作用することで、筋肉の緊張を和らげたり、血液やリンパ液の流れを良くすることで、自然治癒力を高める効果が期待できます。
また、鍼を通して微弱の電流を流すことで、表面だけでなく深層の筋肉を刺激して緊張を和らげたり、神経への血流を良くすることで、神経の過活動を抑える効果も期待できます。
お灸
もぐさと呼ばれるヨモギの葉の裏にある白い綿毛からできたものを使う方法です。
もぐさをツボの上に置き、火を点けて温めることでツボに刺激を与え、血流を促します。
効果としては、まず温めること自体が血流を促し、むくみの改善に繋がりますし、血流が悪い部分をピンポイントで狙って温めることができるというメリットもあります。
さらに、もぐさにはシネオールという成分が含まれており、消毒、殺菌、鎮静、鎮痛作用があるとされており、痛みを和らげたり、リラックス効果も期待できます。
温める
これはお灸と少し内容が被ってしまいますが、お灸は準備に手間が必要だったり、火を使うのでやけどや家事の危険性も少なからずあります。
そういった手間やリスクが嫌な方は、カイロでツボを温めたり、お風呂で浴槽に使ってツボごと体全体を温めるという方法も効果的でしょう。
カイロであれば、ツボの細かい位置が自分では分かりにくくてもツボ周辺をまとめて温めることができます。
お風呂で温める方法もツボの位置まで見つけられなくても良いですし、ツボの場所がある程度分かれば入浴しながらツボをほぐすことでさらに効果を高めることも期待できます。
※ツボの他にも痛みを即時的にとる方法として、あなたの痛みに効くおすすめの筋膜リリース動画をLINEから無料でお伝えしています。
理学ボディのおすすめ
首の痛みに関わるツボを押しているが中々治らない、ツボの他にもストレッチや筋トレをしているが治らないという方は理学ボディで施術を受けることがおすすめです。
理学ボディでは、最短で痛みを改善させることにこだわっており、筋膜という組織に対して施術を行います。
筋膜は筋肉を覆っている膜状の組織で、筋膜が硬くなると筋肉の柔軟性が低下、筋力が発揮しにくいなどが起こります。
筋膜の硬さのある場所はピンポイントで存在しているため、ストレッチでは中々ほぐすことができません。
ツボをほぐしたとしても、筋膜の硬さまではほぐすことはできません。
もし、筋膜の硬さが痛みに影響しているのなら、ストレッチやツボをほぐしていても中々改善することは難しいでしょう。
ですが、筋膜の施術に精通している理学ボディのセラピストなら、ピンポイントの硬さでも見つけることができます。
もし、首の痛みが治らなくて困っているという方は、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。
以下のLINEをお友達登録していただき、簡単な質問にいくつかお答えいただくだけで、あなたの痛みがどういったものか、その痛みを改善するためのマッサージ動画をお送りします。
すぐにできますので、まずは自宅であなたの痛みがどれだけ改善するのか試してみてください。