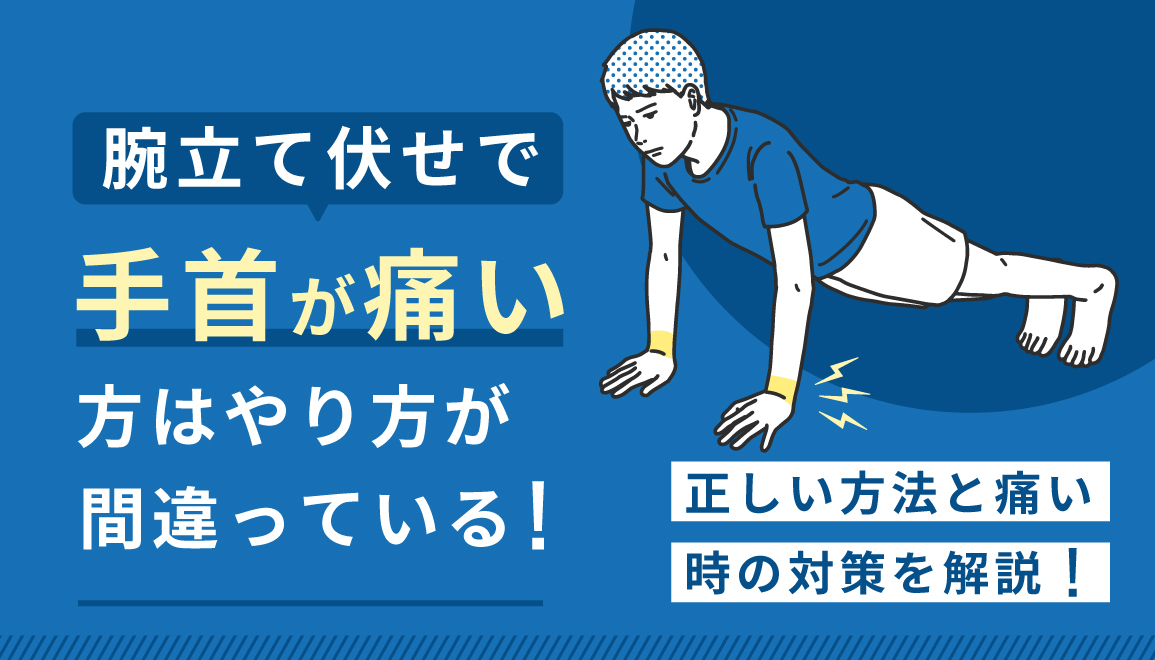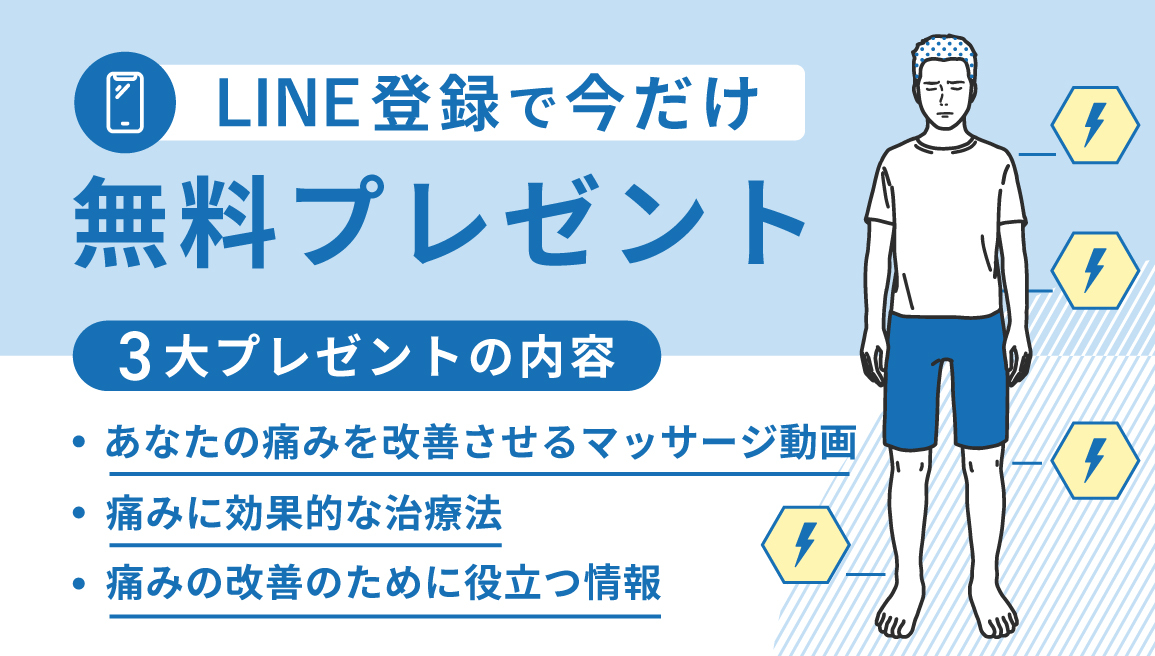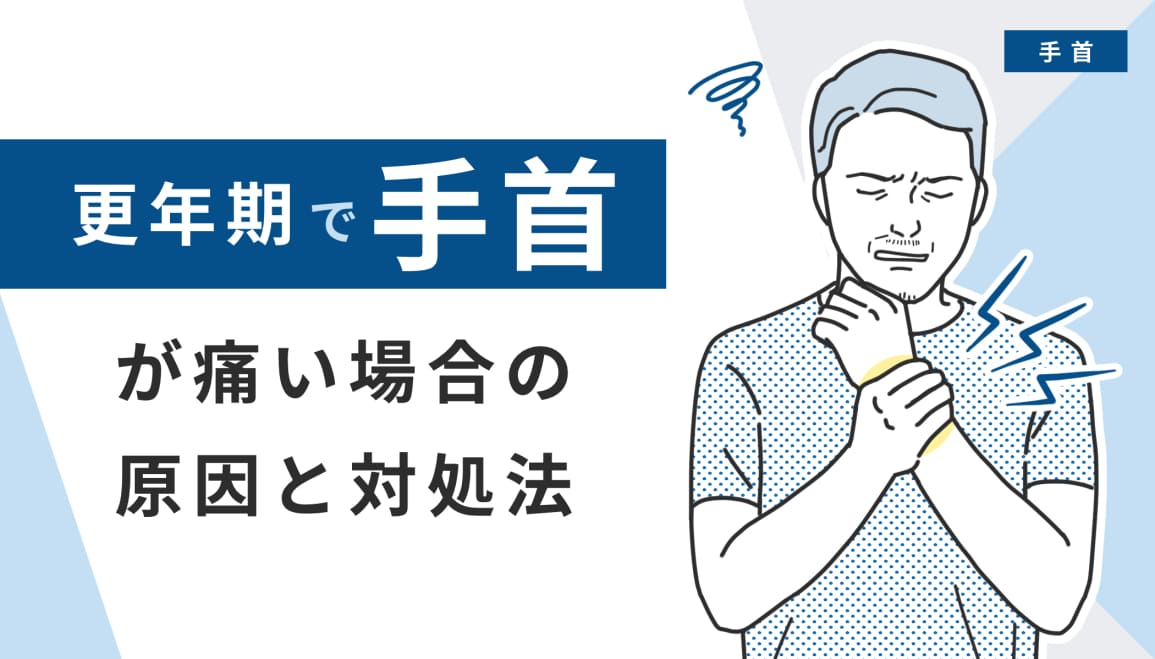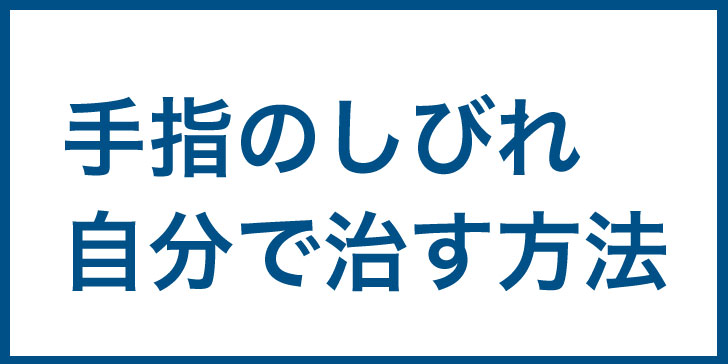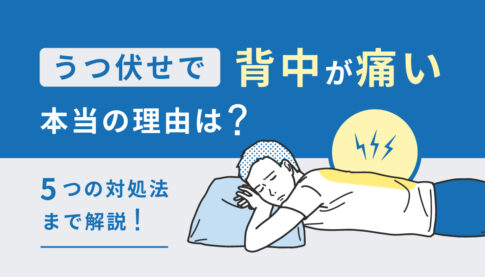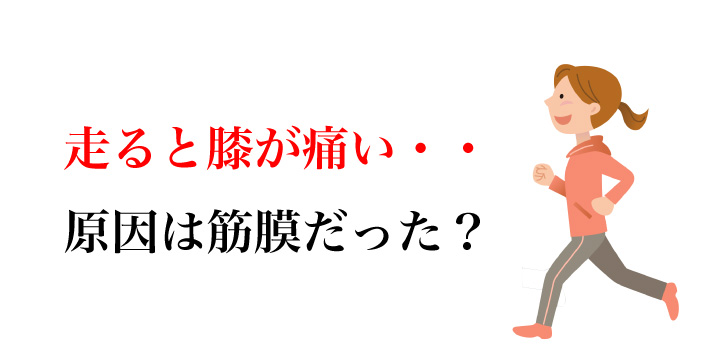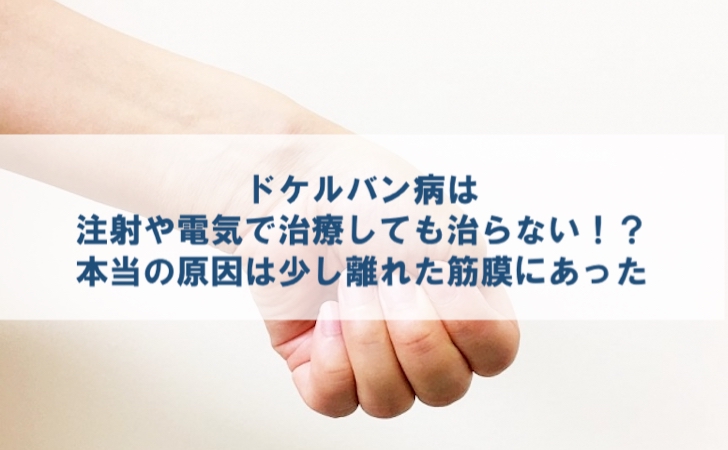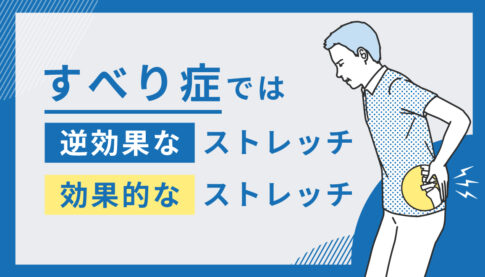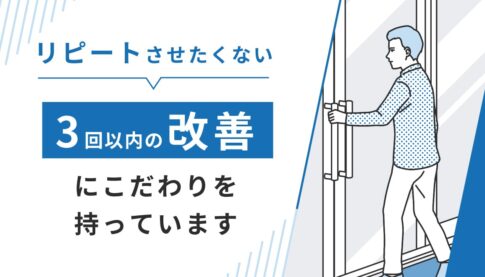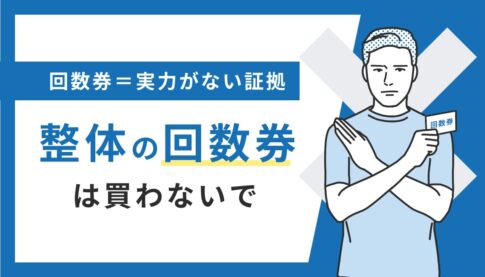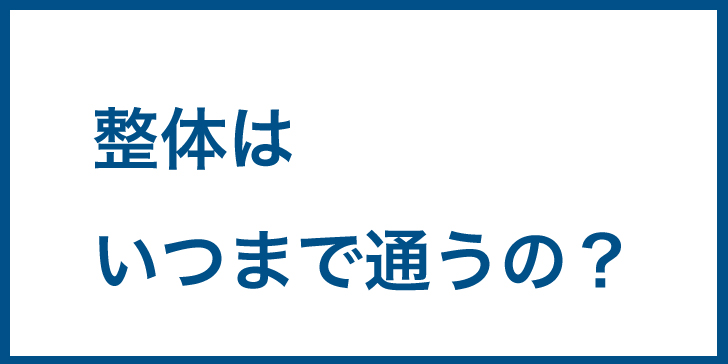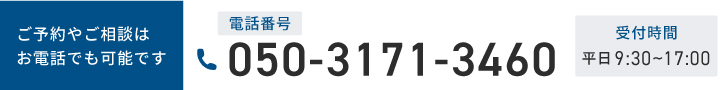腕立て伏せをすると、手首が痛くなって続けられない。
腕立てで手首が痛くなるのは、筋肉が弱いからかも。
このような悩みありませんか?
もちろん、手首の筋力が弱いことも原因の1つかもしれません。
ですが、それだと手首の筋力がつかないとずっと痛いままです。
筋力はあくまで1つの要因であって、やり方を変えるだけで痛みが楽になることも大いにあります。
そこで、今回は手首を痛めない腕立て伏せの正しいやり方と手首が痛い時の対策を解説します。
腕立て伏せで手首が痛くなる原因
腕立て伏せで手首が痛くなる原因としては、おもに以下の3つです。
- フォームに原因がある
- 回数が多すぎる
- 負荷が強すぎる
それぞれ解説していきます。
フォームに問題がある
腕立て伏せで手首を痛めてしまうのは、そもそものフォームに負担がかかる原因があることが考えられます。
手首の関節は親指側へは動きが小さく、小指側への動きが大きいことが特徴です。
そのため、指を内側へ向けた状態で腕立て伏せの姿勢になると、手首の関節の動きを小さくした状態で手首を反らしていることになります。
一方、指を外側へ向けた状態で腕立て伏せの姿勢になると、手首の関節の動きを大きく、動きやすくした状態で手首を反らしていることになります。
前者では、関節の動きを制限した状態で手首を反らすという大きな動きを求めており、かつ、腕立て伏せで体重が加わるので、大きな負担となっている可能性が高いです。
後者の方が、手首の関節には動きの幅に余裕があるので、負担は0にはならないにせよ、負担を小さくして腕立て伏せすることができるはずです。
回数が多すぎる
回数を増やせば、少ない回数で腕立て伏せするよりも効率良く腕や胸を鍛えられるのは事実です。
ですが、自分の限界を超えた回数でやり続けるのは逆効果です。
ある程度の負荷をかけないと筋肉を鍛えられないのは事実ですが、明らかに強すぎる負荷は効率的ではありませんし、手首を痛める可能性が高くなります。
効率良く鍛えるには、どれくらいの負荷で行えば良いかは科学的に示されていますので、それに従って回数を決めるのが良いでしょう。
負荷が強すぎる
回数が適正だったとしても、負荷が強すぎるとやはり手首を痛める可能性が高くなってしまいます。
たとえば、ゆっくりと時間をかけて肘を曲げ、同じように時間をかけて肘を伸ばしていくというやり方では、普通にするよりも強く負荷が加わります。
また、手をつく幅を広くつけばつくほど、腕立て伏せする時に大きな力が加わりますので、負荷が強くなります。
どちらも実際にやってみると違いははっきりと分かるはずです。
あえてそうした方法を行う人もいるかもしれませんが、手首が痛くなってしまう場合は正しいやり方で行うのが良いでしょう。
手首が痛い時に考えられる事
手首が痛い時に考えられる事としては、おもに以下の4つです。
- 手根管症候群
- 腱鞘炎
- 変形性手関節症
- TFCC(三角繊維軟骨複合体損傷)
それぞれ解説していきます。
手根管症候群
手根管とは、手のひらにある複数の小さな骨とその上を横切る靭帯とで作られるトンネルのような空間のことを指します。
そのトンネルにはいくつかの腱と神経が通っており、ここが圧迫されたり、腱や神経がこすれる摩擦によってしびれや痛みが起こることを「手根管症候群」と呼びます。
原因としては、特発性というものが多く、原因不明とされています。
妊娠・出産期や更年期の女性が多く生じるのが特徴です。
そのほか、骨折などのケガ、仕事やスポーツでの手の使いすぎ、透析をしている人などに生じます。
■参照元:公益社団法人日本整形外科学会
腕立て伏せの時以外に、以下のような症状がある場合は手根管症候群の疑いがあるので、一度整形外科を受診し診察してもらうことをお勧めします。
- 夜中から明け方にかけて強くなる痛み
- 手を使う作業、運動時に強くなる痛み
- 手を振ることで痛みが和らぐ
- 親指、人差し指、中指と薬指の親指側の痛み、しびれ
腱鞘炎
腱鞘炎とはよく聞きますが、実は以下の2種類あります。
- 尺側手根伸筋炎
- ドケルバン病
尺側手根伸筋炎は、手首の小指側を通る腱で手首を小指側に倒す働きがある尺側手根伸筋腱の炎症を指します。
ドケルバン病は、手首の親指側を通る短母指伸筋腱と長母指外転筋腱の炎症を指します。
これらの腱が周りの靭帯や骨とこすれて炎症を起こすことが原因で痛みを引き起こします。
原因としては、ドアノブを回すような手首の動きや不慣れな手作業、手を酷使する作業などが挙げられます。
妊娠出産期の女性や更年期の女性にも多く生じます。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
以下のテストでそれぞれ小指側に痛みがある場合は尺側手根伸筋腱炎、親指側に痛みがある場合はドケルバン病の可能性があります。
小指側の腱鞘炎を評価するテスト(合掌回外テスト)
- 胸の前で手のひらを合わせて合掌する
- 合掌したまま、指を下に向けるように手首を動かす
- この時に痛みが出れば尺側手根伸筋腱炎の可能性あり
親指側の腱鞘炎を評価するテスト(Eichhoff test)
- 親指を人差し指から小指で握り込む
- 握り込んだまま小指側へ手首を倒す
- この時に痛みが出ればドケルバン病の可能性あり
変形性手関節症
関節の間に存在する関節軟骨の異常による症状を指します。
手首を繰り返し使うような運動、作業によって、軟骨が変形したりすり減ることで、手首の周りに炎症が起こって痛みを伴うようになります。
その症状としては、手首の周りの痛みや腫れ、動かした際の引っかかる感じ、違和感が挙げられます。
以下の症状に当てはまる場合、変形性手関節症の可能性があります。
- 手の痛み、うずき、こわばり
- 左右の親指の第1関節、人差し指、中指の第1、第2関節のうち、2つ以上に関節のこわばりと腫れがある
- 左右の親指の第1関節、人差し指、中指の第1、第2関節のうち、1つ以上に関節の変形がある
- 各指の第1関節の腫れは合計2つ以下
- 各指の第2関節のこわばりと腫れは合計2つ以上
TFCC(三角繊維軟骨複合体損傷)
TFCCとは、小指側の手首と腕をつなぐ複数ある靭帯や腱の総称を指します。
そして、TFCC損傷とはスポーツや外傷、手首の使いすぎによって、手首の小指側のTFCCに痛みを感じることを指します。
手首はよく動く関節であるが故に、とても負担がかかりやすい関節でもあります。
そんな手首にかかる負担を減らすのがTFCCで、クッションのような役割を担っています。
TFCCが損傷すると、そのクッションの役割が果たせなくなり、骨や腱、靭帯同士ですれて炎症を起こすので痛みを感じるようになります。
以下のテストで手首の小指側に痛みが出現する場合、TFCC損傷の可能性が高くなります。
骨や靭帯が原因の痛みを評価するテスト(Ulnocarpal stress test)
- 手首を真っ直ぐに保つ
- そのまま手首を小指側に倒す
- 痛みが出ればTFCC損傷の可能性あり
腕立て伏せで手首が痛い時の対策
腕立て伏せで手首が痛い時の対策としては、おもに以下の5つが挙げられます。
- 手首のストレッチ
- サポーターを装着する
- プッシュアップバーを使う
- 正しいフォームで行う
- 自分にあった負荷や回数で行う
それぞれ解説していきます。
手首のストレッチ
腕立て伏せの姿勢になると、手首が反らされるので、肘から下の手のひら側の筋肉が伸ばされます。
ここには、橈側手根屈筋や尺側手根屈筋と呼ばれる手首を手のひら側に曲げる筋肉があります。
ここの筋肉が硬くなると、手首を反りにくくなるので腕立て伏せの姿勢をとるだけでも手首には負担がかかります。
その状態で腕立て伏せをすることで、手首を痛めてしまう可能性があるので、ここが硬くて痛みが出てしまう場合は、ここの筋肉をストレッチすることが効果的です。
- 四つん這いになる
- 指先を自分に向け、肘を完全に伸ばす
- おしりをかかとにつけるように、重心を後ろへ移す
- 手首が伸ばされると感じる位置で15〜20秒キープする
- 2〜3セット行う
ポイントとしては、重心が前すぎたり、肘が曲がっていると、上手くストレッチすることができないので、注意しましょう。
サポーターを装着する
サポーターは関節の動きを制限して、動きすぎないようにすることで、痛みを出にくくしてくれます。
手首の動きが制限される分、腕立て伏せはしにくくなるかもしれませんが、関節に過剰に負担がかかることは避けられるので、一度試してみる価値はあるでしょう。
プッシュアップバーを使う
プッシュアップバーとは、床に取っ手のようなものを置き、それを握って腕立て伏せするための道具です。
腕立て伏せで手首が痛くなる方は、手首が反らされたまま体重が加わることが負担になっています。
なので、プッシュアップバーを使うと手首を反らなくても良いので、反らされることによってかかっていた負担はなくなります。
ただ、プッシュアップバーを握ったまま体重がかかるので、手のひらが痛くなってしまうかもしれません。
その場合は、手袋やタオルをかませるなどすることで、痛みを和らげることができます。
正しいフォームで行う
指の向きが過度に内側や外側を向いていたり、手の位置が過度に前後や内側、外側にずれていると、正しく腕立て伏せすることができず、手首を痛めてしまう原因になります。
上級者や慣れている方はあえてそうする場合もありますが、慣れない方や手首を痛めてしまう方は、まずは正しいフォームを身につけましょう。
一般的に言われている正しいフォームは以下の通りです。
- 肩幅より少し広いくらいの位置に手を置く
- 指先は真っ直ぐ前に向ける
- 足はこぶし一個分程度に開く
- 首からかかとまでがなるべく一直線になるようにする
これを守って腕立て伏せすると、過度に手首に負担がかかることは避けられるはずです。
自分に合った負荷や回数で行う
自分に合った適切な負荷や回数で行うことは、腕立て伏せに限らず、トレーニングを行う上で重要なことです。
筋トレの効果がどのようにして決まるかと言うと、総負荷量によって決まります。
総負荷量とは、「強度×回数×セット数」で決定されます。
強度とは、たとえば重りをつけて運動したり、あえて動かしにくい位置に関節を置いて運動したり、ゆっくりと運動して負荷をかけたりなどが挙げられます。
腕立て伏せの場合、重りをつけるなどはやりにくいですし、手のつく位置を広げると負担になって手首を痛める可能性もあります。
なので、強度以外の回数やセット数で調整するのが良いです。
一度に多くの回数をこなさないと意味がないと思っている方もいるかもしれません。
ですが、3つの要素のかけ算なので、回数が少なくてもセット数を増やせば同じだけの効果は得られます。
また、一般的に筋肉をつけるためには、限界の7〜8割くらいの強度で筋トレをこなす必要があるとされています。
たとえば、腕立て伏せを連続で10回が限界の場合、7〜8回くらいは行う必要があるということです。
ただ、それだと強度が強すぎて手首を痛めてしまう場合もあるので、上記の強度×回数×セット数に則って、回数を減らしてセット数を増やすやり方が良いでしょう。
手首にかかる負担を減らしながら、効果もちゃんと得られるので、お勧めの方法です。
理学ボディのおすすめ
今回紹介した対策を実践しても中々痛みがなくならないという方は、理学ボディで施術を受けることがおすすめです。
理学ボディでは、最短で痛みを改善させることにこだわっており、筋膜という組織に対して施術を行います。
筋膜は筋肉を覆っている膜状の組織で、筋膜が硬くなると筋肉の柔軟性が低下、筋力が発揮しにくいなどが起こります。
筋膜の硬さのある場所はピンポイントで存在しているため、ストレッチやマッサージでは中々ほぐすことができません。
もし、筋膜の硬さが痛みに影響しているのなら、ストレッチやマッサージをしていても中々改善することは難しいでしょう。
ですが、筋膜の施術に精通している理学ボディのセラピストなら、ピンポイントの硬さでも見つけることができます。
もし、手首の痛みがなくならなくて困っているという方は、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。
以下のLINEをお友達登録していただき、簡単な質問にいくつかお答えいただくだけで、あなたの痛みがどういったものか、その痛みを改善するためのマッサージ動画をお送りします。
すぐにできますので、まずは自宅であなたの痛みがどれだけ改善するのか試してみてください。