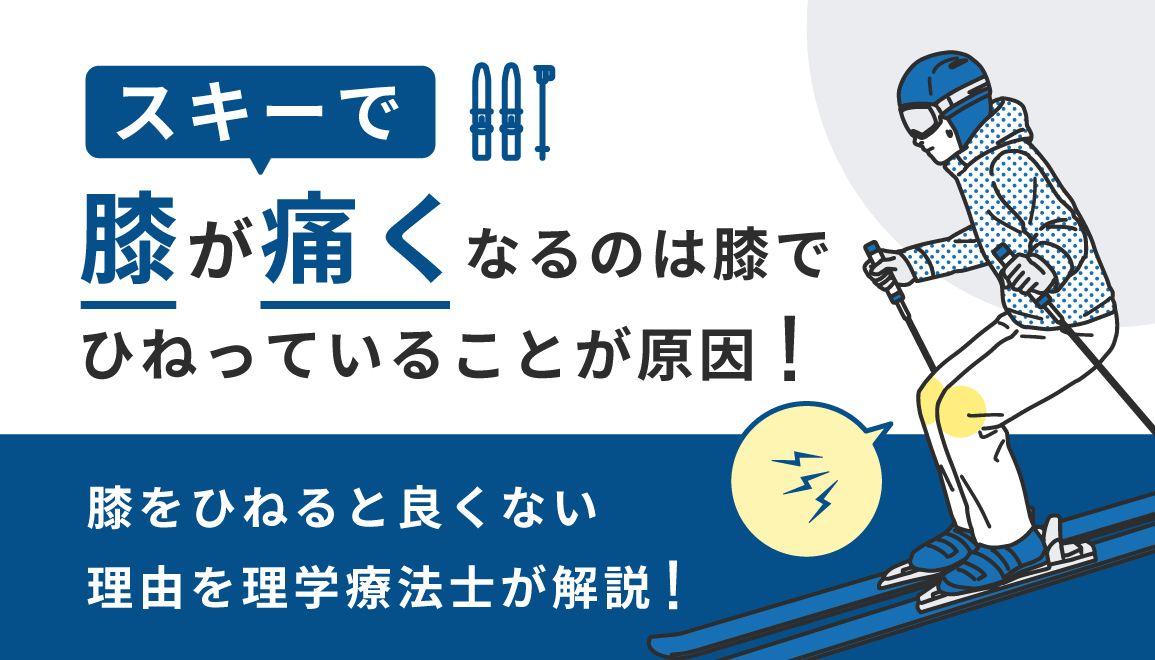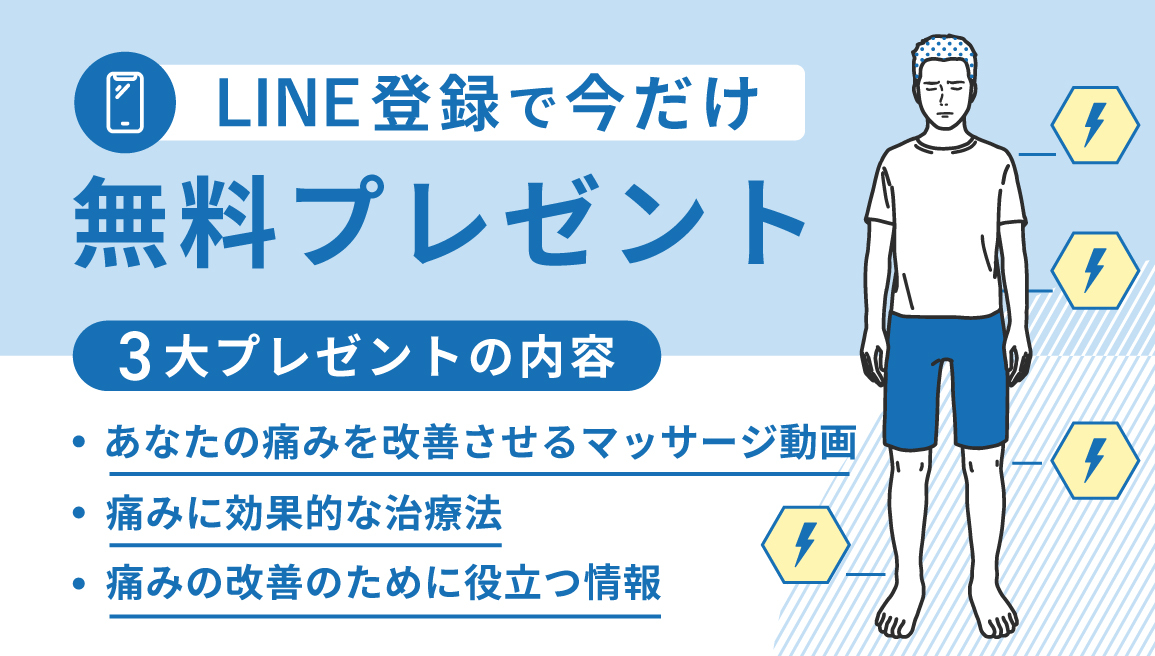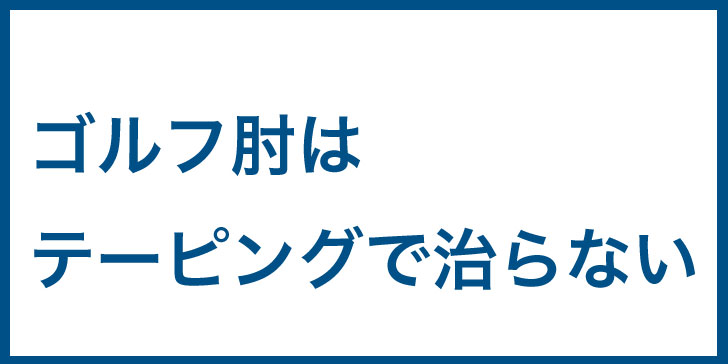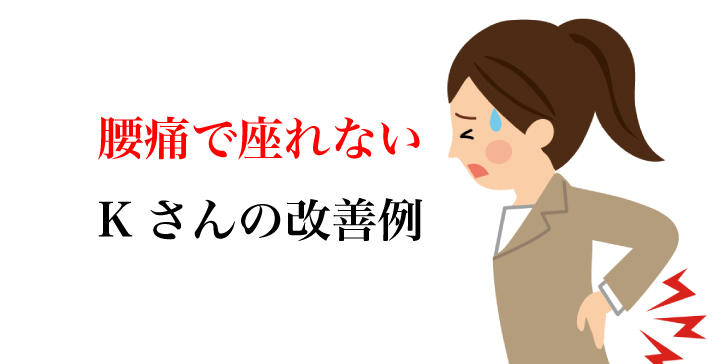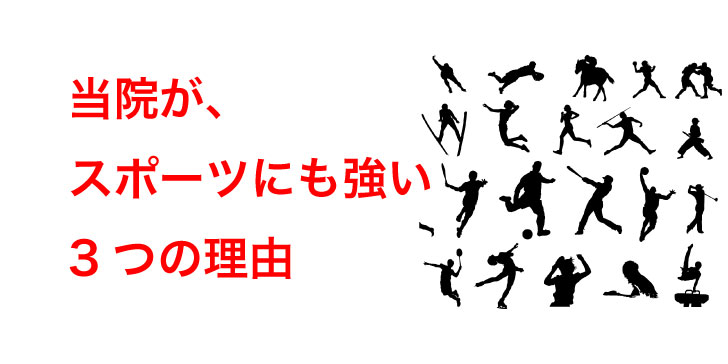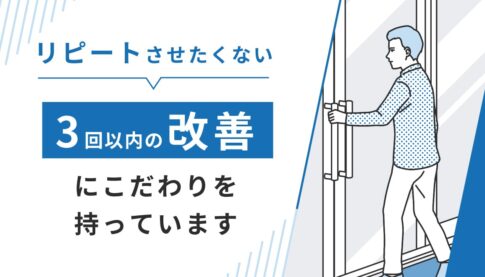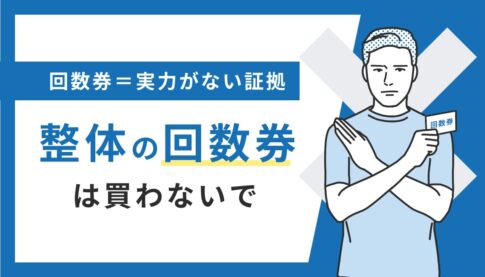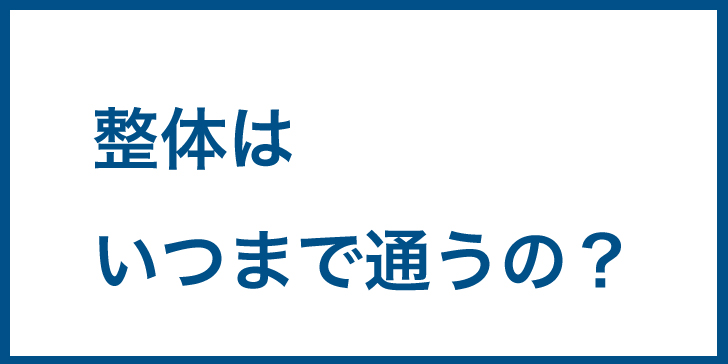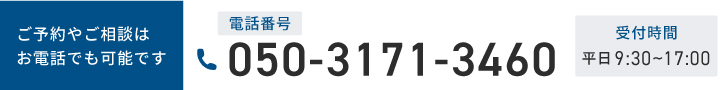スキーを始めたが膝が痛くなってしまった。
久しぶりにスキーをすると、膝が痛くなって満足に滑れなかった。
スキーをした後から膝が痛くて心配になっている。
このような悩みありませんか?
結論から言うと、スキーで膝を痛めてしまう方は、膝を支点に体をひねっている場合が多いです。
膝はひねるようにはできていないので、そういった動きばかり繰り返していると、いつか痛めてしまうことはむしろ必然でしょう。
そこで、今回はスキーで膝が痛い理由や膝が痛い時に考えられる事、痛い時の対策を解説していきます。
スキーで膝が痛い理由
スキーで膝が痛い理由としては、膝に動きを超えた過剰な負担がかかってしまうことが大きいです。
関節の動く範囲内であれば、それほど大きな問題にはなりませんが、本来動かない方向なんかに動かすと痛めるのは当然ですよね。
それを踏まえ、スキーで膝が痛くなる理由としては以下の3つが挙げられます。
- 膝を支点にひねっている
- 膝を横に動かしている
- 転んだ時に膝が過剰に曲がった
それぞれ解説していきます。
膝を支点にひねっている
スキーでは、方向を変えたり、止まる時にブレーキをかけるため、どちらかの足を支点にします。
たとえば、右へ曲がる際は右足を支点にして体を右側へ傾けていきますよね。
この時、膝を支点にして曲がると膝を痛くしてしまう可能性が高いです。
そもそも、膝関節はひねる動きはほとんどできず、曲げ伸ばしがおもな動きです。
そのため、ひねる動きが過剰に求められると、後述しますが、靭帯や半月板に負担となり損傷してしまう可能性が高いです。
膝を横に動かしている
スキーでターンをする時、板を傾けてエッジングする時、膝を内側あるいは外側へ横に動かしているように見えます。
ですが、上述したように、膝関節は曲げ伸ばしがおもな動きです。
ひねる動きはもちろん、横へ水平移動するような動き方もできません。
なので、エッジングする時になどに膝を支点に横へ動かそうとすると、靭帯や半月板に過剰な負担となってしまう可能性があります。
転んだ時に膝が過剰に曲がった
スキーを始めたばかりの初心者の方は、滑り慣れていないので転んでしまうこともあるでしょう。
ですが、転び方にも注意しないと膝を痛めてしまう可能性があります。
スキーでは、足がスキー板に固定されており、板は長いので、真っ直ぐ後ろへおしりをつけようと思っても足の固定や板の長さが邪魔になって上手くできません。
そのため、滑っている時に転んでしまった際、とっさに後ろの方へ転んでしまうと、足の固定が支点になって膝が過剰に曲がってしまいます。
足が固定されていなければそんなことはないのですが、足は固定され、膝が曲げられるので筋肉や靭帯に引っ張られて、すねの骨が強く前に引かれます。
この時に、強く前に引かれることが原因で靭帯損傷を引き起こす可能性があります。
膝は曲げ伸ばしが得意な関節ではありますが、固定されている部位などによっては強い力が加わってしまう可能性があるので、注意が必要です。
スキーで膝が痛い時に考えられる事
膝が痛い時に考えられる事としては、おもに以下の5つです。
- 靭帯損傷
- 半月板損傷
- 変形性膝関節症
- 腸脛靭帯炎
- 鵞足炎
それぞれ解説していきます。
靭帯損傷
膝関節には大きく分けると4つの靭帯が存在しています。
- 膝の前に付着する前十字靭帯
- 膝の後ろに付着する後十字靭帯
- 膝の内側の内側側副靱帯
- 膝の外側の外側側副靭帯
このように、前後、左右から膝を守ってくれているのが上記の4つの靭帯です。
一般に外反強制により内側側副靱帯が、内反強制により外側側副靭帯が損傷し、また脛骨上端の前内方に向かう外力で前十字靭帯が、後方への外力で後十字靭帯が損傷します。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
外反と言うのは膝が内側に飛び出ているいわゆるX脚のような形、内反と言うのは膝が外側に飛び出ているいわゆるO脚のような形のことを指します。
スポーツ中や交通事故など、その他大きな力が膝に加わって外反や内反へ強制されると、各靭帯が損傷される可能性があります。
スキーにおける靭帯損傷としては、転倒時に膝が過度に外反強制されたり、強く曲がる際に固定されたスキーブーツが支点になって、すねの骨が強く引き出されたり回旋が加わることで受傷する場合が多いです。
症状としては、受傷直後は痛みや関節の動きの悪さ、腫れが主症状で、しばらくするとそれらの症状は軽快していきますが、靭帯による膝の安定が得られないので、膝の不安定感が目立ち、下り坂やひねる動きの際に顕著に出現します。
そのままにしておくと、さらなる膝の痛みや半月板の損傷につながる可能性もあるため、リハビリで筋力をつけたり、サポーターで膝を安定させる、場合によっては手術が必要なこともあります。
半月板損傷
半月板とは、C型をした軟骨様の板で内側・外側にそれぞれがあり、クッションとスタビライザーの役割をはたしています。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
簡単に言うと、膝にかかる衝撃を吸収し、膝を安定させてくれる役割を持つのが半月板です。
ですが、膝にかかる負担が大きい、偏った負担が繰り返し膝にかかると、半月板はその許容範囲を超えて損傷してしまう場合があります。
その結果、半月板が損傷すると半月板損傷と診断されます。
症状としては、半月板が損傷すると、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。
ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなるロッキングという状態になり、歩けなくなるほど痛くなります。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
バスケットボールやサッカーなどのスポーツ中の受傷が多いとされ、スキーの場合も上述したように転倒時の過度な外反強制や深く曲げられた際に受傷する場合があります。
程度が軽い場合はリハビリテーションや痛み止めで良くなっていきますが、重症の場合は手術で半月板を縫い合わせたり、取り除くことが必要になることもあります。
変形性膝関節症
変形性膝関節症とは、関節軟骨が年齢とともに弾力性を失い、使い過ぎによりすり減り、関節が変形するというものです。
■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会
症状としては、歩き始めや立ち上がった瞬間の痛み、正座、階段の昇り降りの痛み、しにくさが挙げられます。
原因としては、加齢による関節の衰え、肥満、遺伝、骨折や半月板損傷などの外傷によるものが考えられます。
ただ、変形性膝関節症は骨折や靭帯損傷のよに、ある日突然なるものではなく、上記の影響で徐々に関節の変形が進行することで発症するものです。
痛みが出る前に、膝の曲げ伸ばしのしにくさや違和感などがあるはずなので、そういったものがなく、急に痛みが出た場合は変形性膝関節症である可能性は低いでしょう。
ですが、自覚症状はなくても変形性膝関節症が進行していて、スキーをきっかけに膝へ過剰に負担がかかることで痛みが出現したという可能性は0ではありません。
痛みがなくても変形性膝関節症と診断される方もいるので、痛みや膝の動かしにくさがなければ違うというわけでもないのです。
腸脛靭帯炎
腸脛靭帯と言うのは、おしりの外側から膝の外側まで伸びる長い靭帯のことを指します。
腸脛靭帯炎はそこが炎症を起こすことで、別名ランナー膝とも言われ、マラソンをする方に多く見られ、足を酷使した際に膝の外側にズキズキとした痛みを生じるのが特徴です。
ただ、これはマラソンをする方だけに起こるわけではなく、膝の外側や内側、前側に偏って体重をかけて歩いたり走る、立つ、歩くことで筋肉が過剰に緊張する部位が出てきます。
スキーにおいても、滑っている時に膝を過度に曲げている、ターンの時に膝を支点にひねっているということがあると、腸脛靭帯で炎症が起こる可能性はあります。
たとえば、外側に偏ると腸脛靭帯や外側広筋、内側に偏ると内側広筋や縫工筋、薄筋と呼ばれる筋肉が緊張します。
ある方向へ偏って力が加わった時、膝の曲がりすぎや、O脚のように外側へ飛び出るのをそれ以上いかないように、筋肉がそれを止めるように収縮します。
そのように、筋肉が何度も伸びたり縮んだりを繰り返すことで、筋肉は常に緊張した状態となり、痛みを伴うようになる可能性があります。
鵞足炎
鵞足と言うのは、太ももの内側から膝の内側へかけて伸びている3つの筋肉の総称で、鵞鳥の足のように見えることからそう呼ばれています。
この鵞足がある部分は、膝の曲げ伸ばしで伸びたり縮んだりするため、階段の上り下りなど膝の曲げ伸ばしを繰り返す動きで、炎症が起こり膝の内側にズキズキとした痛みが生じる可能性があります。
痛みが起こるメカニズムとしては、腸脛靭帯炎と同じようなものと考えられます。
スキーで膝が痛い時の対策
スキーで膝が痛い時の対策としては、一番は練習してスキー自体が上達することでしょう。
ですが、上達する前に怪我してしまっては元も子もないので、練習しながら並行して膝を痛めないような対策が必要です。
対策としては、おもに以下の3つが挙げられます。
- サポーター
- ストレッチ
- 筋トレ
それぞれ解説していきます。
サポーター
膝を支点にひねってしまうことが原因であれば、サポーターなどを使って膝を動きにくくすることで、負担を軽減するという方法は有効です。
サポーターは、動きすぎる関節の動きを抑制して、関節を守るという役割があるので、膝を支点にひねる、横へ動かすという滑り方をしてしまう場合はサポーターを使うのはありでしょう。
ストレッチ
膝を支点に滑るのが良くないと解説してきましたが、どこを支点にするのかと言うと、股関節です。
足の中でも股関節は曲げ伸ばし、開く閉じる、ひねるといったあらゆる方向への大きな動きが可能な関節です。
なので、膝を支点にターンするのではなく、股関節を支点にすると、膝へ過剰に負担をかけることなく滑ることができます。
そのためには、そもそも股関節の柔軟性が必要なので、ここでは股関節をひねる方向へのストレッチを紹介します。
内側へひねるストレッチ
- 仰向けになる
- 片側の膝を90度程度に曲げる
- 曲げた足を体の反対側へ動かし、床へ膝をつけるようにする
- 手で膝を軽く床方向へ押し、そのままの姿勢をキープする
- 15〜20秒程度ストレッチする
- 2〜3セット行う
ポイントとしては、足を反対側へ動かした時、股関節が硬い方は床に膝がつかないと思いますが、その時に動かす側の肩が浮かないようにしましょう。
肩が浮いてしまうと、股関節も上手くストレッチできないので注意しましょう。
外側へひねるストレッチ
- 四つ這いになる
- 膝を可能な限り横へ開く
- 両肘を前につく
- 股関節を曲げるように体を後ろへ動かす
- それ以上いかない位置でキープする
- 15〜20秒ストレッチする
- 2〜3セット行う
ポイントは、肘をついて股関節を曲げる際、腰が曲がらないように注意しましょう。
この時、頭が下がると腰も曲がってしまいやすいので、頭は上げたままキープしておくことも大事です。
筋トレ
膝関節は曲げ伸ばしは大きく動きますが、ここまで解説したように横やひねりの動きはほとんど動きません。
それだけに、筋肉の働きで膝を安定させることが重要です。
そこで重要となるのが、ハムストリングスという裏ももにある大きな筋肉です。
多くの人は前ももの大腿四頭筋が普段の生活の中で使われやすく、反対に裏もものハムストリングスは使われにくい傾向にあります。
なので、ハムストリングスが弱くなりやすいため、筋トレすることで大腿四頭筋とのバランスが取れ、膝を安定させやすくなります。
ハムストリングス
- うつ伏せになる
- 膝と膝の間は握りこぶし2個分ほどあける
- かかとをおしりの外側へ向かってゆっくりと曲げる
- 曲げられるところまで曲げたら、元の位置までゆっくりと膝を伸ばす
- 20回程度繰り返す
ポイントは、なるべくゆっくりと曲げ伸ばしをすることです。
筋トレというと強い力で瞬間的に力を入れることをイメージするかもしれませんが、普段の生活ではそのような場面はほぼありません。
むしろ、筋肉がゆっくりと伸ばされながらも力を発揮するような力の入れ方が求められるので、なるべくゆっくりと行うようにしましょう。
理学ボディのおすすめ
今回紹介した対策を実践しても中々膝の痛みがなくならないという方は、理学ボディで施術を受けることがおすすめです。
理学ボディでは、最短で痛みを改善させることにこだわっており、筋膜という組織に対して施術を行います。
筋膜は筋肉を覆っている膜状の組織で、筋膜が硬くなると筋肉の柔軟性が低下、筋力が発揮しにくいなどが起こります。
筋膜の硬さのある場所はピンポイントで存在しているため、ストレッチやマッサージでは中々ほぐすことができません。
もし、筋膜の硬さが腰痛に影響しているのなら、ストレッチやマッサージをしていても中々改善することは難しいでしょう。
ですが、筋膜の施術に精通している理学ボディのセラピストなら、ピンポイントの硬さでも見つけることができます。
もし、膝の痛みがなくならなくて困っているという方は、ぜひ理学ボディにお越しいただき、筋膜の施術を受けてみてください。
以下のLINEをお友達登録していただき、簡単な質問にいくつかお答えいただくだけで、あなたの痛みがどういったものか、その痛みを改善するためのマッサージ動画をお送りします。
すぐにできますので、まずは自宅であなたの痛みがどれだけ改善するのか試してみてください。